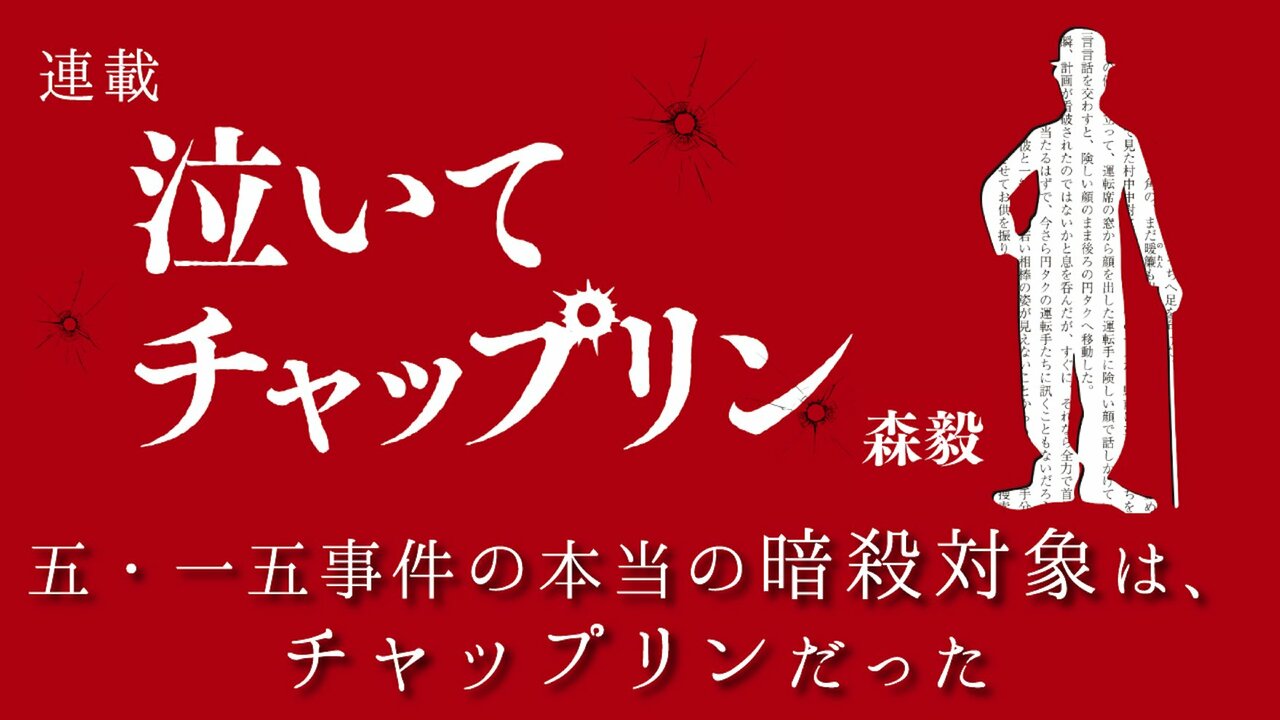五
「きみはまさか……まさか、チャップリンも道連れにしようと考えているわけじゃないだろうね?」
と、山内大尉もさすがに声を詰まらせて、コーヒーカップを机に戻した。
田島も静かにカップを置いた。
「たしかに、風が吹けば桶屋が儲かるというのは少々ナンセンスかもしれませんが、風が吹けば、やはり人々の暮らしや気持ちにも、それなりの影響を及ぼすのではないかと思います。しかもそれが人々が肝(きも)を潰すような突風であればなおのことだと思います。
しかし、その突風の詳しいお話をするまえに、大尉殿に一つお伺いしたいのですが、もし私がそんなことを実行したら、アメリカと戦争になると思われますか?」
大尉は失笑した。
「そいつはまた禅問答以上に難問だなあ。はたして鬼がでるか蛇(じゃ)がでるか、何れにしろ平穏無事というわけにいかないことだけは確かだろうな。
そうじゃないか、弓矢でバッファロー狩りをして大自然とともに牧歌的な暮らしをしていたインディアンから、ライフル銃にものをいわせて北米大陸を奪い、さらにハワイを併合して原住民を農奴同然に酷使し、今では数千キロも離れたフィリピン諸島まで植民地にしている国だからな。
ものの本によれば、インディアンの大量虐殺で名高いアメリカの第七代大統領アンドリュー・ジャクソンは、今のアメリカの基礎を築いた『軍神』として今も崇められているということも頭の片隅に止めておいたほうがいいしな。
いや、そんなアメリカばかりではなく、ヨーロッパの先進列強国にしても、かの文豪ゲーテの『強き光あるところには濃き影がつきまとう』という名言ではないが、若き日の夏目漱石(なつめそうせき)も、イギリス留学中の日記に、ロンドンという最先端の近代社会の底辺で働いている労働者の、わけても黒人やインド人など、最下層の有色人種の奴隷同然の惨めな暮らしぶりを目にして『文明の裏の悲惨』と、近代文明に対する不信感を記しているし、きみのいう通り、『アヘン戦争』のような手段を選ばぬ非人道的なやりかたで植民地を拡大して繁栄してきた、いや、いまだ現在進行形の植民地拡大の野望を棚に上げて、虐げられているアジアの国々や民族の解放を目指す、我国の満州開拓を非難するなど、片腹痛いかぎりだといってもいいだろう。
なかでも、前世紀からおよそ百年間、利己主義的なモンロー主義を貫いてきた超大国アメリカは、他国の戦争などには関わりたくないと孤立主義を貫いてきたにもかかわらず、先の世界大戦では、ドイツがヨーロッパ全土を席巻し、軍事的にも経済的にもアメリカを脅かす大国になるかもしれないという危機感から、イギリスの旅客船《ルシタニア号》がドイツの潜水艦に撃沈されて、偶々(たまたま)乗船していたアメリカ人百名ほどが犠牲になったことを口実にドイツに宣戦布告した国でもあるからな。
そして今度は、今や名実共に東亜の盟主となり、欧米列強国と肩を並べるまでになった我が国の目覚しい躍進ぶりに神経を尖らせ、新聞でも報道されているように、アメリカの太平洋艦隊はハワイ沖で実戦さながらの演習をしているというし、それが日米開戦の起爆剤になることも、一応想定しておかなければならないだろな。
またその背景には、これもきみのいう通り、『日清・日露戦争』以後、我国の勝利によって刺激されて、インドやアジアの各地でも民族意識が芽生え、マハトマ・ガンジーや孫文(そんぶん)といった有力な指導者も現れるなど、自主独立の気運が高まり、白人至上主義の欧米中心の国際秩序の崩壊の兆しに、アメリカもこれまでにない危機感を抱いているといったところが、現下の緊迫した国際情勢の根にあるといってもいいだろう。
さらに、その根っこには、ドイツの皇帝ウィルヘルム二世が主唱した、『かつての蒙古のごとく、日本を先頭とする黄人の興隆はヨーロッパ文明を破壊するであろう。ヨーロッパの先進列強国は一致してこれに対抗すべきである』という、岡倉天心も『滑稽』と批判しているように、自分たちがかつての蒙古のごとく、アフリカやアジアを侵略し民族固有の文明や文化を蹂躙(じゅうりん)し破壊してきたことを棚に上げた、人種差別もはなはだしいエモーショナルな『黄禍(こうか)論』があるのは間違いないだろう。
そしてその影響は、三年前のウォール街に端を発した『世界恐慌』に今も苦しんでいるアメリカにも波及して、日本の新聞でも報道されているように、失業者が街に溢れ、各地で暴動も頻発しているという社会不安が深刻さをますにつれ、その反動というか、トバッチリというか、日系移民に対する差別や排斥運動が日に日に激しくなっているというし、そうした様々な事情が重なって醸じょう成せいされた反日感情も無視できないからな……いやいや、ちょっと扱こき下ろし過ぎてしまったかな。でもアメリカに学ぶところは、それにもまして多々あるがね。
たとえば、このアメリカ文化の一つといってもいいコーヒーも、その一つだ。いや、オーバーではなく、中国から伝来したお茶が、今では日本の伝統文化になっているようにね」
と山内大尉は笑い、コーヒーカッブを手に取り、その香りを楽しむように口許に運んだ。
「ええ。今ではちょっとした街には、カフェの一軒や二軒はありますからね。
それに、『敵国外患なければ国亡ぶ』という意味でも、大いに学ぶべきだと思います」
と、田島も笑顔で応え、同じようにコーヒーを口にした。
「たしかに、その通りだ。しかし現下の我国の情勢も、満州事変を契機に、『国人がみだりに外戦に熱して』と、さっききみが話した福翁の言葉通り、日清戦争以後の好戦的な昂揚した雰囲気が再燃し、加熱しながら旋回上昇しはじめている感がないでもないからな。
つい先日の新聞にも、『宿命の日米戦争』と題するセンセーショナルな論説が掲載されていたばかりだが、かの『ポーツマス条約』に不満をもった民衆の『日比谷焼打ち事件』や、五年前の『金融恐慌』で、全国各地で銀行の取り付け騒ぎが起きたことでも分かるように、いつの時代でも民衆というのは、社会の雰囲気や風潮に呑まれやすく流されやすいし、こちらもやはり、そうした強硬論を唱えることが愛国心であるかのようなエモーショナルな風潮が、今や軍人や政治家ばかりではなく、地方人(一般市民)にも浸透しはじめているようだし、満州事変もいまだ完全に収束したとはいえない今、アメリカの出方次第では、文字通り『前門の虎、後門の狼』といった、神風が吹くことを祈願しなければならないような、『元寇(げんこう)』以来の絶体絶命のピンチになることも、やはり覚悟しておかなければならないだろう。
とはいえ、その日米戦争に関しては、あの天才的な作戦参謀の石原莞爾(いしはらかんじ)中佐が、それが文字通り徹底的な殲滅戦(せんめつせん)、すなわち全国民を巻き込んだ空前絶後の総力戦になることを、陸大(りくだい)(陸軍大学)を卒業して『大学仰付(おおせつけ)』の在外武官としてドイツに留学し、ヨーロッパ各地の先の世界大戦の戦跡に足を運んで検証し研究した成果にもとづいて力説していて、そんな近代戦に対する備えの至らなさを、たとえば、いまだ緒(ちょ)についたばかりの航空戦力の整備増強が喫緊(きっきん)の課題であるとか、逆に、敵の空襲に備えて耐火建材の研究普及に努めなければならないなどという、まるで我国にアメリカの爆撃機が襲来することを想定しているかのような具体的な防衛策にまで言及しているが、しかしそんなことは、満州の産業五カ年計画などとちがい、五年や十年ではとてもできることではないからね。
だから石原中佐も、軍事力の強化もさることながら、今はその産業計画でも陣頭に立って推進し、日本が東亜の盟主としての実力が確固たるものとなるまでは、『昭和十七年までは、いかなる戦争もしない』と年度まで区切って表明している、いわゆる『十年不戦論』を国策の柱に据えようと尽力していることは、きみも知っているよね」
と、山内大尉は念を押すように田島を見て笑った。