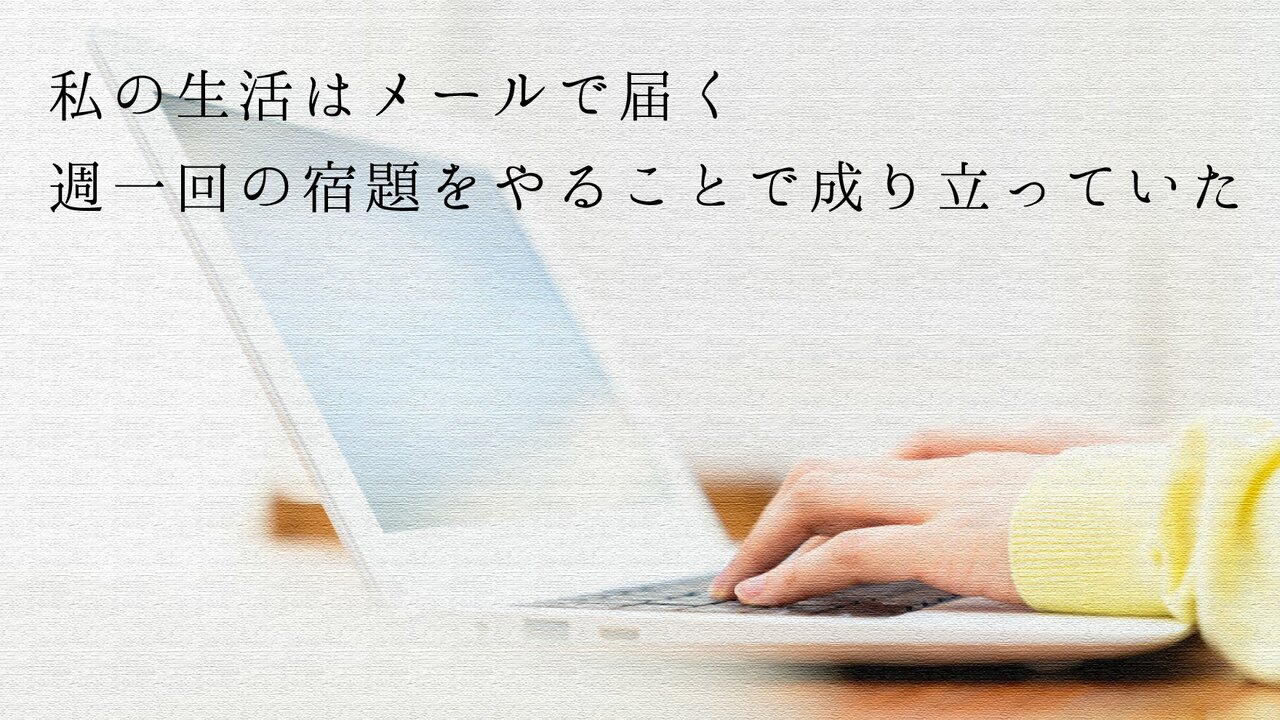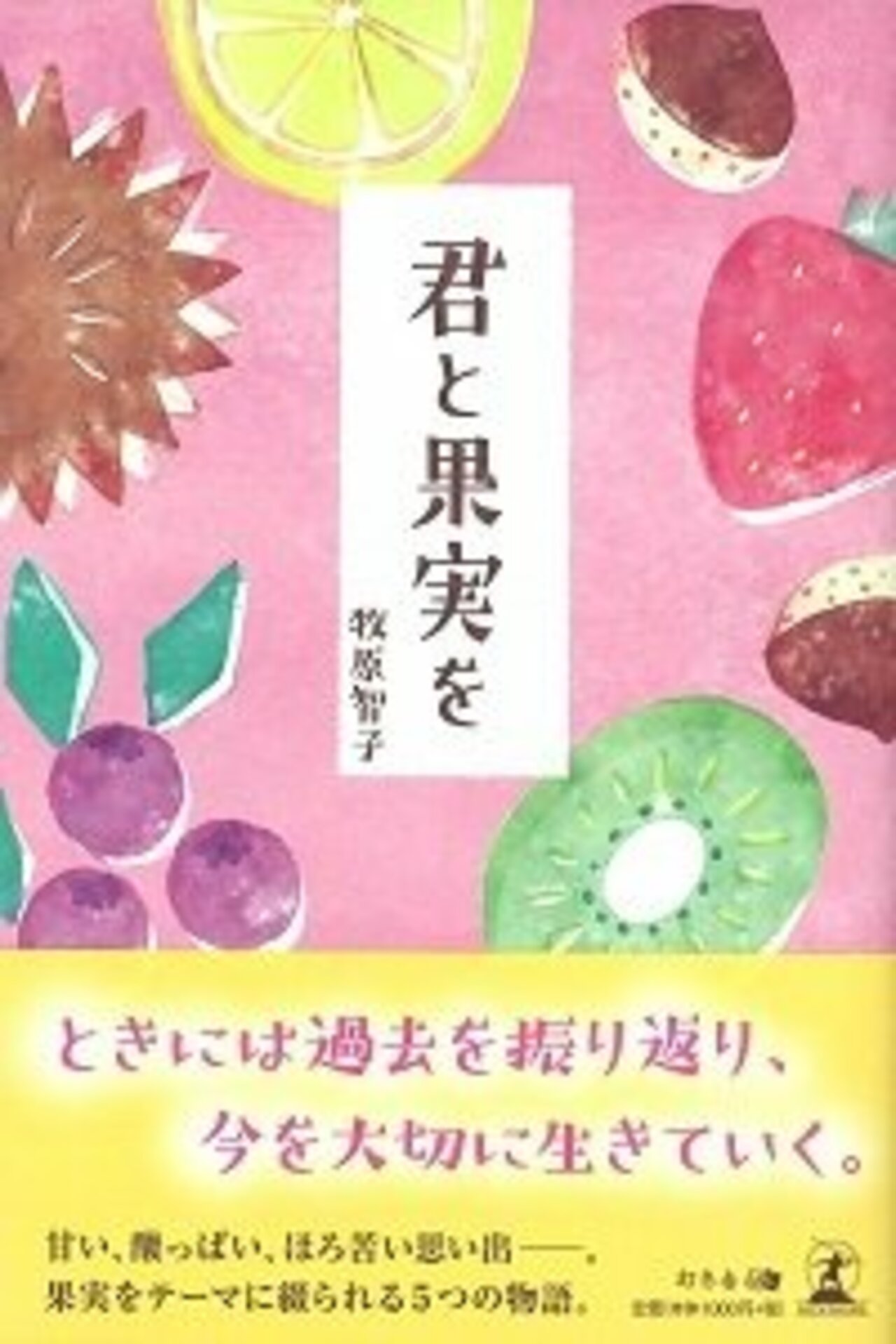栗に願いを
戻った翌日、朝早くの着信。結城さんだった。
「もしもし。高梨さん、あの大変なことが起こったんですが……」
「どうしました?」
「振込があったんです。リチャードさんから」
「え? 振込?」
「そうです。私がお話ししていた、あの家を購入する時に必要な手付金が入っていました。きっと振込手続きをされてから北海道に来たんだと思います」
「どうしましょう。そのままお返ししましょうか」
いろんな思いが巡った。北海道の話をしてくれた時の彼の嬉しそうな表情、育った環境に似ているとも言っていた。もう私との生活がイメージできていたんだろうと思う。
私は考えた。もちろん選択肢は二つだ。そのまま全額リチャードの家族に返す。もう一つは、リチャードの家族と話して、そのまま購入する、ということ。彼が遺した最後の家、と思えば、家族も何か違う感情が生まれるのではないかと。
話したいことをある程度文章にまとめてから、リチャードの父に連絡をした。父親はこう言った。
「息子はあの家にミキと住むって言ってたよ。それはとても嬉しそうにね。私たちはどちらでも構わない。もしミキが住んでくれるならそれは嬉しいことだけど、ミキを縛り付けるようなことになるのであれば、気にしないで、そのまま送金してくれればいい」
おおまかにはこのような話だった。私は迷った。
すぐに結論を出せないので、もう一度連絡させてもらいます、といって電話を切り、その後に結城さんにもメールを入れた。彼の父がこのように話したことで迷っています、必ず近日中には連絡をするので待って欲しい、と。
私は誰にも相談しなかった。いろんな雑音が入ることが嫌だった。きっと親はやめろ、と言う。友達もたぶん、ほとんどはそう言うだろう。
私は一番シンプルに考えようと思った。自分がどうしたいか。その答えは、もう、自分の中で出ていたように思う。
縁もゆかりもない湖の近くの街に住み始めて六年。湖の中心部分に浮かぶ小さな島の景観も美しく、毎日の散歩を終えると清々しい気持ちになる。
私の生活はメールで届く週一回の宿題をやることで成り立っていた。その仕事と同時にたまに入ってくる大きな翻訳の仕事は、まだまだ自分にやりがいをもたらしてくれるものだった。