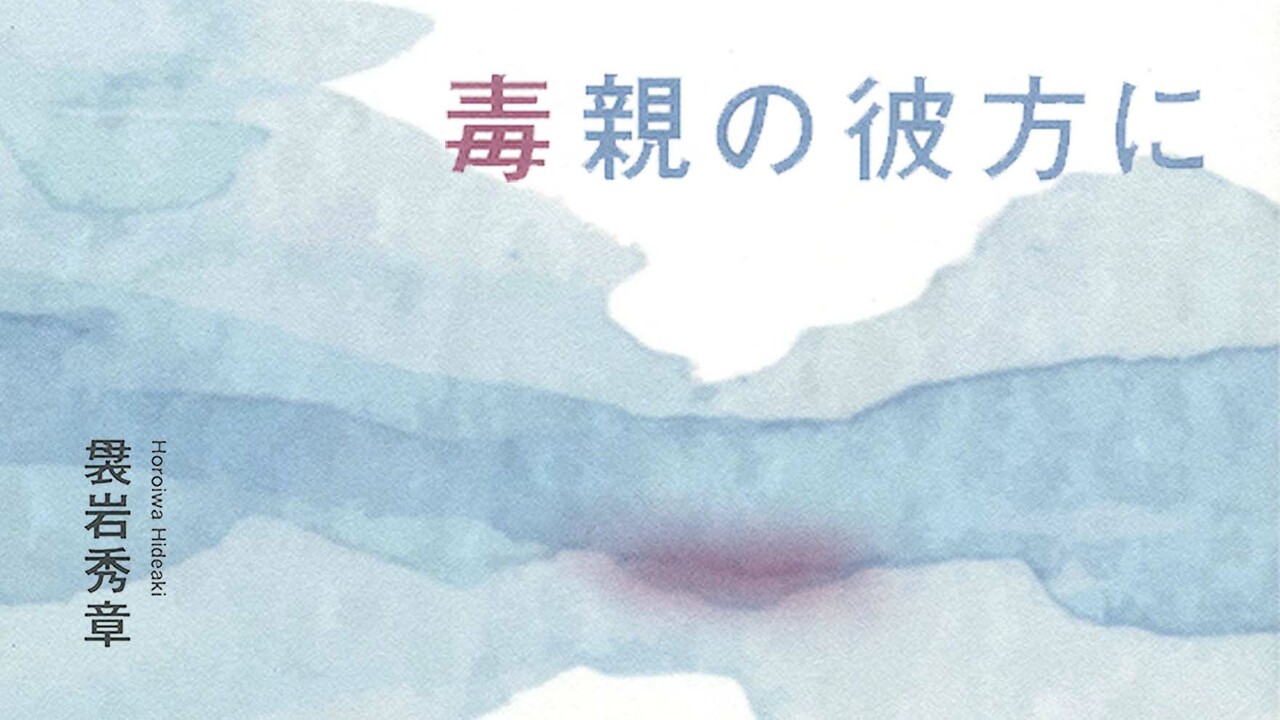【前回の記事を読む】母との暮らしから寮生活へ「わたしの知らない世界だった」
母との関係
母との関係は、痛みと孤独に満ちたものだった。家に居場所がないと感じると、たまらなく寂しくなるので、無理に明るく振舞って友だちと出かけてみたり、それでもどうしようもなくて元彼のところに行ってみたり。
「でもそんなの気休めですよね。仕方なくうちに戻り、大げさにくつろいで見せたり、母親に『自分のうちを覚えていたんだ』と嫌味を言われてもおかしそうに笑ったり。どんどんむなしくなることばかりなんです。でも家にいるためにはそうするしかないでしょ?」
無理して自分を鼓舞して、母の言いつけに従って家事を片付けて、妹や弟の話を聞いて。
「おねえちゃんが掃除をすると便所もピカピカだね」と言われると、それが皮肉なのか別の用事を言いつけるためのものかわからなくても、無性に嬉しい。
「そうでしょ?」などと明るく答えて「つけあがるんじゃない!」と叱られる。
「それでも自分の居場所がそこにあるような気がしてくるんです。ここでは自分が必要とされていると思い込みたい、思い込みたいんです」
絞り出すようにそう言うと、彼女は顔を伏せてしまった。
〈あなたがそんな扱いを受けていいはずはないけれど、たまたまそうなってしまって、とても可哀想だった。それに耐えて、よくここまで頑張ってきた〉
「わたしが我慢だけで満足できると思いますか……」
彼女は弱々しくそう言って、さめざめと泣いた。
「そんなお調子者は長続きしません。テンション上げるのに疲れて家から出たくなくなると、母親から追い出されないようにしなきゃと思い、今度は緊張が始まります。母親が気に入らないことをしてはいけない、神経を逆なでしないようにしなきゃ、家に置いてもらうためにいい子でいるんだ……」
「母親の一挙手一投足が気になり、またその態度を母親が面白くなく思っていないか気になって、身動きが取れなくなるんです。まるで糊付けにされた服みたいに心も体もぎくしゃくして、本当に自分が動くとバリバリ音を立てるような気がして、歩くのも声を出すのもびくびくしてしまいます」
「わたし、いけない子なんです。母が本当は大嫌いなんです。家にいさせてもらうには、お母さんのこと大好きで、何を言われても気にせず、素直に言うことを聞いていなきゃいけないのに、わたしは母が嫌い、大嫌いなんです。だからうちに帰れない……帰っても居場所がないの」
ここで彼女は声を上げて泣き始めた。切なく、どこまでも孤独な泣き声だった。寂しさを紛らわそうと明るく振舞えばむなしくなる。追い出されないようにおとなしくしていると母の態度に怯えて竦んでしまう。どちらも急所に刺さったとげのように彼女に痛みをもたらし疲弊させていた。