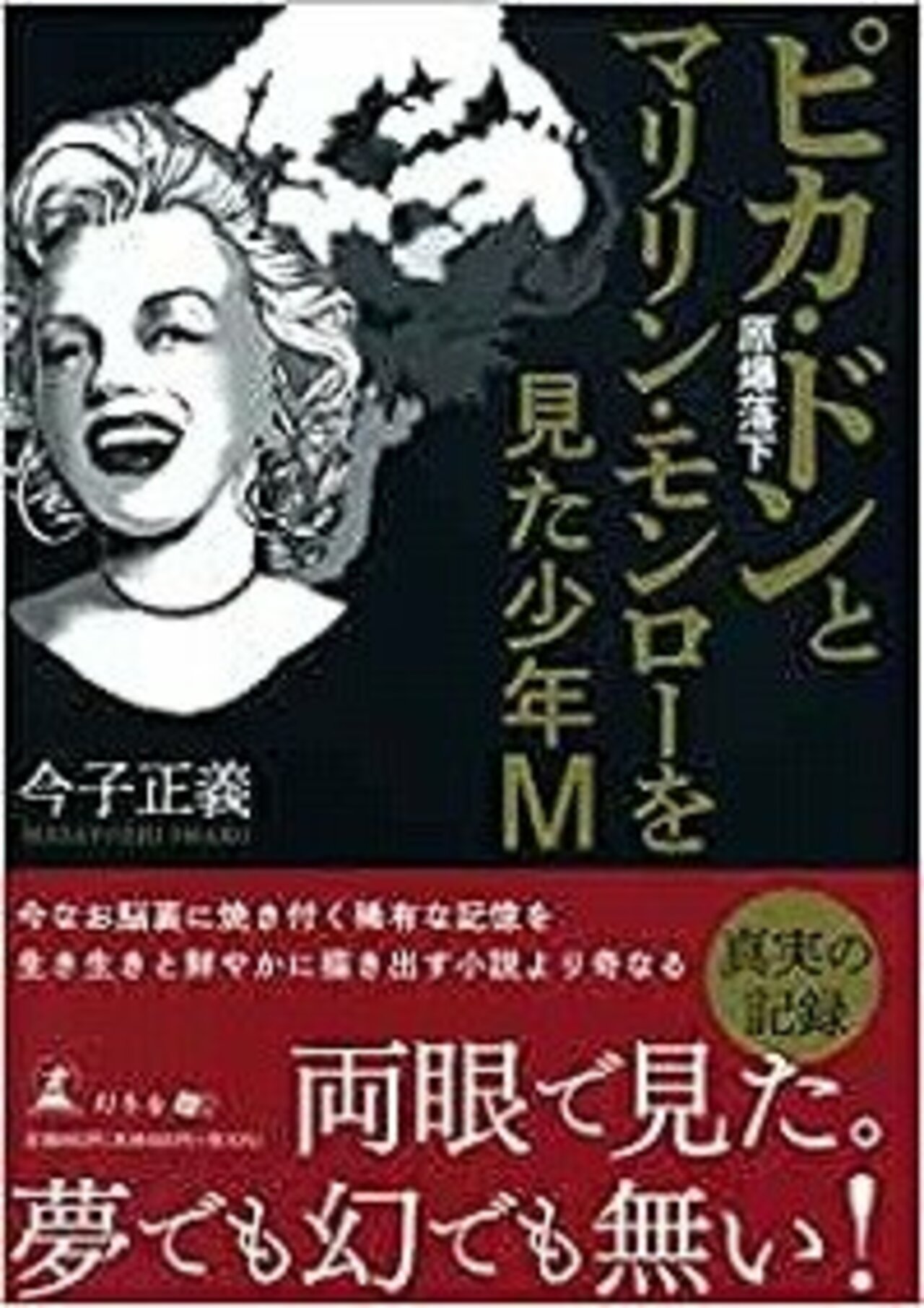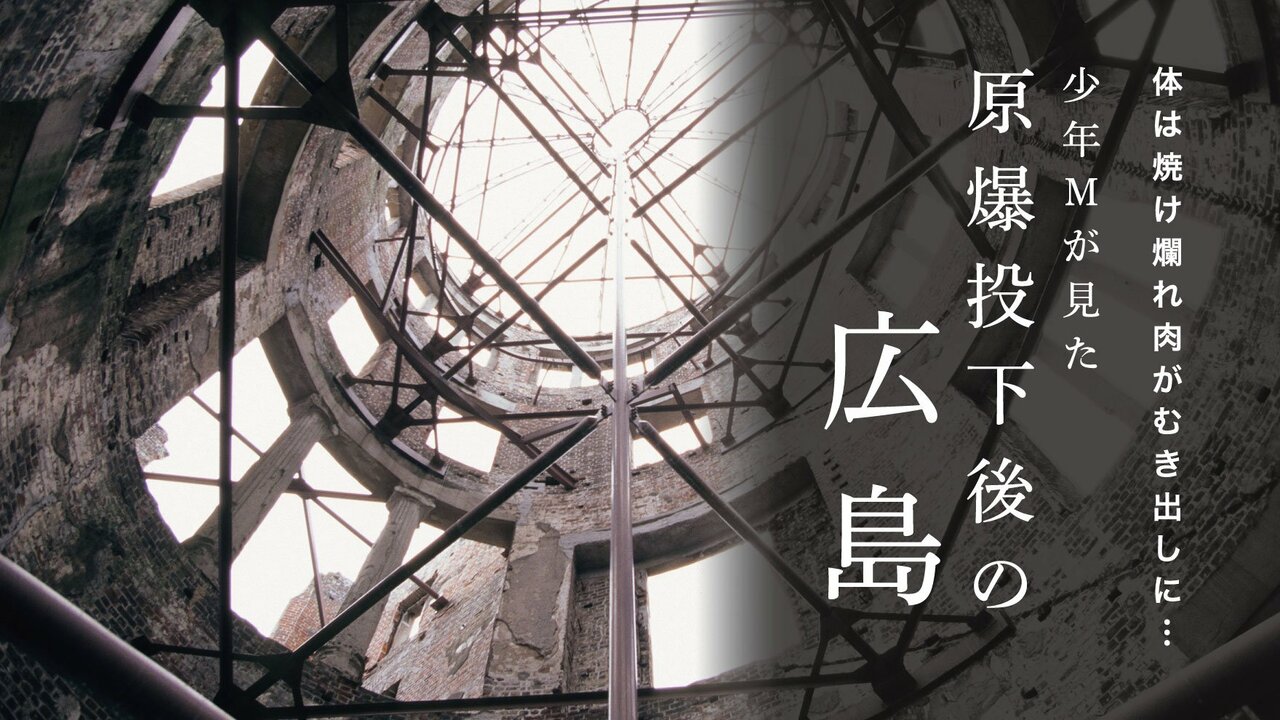本物の砂糖が運び込まれた
その頃のことだった。日本軍が秘匿しておいた食料が、こっそりと岸川の家に運び込まれてMたちが住んでいた蔵の前の土間に積まれているらしいという噂を耳にした。
Mが本当かどうか確かめに行ってみると、そこには大きな麻袋が四列五段に積み上げられていた。麻袋の千切れかけた端の綻びから白い粉のようなものが溢れ出そうになっているのを見つけた。もしかして砂糖ではないかと思ったが、毒かもしれないとも感じた。Mは裂け目に指を突っ込んで取り出した粉を恐る恐る嗅いでみた。変な匂いはしなかった。ちょっとだけ舐めてみた。夢にまで見た砂糖の甘い味だった。
岸川の人は誰もいなかった。Mは台所に置いてあった茶碗を取ってきて麻袋から砂糖を指で引っかいて取り出し、茶碗に山盛りにして逃げ出した。家に持ち帰って母に見せると「これ砂糖じゃない。どうしたん?」と怪訝そうな面持ちでMを見た。
「岸川にいっぱいあるんじゃ、もっともらってくるけえ」
と、鍋を取って駆け出していった。母は呆気にとられて見送っていた。
岸川の砂糖は消えていた
ところが、Mが岸川の家に駆け戻ると土間から麻袋の荷物はすっかりなくなっていた。出てきた岸川のおばさんに質すと、
「トラックが来て、あっという間に、みな持って行かれたんじゃ。砂糖らしかったが、陸軍の隠匿物資じゃったようじゃ。もう一袋も残しちゃおらんけん。ちょっとでも取っときゃ良かったんじゃが」
と、口惜しそうに言われ、Mはがっかりした。
Mは家に帰ってきて「もう一袋もなくなっとった」と腹立たしげに空の鍋を母に渡した。
「誰がどこへ持って行ったんかね」と、母は残念そうに言った。母は、四つの茶碗に、はったい粉を入れ、Mが持ち帰っていた砂糖を混ぜて熱湯を注いでかき混ぜてくれた。
母、兄、妹とMの四人家族は一緒に飯台を囲み、匙でかき混ぜて口に入れた。ほっぺたが落ちそうになるほど甘くてうまかった。しばらく食べたことのない本当の砂糖の甘い味だった。
「おいしいね。お父ちゃんがおったら良かったんじゃがの」と、妹の美代が言うと、「父さんは甘い菓子より酒のほうが好きじゃけえ、ええんよ」と兄の真一が言った。
Mは頷いて、最後の一匙を口に入れ、飲み込むのが惜しくなった。