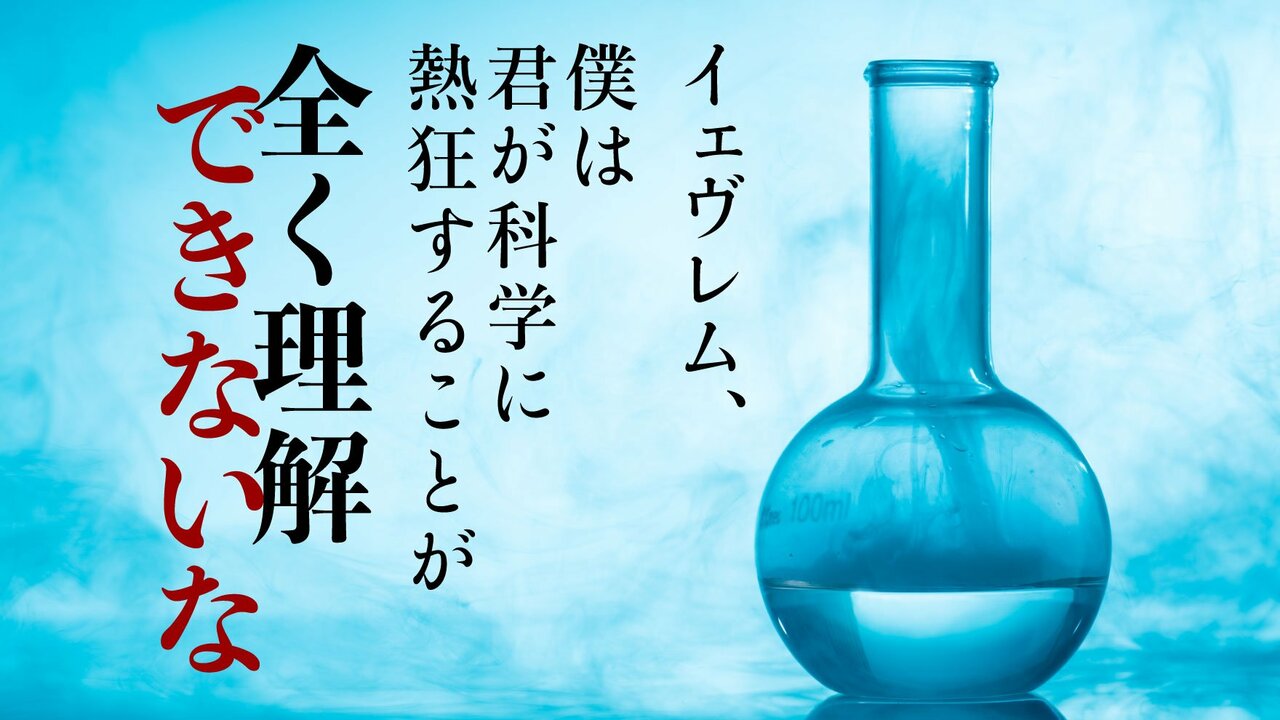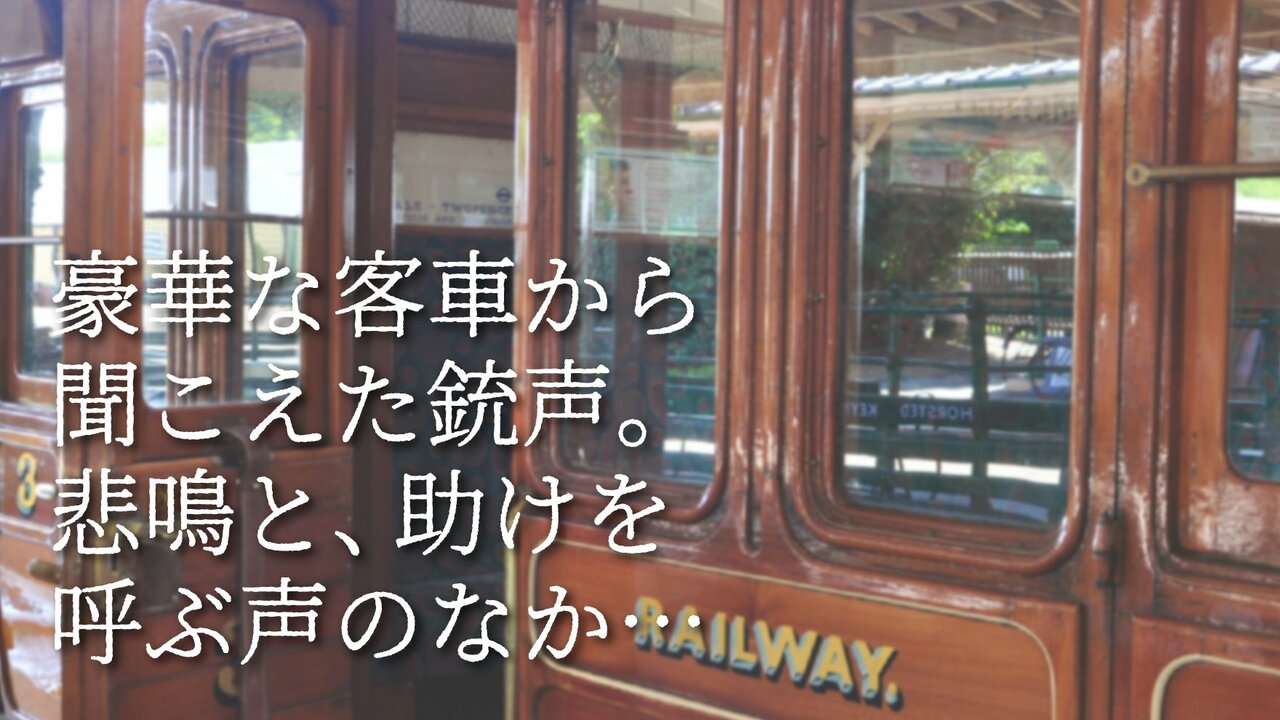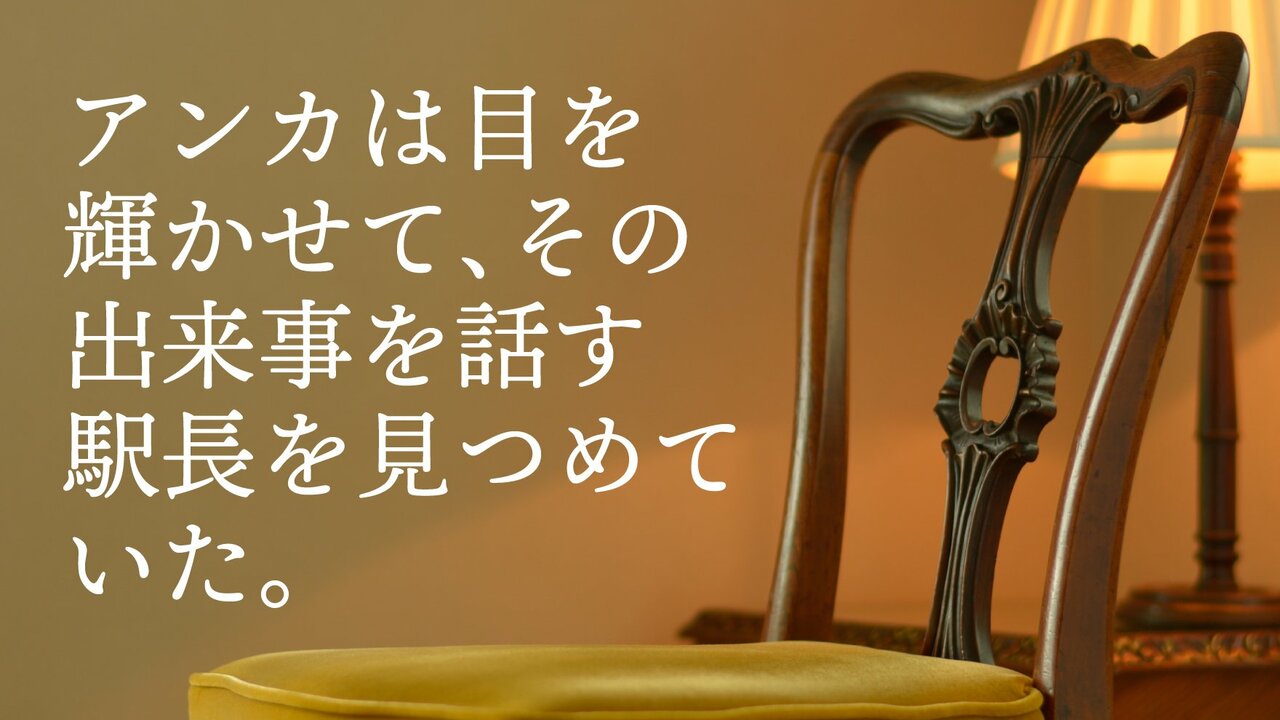【注目記事】「発達障害かもしれない職場の人」との関係でうつ病になった話
第三章 セルビア初紳士クラブ 一九一九年 ベオグラード
次の日、六月十二日の午後、アンカ・ツキチはプリビチェヴィチ氏を待つために、「セルビア初紳士クラブ」の日陰の仕切り席に座っていた。
昨晩のグリマルディのこととか、プランクのことで混乱したすべてについて大して思い起こすこともなかった。というよりも、彼女はこれといったことは考えずに、長いシガレットホルダーに入れた細いたばこをふかしていた。
濃いまつ毛の半分閉じた眼で、客があまり入っていないカフェーの店内を見ていた。全部が視野に入っていたけれども何か特定のものを見ていたわけではない。
それは、極東で学んだ技、感覚と洞察力を高めるための半瞑想状態のひとつである訓練だった。アンカは、この状態で平気で何時間でも過ごせたが、そこにハジ・ナースティチ氏が注文を受けるためにやってきて、彼女を目覚めさせた。
「お伺いします、お嬢様」
と言って、マスターがふっくらとして薄紅色の顔に微笑みを浮かべる。
「ご注文はいかがなさいますか?」
アンカはゆっくりとまぶたを開く。視線を上げてハジ・ナースティチに微笑みを投げかける。それは若者の膝をよろめかせてしまうほどだった。世慣れした男達ですら、自分から財布のひもを緩めてしまうことであろう。
「ウォッカ・マティーニを」とアンカは言って、青味がかった煙を、窓の近くで斜めに差し込んでくる日光めがけて吹き飛ばす。
「シェイクせずに、ステアで」
「すぐに持って参ります」
マスターは声高らかに言い、それからお辞儀して、バーのほうに身振りで合図する。バーの若者は若い女性客のためにカクテルを作り始める。
「お連れ合いをお待ちですか?」
ハジ・ナースティチが気遣いながら尋ねる。
「何か特別なご要望はございますか?」
アンカは、プリビチェヴィチのこと、彼の態度のことについて思いめぐらす。
アンカと公共スペースで会うときに誰かに見られたら、国家公務員に若い愛人がいるといったゴシップが広まってしまうことを恐れて、プリビチェヴィチ氏はいつも堅苦しい態度を取る。そういった噂は、もちろん瞬時にユーツァ夫人の耳にも届いてしまう。
彼女の前では、彼はいつも平身低頭だ。
「いいえ、マスター」
アンカは再び微笑む。
「仕事での会食ですから。すぐに終わります」