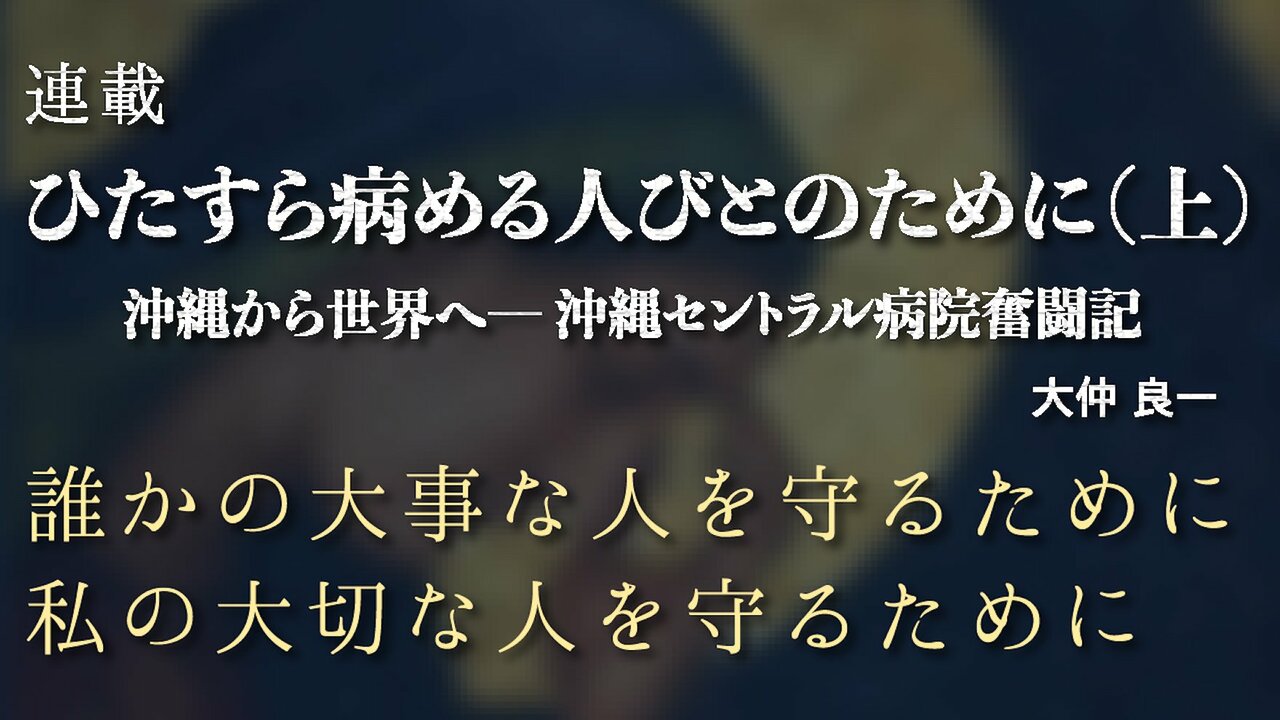インドの言語
次に、日常の言語について触れてみます。
【第13回】でも述べたように、インドの州区分は、イギリスから独立後に全インドを使用言語別に再編成した言語州が基本になっており、地方の少数民族の方言も入れると、何と八五〇もの言語があるといわれます。
実際、紙幣にはそれらの言語の最大公約数の一三種類の単位で表示されているのが実情でした。ヒンドゥ語はインド・アーリア語族に属し、ヨーロッパ諸国と同じルーツを持っているため、単語の中には今のヨーロッパ語とどこか類似しているものがあるといわれています。
英語はかつて、イギリスの植民地時代に、各地方によって言語を異(い)にする独立運動の志士たちが言葉の障害を排除し、意思の疎通を図る手段として使用したものでした。現在でも、出身地の違うインド人同士が地方の言語から英語に切り替えて話すほど、お互いの意思の疎通のための共通語として重要な役割を担っているようです。
現代の沖縄の青少年たちが、沖縄の方言を満足に話せないように、当のチャンドラ・セカランさんも地元のヒンドゥ語については十分に話せず、院内における意思の疎通は、もっぱらインド訛(なま)りの強い英語になりました。
コミュニケーションの壁
このように、宗教や食事、さらに言語や生活習慣をまったく異にする外国からの患者さんを迎え、当初の予想をはるかに超える困難に直面することになりました。
まず、毎朝夕の沐浴と礼拝が宗教上の習わしのようであるため、入院翌日から早速、てんてこまいのスタートとなりました。
さらに、週二回はインド料理をメニューに加えようと配慮して、コザ市に在住するインドの方を調理の講習にお招きし、主食のチャパテイの作り方や、スパイスの調合の仕方などについて厨房職員の教育をしました。
一方、リハビリの現場においても、他の職員や多くの患者さんたちとのコミュニケーショを十分に図るために、片言ながらも英会話の可能な職員を配し、予定の六ヵ月間で最大の効果を挙げるべく、万全を期してのスタートでした。

リハビリの効果が出る
リハビリ当初の問題点は、摂取カロリー制限による減量との闘いでした。一日六時間にも及ぶハードなメニューで、着実に体重のコントロールに成功し、セカランさんの持ち前の根性も手伝って、みるみるうちに下肢の運動機能の回復が認められるようになってきました。
両下肢の運動機能障害で、しかも体重が九〇キログラムを超える患者さんが、極めて円滑に歩行障害を克服できたのは、患者さん自身はもとより、何といっても県下で唯一、当院に備え付けてある歩行訓練用ロボットによるところが大きいといえます。
このロボットは、水中における浮力と同様に、コンピューターによる患者さんの体重コントロールが床上でも可能で、肥満患者さんの訓練には極めてその効果を発揮できるものです。
彼の歩行機能の驚異的な回復ぶりは、同じく下半身麻痺でリハビリに励んでいる他の患者さんたちに大きな刺激を与え、覚えたての片言の日本語とともに、セランカさんはいつの間にか病院中の人気者となりました。
わずか六ヵ月前には、自前の車椅子姿で那覇空港に降り立ったチャンドラ・セカランさんが、今、杖なしで廊下を歩行し始め、手摺(てす)りをつかみながらでも階段の昇降が可能なまでに回復しました。幾多の艱難辛苦(かんなんしんく)に耐えて励んだ、彼の並々ならぬ努力と、県内在住のインドの方々の物心両面からの援助、さらには職員の有形無形の協力が実を結んだものでした。
長いようで短かった六ヵ月間の医療協力、インドで約束した医療を介しての国際奉仕をつつがなく果たすことができ、一人の男のささやかなロマンをまっとうし得た喜びに、私は静かに浸ったものでした。

インドで大仲記念スカラーシップが創設される
一九九〇(平成二)年四月四日、チャンドラ・セカランさんは、病院の職員やロータリークラブの皆さんや多くの報道陣に見守られる中、「新婚旅行は沖縄に来ます……」と元気な言葉を残し、那覇空港から故郷インドへと旅立たれました。
チャンドラ・セカランさんがインドへ帰り、しばらく音信が途絶えていたある日、コインバトール東ロータリークラブから久方ぶりに一通の航空便が届きました。
チャンドラ・セカランさんが、自ら車の運転をしながら税理事務所に通い、懸命に働いているという、うれしい便りでありました。
その上、さらに私をびっくりさせたのは、インドの各地でポリオの実態調査をしたことに加え、ポリオ後遺症で悩んでいたチャンドラ・セカラン青年を、六ヵ月もの間、ボランティアで生活および医療面での世話をし、見事にリハビリの成果を挙げて母国インドに帰してくれたことに対する深甚(しんじん)なる感謝の意を表し、日本とインド両国の国際友好のシンボルとして『Dr.Ohnaka memorial scholarship』を制定し、毎年三人の医学部最終学年の学生に奨学金を貸与することになったということでした。
事前に何の情報もなく私の名前を冠(かぶ)せた「奨学基金」が発足していることに、ただただ驚き入った次第でした。
後日、私が所属するロータリークラブにも情報が届き、インドのロータリーの素晴らしい活動に呼応して、沖縄でも私をもとより、有志の方々が浄財を募り「奨学資金の一部に」と、新たな活動が始まりました。
すでに外務省からの連絡で、在マドラス日本国総領事の石崎辰雄氏がわざわざコインバトールまで赴き、基金の一部の贈呈式が催されたという、誠にうれしいニュースが届きました。
〝夢が現実に″と報道された、インドのロータリアン誌の記事