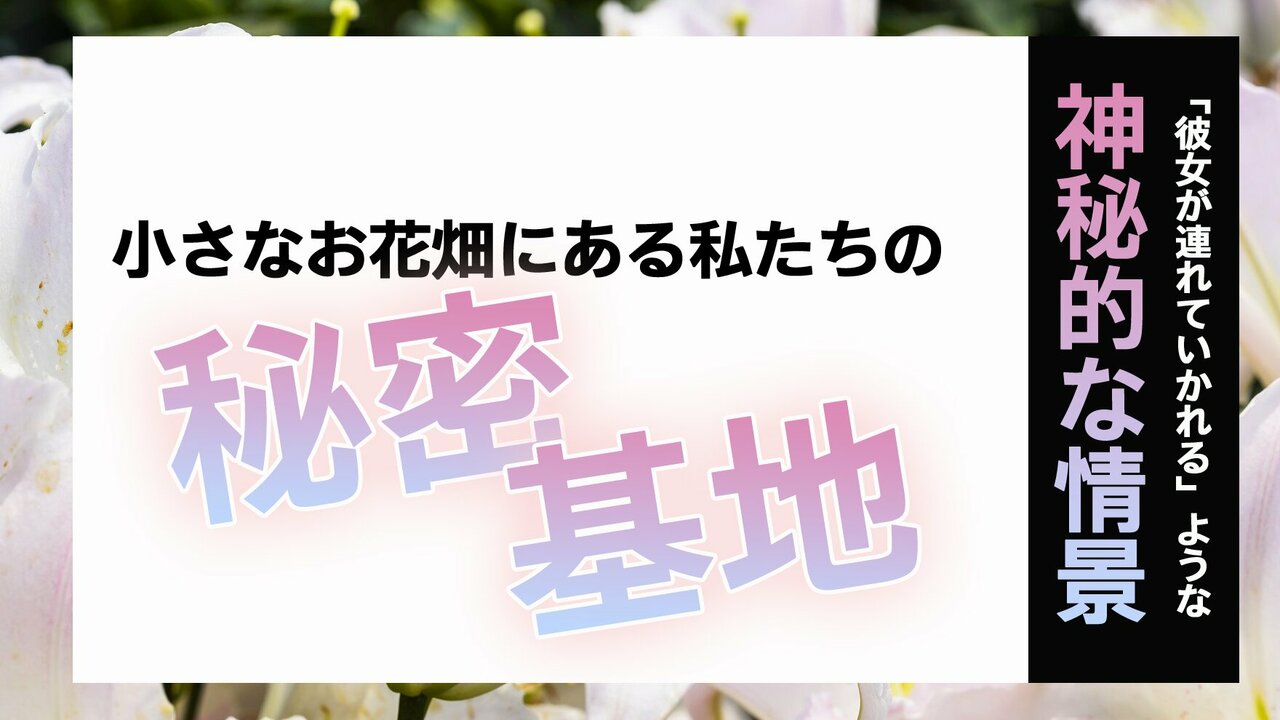最初──彼女と初めて会った時の衝撃は今でも鮮明に覚えている。
その日、島本家が引っ越すにあたりうちの近くに家を建てる、その工事着手前の挨拶に、両親と共に彼女はうちへやって来ていた。歳が近く、誠実そうな島本さん夫婦を父はいたく気に入り、玄関口ではなんだからと家へ上げお茶を振舞った。……用意したのは母だったが。
私はその時二階の自分の部屋にいて、知らない大人と関わるという、子供にとっては勇気と体力のいる行為から逃げていた。しかし、父母と島本さん夫婦が談笑する声が聞こえてくると、好奇心に負け、こっそり居間へと降りていった。
いつも自分が過ごしている空間で、父母が知らない大人と楽しそうに話をしている。その光景は、自分が今家の中にいるにも関わらず妙な居心地の悪さを感じさせた。しかし幼い私にはなぜそんな感情を抱くのかなんてわかるはずもない。
子供の心理とは不思議なもので、嫌に感じるのなら見なければいいものを、幼い私はしかめ面になりながらその光景をつぶさに観察していた。
テーブルの片方に並んで座る父母、向かい側で同じように座る島本さん夫婦。四人の大人の表情は和やかだ。けれど何を話しているのかはわからない。それが私を更にむかつかせた。
四人の大人を交互に睨め付けていると、視界の端に、大人とは違う小さな影が見えた。
テーブルの奥の席に子供が座っている。
居間には四人の大人の他にもう一人、自分と同じくらいの歳の女の子がいたのだ。その女の子は自分とは違い、大人たちが談笑している中にいても、不機嫌な顔や退屈そうな素振りは一切見せず、にこにこと楽しそうにはにかんでいた。
話に加わっている様子もないのに、何がそんなに面白いのだろう?
不思議に思っていると、視線に気づいたのか、女の子がこちらを振り向いた。
驚いた私は戸口から顔を覗かせたまま固まってしまい、そのまま女の子の顔を凝視してしまう。むこうも同じで、はっと目を見開かせたままこちらから視線を外さない。
時間が止まってしまったように、二人は見つめ合っていた。