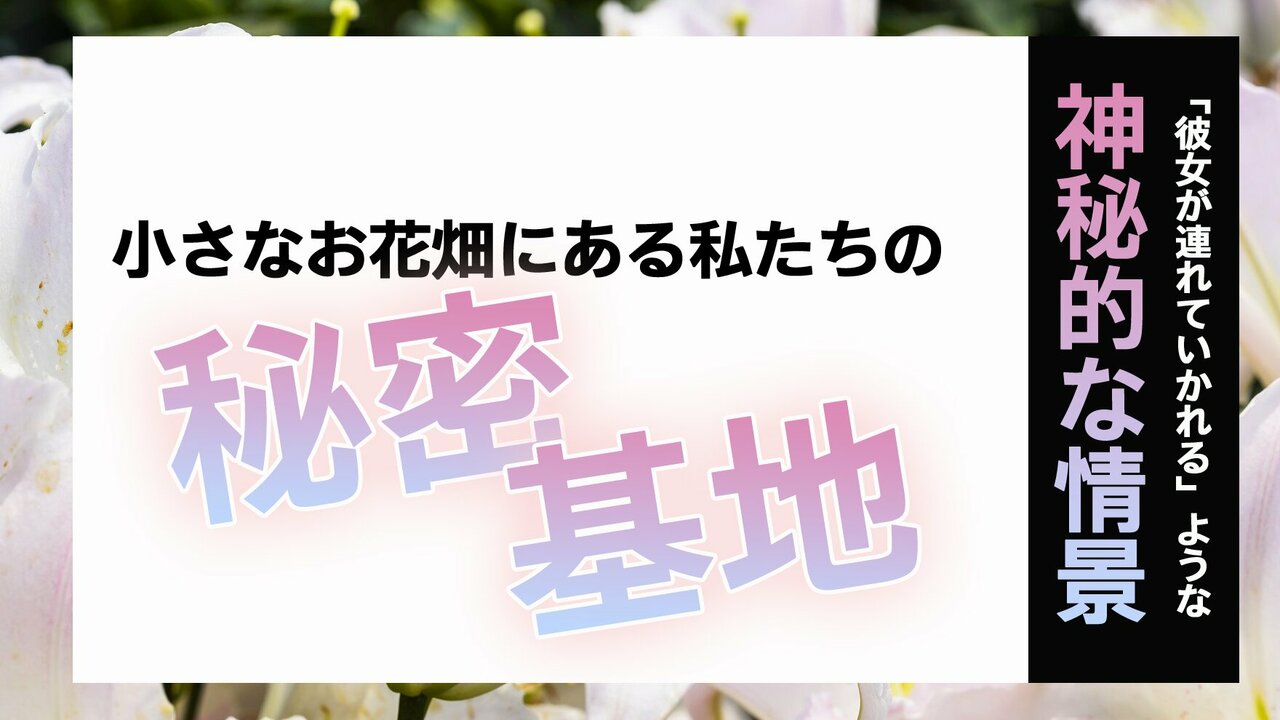1
掃除をするのだろう、日差しを照り返す後頭部を見送りながらそう思った。利用者が少なくとも落葉落枝、虫の死骸などで汚れは溜まる。ほとんど無人駅の様相を呈しているこの駅が良好な状態を保っているのも、ひとえにおじちゃんの手入れの賜物なのだった。心で感謝を述べつつ駅舎のベンチに腰掛ける。
雨避け屋根の下は涼しかった。もちろん冷房の効いた車内とは比べられないが、都会と違って、あの、日光がビルの鏡面に反射して、どこかしこからもぎらぎらと照らされる拷問のような暑さは感じない。
まもなく正午という時間帯、日差しは高い角度から降り注ぎ、地面を白く照らしている。強い光によって生まれた影は、反対に密度の濃い黒色をしていた。日向と日陰、あっちとこっちではっきりと分かれたコントラスト。
その光景になんだか象徴的なものを感じ……帰省したこともあってか、昔の記憶が刺激され懐かしい思い出がイメージとして浮かんでくる。電車内では未遂に終わったけれど、今は日向の向こうにはっきりとそれを見ることができた。
強い日差しの下、それでもなお白い肌を輝かせ、無邪気にはしゃいでいる彼女の姿を。
2
「ゆかちゃん」
ベンチで涼んでいると誰かに名前を呼ばれた。
いつの間にかうたた寝していたらしい。目をしばたたかせながら、半ば反射的に、誰に呼びかけられたのだろうと頭を巡らせるけれど……すぐに考えるのをやめた。私のことを「ゆかちゃん」と呼ぶ人間は一人しかいない。
目をこすって視界のピントを合わせると、そこには制服姿のさよちゃんがいた。彼女は日陰の下、申し訳なさそうに眉尻を下げて、こちらを見下ろしている。
「ごめん、待たせちゃったよね」
「ううん、待ってないよ」
「でも寝てたじゃない」
急いで来たのだろう。言葉の端々には荒い息が混ざっていたし、前髪が汗で貼りついている。そしていつもは白い彼女の顔が、暗い影の下でもはっきりとわかるほど赤く染まっていた。
「昨日遅くまでテレビ見てて、寝不足なだけ」
そう言うとさよちゃんはさきほどとは違う理由で眉を歪ませ、不満げな顔を見せる。
「だめだよ夏休みだからって夜ふかしばっかりしちゃ。ゆかちゃん成長期なんだから、ちゃんと寝ないと大きくなれないよ」
「さよちゃんが言うと説得力あるー」
「もう!」
今日のことも含めてよく寝坊することをからかうと、さよちゃんは頬を膨らませてわかりやすく怒って見せた。高校生とは思えない幼稚な仕草がかわいらしくて、こっちのほうが年下のはずなのに、なんだか微笑ましい気持ちになる。
「ふふ、ごめん」