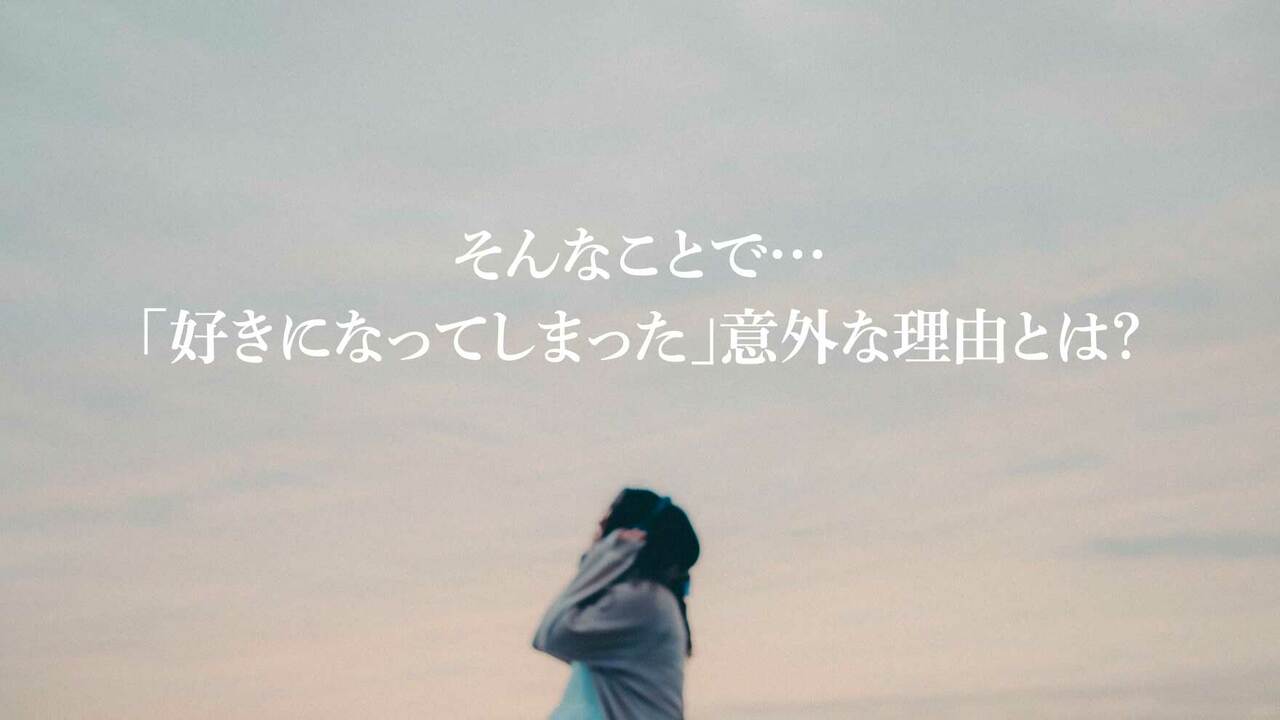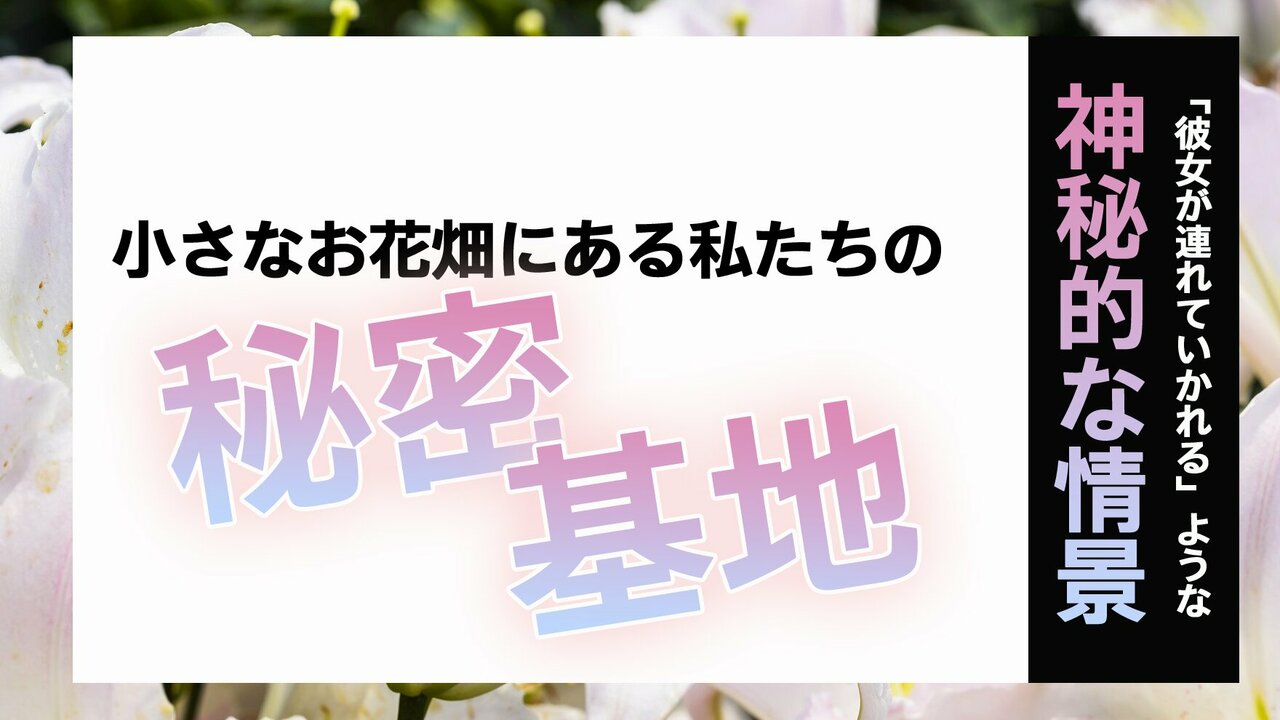2
明るい亜麻色の髪と白い肌、口元から零れる牙のようにとがった歯、その姿が十年近く経った今でも脳裏に焼き付いている。
「ゆかちゃーん?」
さよちゃんの声が耳に届くと共に、頬に冷たい物が触れた。
「うわっ」
思わず身を反らす。振り返るとさよちゃんが意地の悪い顔で、両手に缶飲料を持ちながら立っていた。
「な、なに、もう……びっくりするじゃん」
濡れた頬を素手で拭いながら抗議するが、さよちゃんは意に介したふうもなく更に笑みを深める。吊り上がった唇から白い八重歯がきらりと顔を覗かせた。それは、作り笑顔でない──彼女が感情のままに笑う時に見せる合図だった。
「寝不足で隙だらけのゆかちゃんが悪い。ほら、これ飲んで頭しゃっきりさせて」
両手のうち片方に持っていた缶飲料を差し出してくる。私がよく飲むミルクティーだった。
「……そういう時ってコーヒーとかじゃないの?」
言いながら缶飲料を受け取り、手首で振る。よく冷えていることはさっき頬に触った時点でわかっていた。
「ゆかちゃんそれ好きじゃなかったっけ?……あれ? それともコーヒー苦手だったんだっけ?……確か両方だったよね」
「いやどっちともあってるけどさ。そういうことじゃなくて……ほら、頭をすっきりさせるにはカフェインが入ってるコーヒーのほうがいいんじゃない?」
「紅茶にもカフェイン入ってるよー。コーヒーよりは少ないけど」
「そう、だけど」
「じゃあ問題ないね!」
私が反論する間も与えず、さよちゃんは一人だけプルタブを開け飲み始めてしまう。反論する気力が消え失せた私は、そもそも反論したかったのかも定かではないことに気づき、なんだかわからないうちに敗北感を味わったな、と諦めに近い何かを感じながらミルクティーをいただくことにした。が、プルタブに指を掛けたところで動きを止める。
「あっ……お金」
「うん? いいよいいよ、寝坊したのに待っててくれたお詫び」
さよちゃんはそう言って微笑んではいるが歯を見せず唇を閉じている。はっきりとした拒絶の意思を感じる、有無を言わせぬ笑顔だった。
「じゃあ……いただきます」
私は今度こそ諦め、缶を開けてミルクティーを飲み始める。自販機の冷蔵機能が強過ぎたのか、ミルクが少し固まっていて、舌にざらりとした感触があった。飲みながら横目で隣を窺う。
さよちゃんは炭酸飲料を勢いよく流し込んでいた。音をたてながら力強く隆起する喉は汗でうっすらと濡れていて、そこに更に、口から溢れた液体が尾を引いて流れていく。そんなに一気に飲み込んで喉は痛くないのかなと不思議に思う。もしかしたら彼女は痛みを感じないんじゃないか? とも。
しかしその考えは的外れだったようで、缶を口から離し、大きく息を吐いた彼女の目元には涙が溜まっていた。
「ゆかちゃん、どうかした?」
視線に気づいたさよちゃんが涙目で問い掛けてくる。