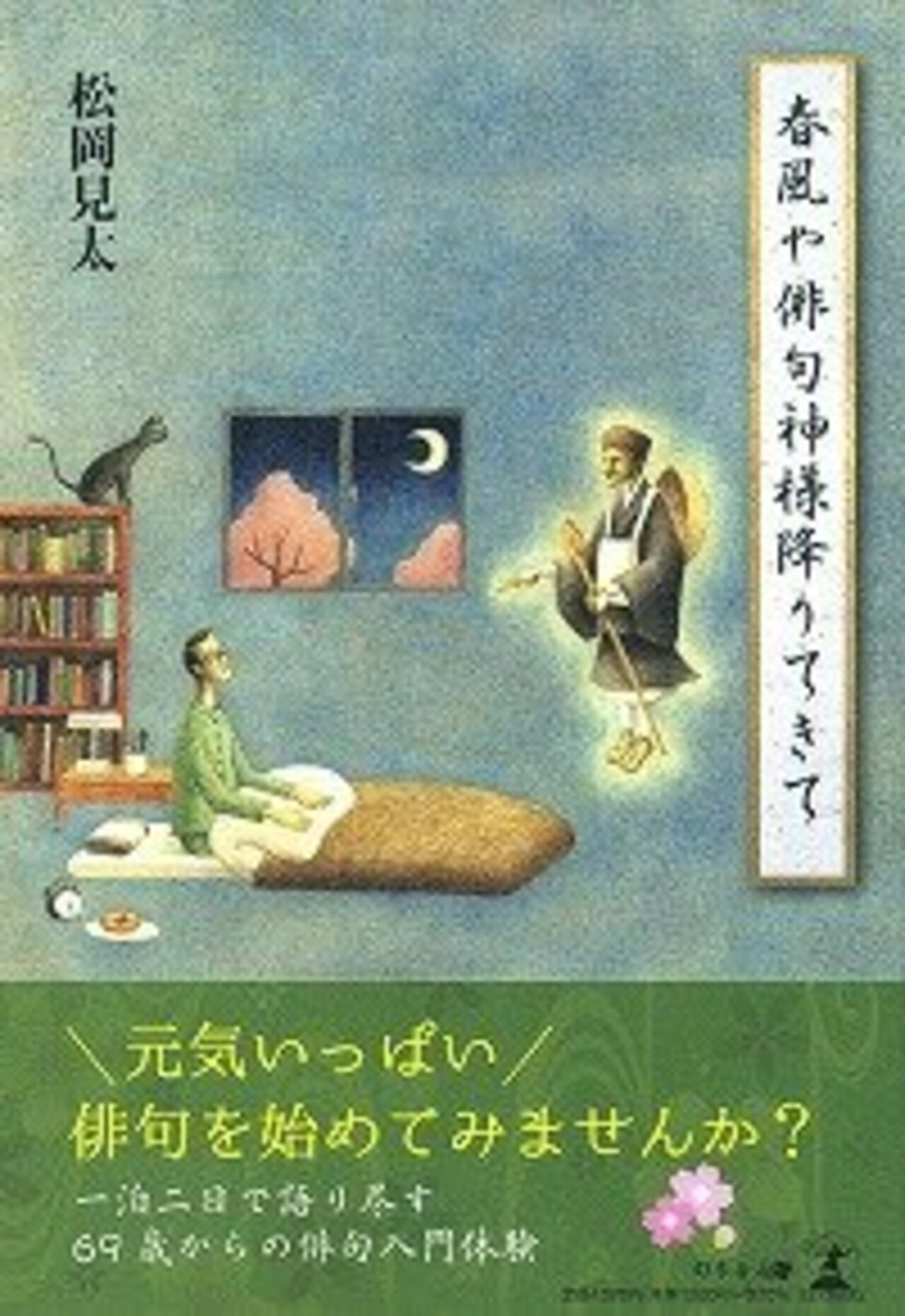俳句は座の文芸と呼ばれるように、俳句の作り手とそれを味わう複数の読み手から成る。しかも『ほとんどの読み手は、同時に俳句の作り手でもある』という、他の文芸に全く見られない特徴がある。作られた俳句の評価は、このような読み手によってなされるのである。
作り手自身は自分が作った句の評価をできないという性格が俳句にはある。この自分の俳句の出来具合について、自己判断がつかないということが、俳句の最も難しい点であると、私は思う。
俳句の作り手は、野球の投手に似ている。投手が投げた球のコースと高さを見て、「ストライク」か「ボール」かを見極めるのは、捕手の後ろに立つ審判である。「ボール」とコールされた際、投手が「いやストライクを投げたはずだ」といくら反論してみても、審判の判断が変更されることは決してない。投手が投げた球が、「ストライク」か「ボール」かは、投手ではなく審判という第三者によって決定される。
俳句もこれと同じ構図で、よい句か駄句かは、読み手によってのみ決められる。作り手は決定に関与できない。俳句の作り手は、一旦句が手元を離れれば、他人様の評価を待つだけである。投句をする度に、受験生のような立場に立ち、出た結果を素直に受け入れるしかないのである。評価されなかった句は、自ら捨てるか、推敲をするなどして新たな句で勝負するしかない。
実際、自分が作った句の良し悪しを、自己判断するのは難しい。自分で名句ができたぞと思って、新聞の投句欄に送っても、選者に選ばれて掲載されることはまずない。句会においても、これはと思う自信作が選に入らず、がっかりすることが多い。その反面、不思議なことに、数合わせで作った、自分ではあまり良い出来ではないと思った句が、評価されることがままある。
参考までに、そのような私の句を紹介しよう。句会に出す五句を作ろうといろいろ試したがうまくいかず、五句目がどうしてもできない。悩んだ末に、ふと芭蕉のいう三尺の童だったら、どう詠むだろうかと思った。そこで思い切り童子になりきってみた。それこそダメもとで作った句だ。
かしわもちてのひらよりも大きな葉