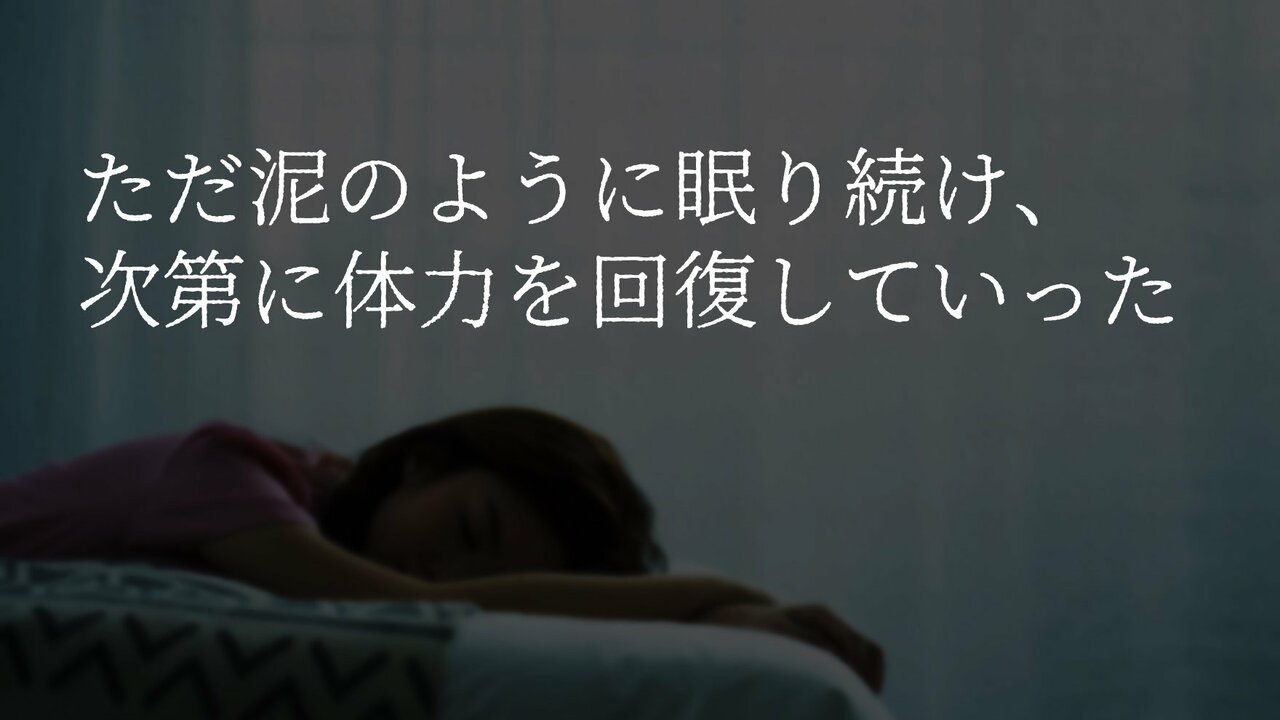第三章 免疫力に働きかける
17 もしあるとしたらステージⅤ
二〇一七年の一月三十一日、三時間くらい検査をした後、にわかに周囲がザワつき始めました。主治医に「呼吸をするのに苦しくないですか?」「いつでも酸素吸入ができる状態にしておきますから」と言われました。看護師さんからも矢継ぎ早に「血痰が出ていますか?」と聞かれました。
呼吸も問題なかったですし、血痰どころか痰すら出ていなかったので、思わず「何ともないですが、いったいどういうことですか?」と尋ねると、「村松さん、ご家族を呼んでいただけますか。話したいことがあるから」と主治医から返事がありました。ただならぬ事態だということはわかったので、息子に連絡を入れました。
一同が揃ったところで、主治医がいつもの冷静な面持ちで、MRIに写った画像について説明をし始めました。十月時点で右肺に認められた四センチ余りのがんは、さらに大きくなって六センチ近くにもなっていました。飛び散っていたがんも一回りも二回りも大きくなってくっきり写っています。腫瘍マーカーは、正常値が0.0~0.5のところ、2.789もありました。
抗がん剤治療を受けてきたものの、少しもがんは小さくなっておらず、むしろ悪化して、倍以上の大きさになっていたことを初めて知りました。すべての検査結果が最悪で、もしあるとしたら(ないですが)ステージⅤ。ステージⅣで余命三カ月と言われていたのですから、もう末期も末期、余命一週間という感じでしょうか。そのとき私が感じた怒りは、ただならぬものがありました。
「昨年暮れの時点で悪くなっているのがわかっていたはずなのに、どうして伝えてくれなかったんですか?」
抗がん剤を投与していたのに、私のがんはどんどん悪くなっていた。そのことを一切教えてくれなかったのはなぜか? 抗がん剤で何回までやりますと言った以上、そのコースが終わるまでは実行するしくみになっているのでしょう。
「人の体をなんだと思っているの? 冗談じゃないよ! だからこの病院は患者の顔も見ない人たちばかりで、二つの派閥に分かれてしょっちゅう揉めたりしているのよ!」
そんな私の怒鳴り声が病棟の部屋に轟きわたっていました。それを制する人は誰もおらず、看護師さんたちは下を向いたままうなずき、若い先生たちも無言で聞いていました。
「だからオプジーボをやってと言ったでしょ!」と叫ぶと、呼吸器科の医師が「教授に伝えます」と言いました。さらに、「教授に伝えるなんて言ってる場合じゃないわよ、すぐオプジーボをやってください」と訴え続けたら、「やれるかどうか調べるのに、一週間から十日かかります」という返答がありました。
怒髪天を衝くとはこのことでしょう。私は怒りで自分の髪が逆立つのがわかりました。けれどもその場で先生に言いたいことを思い切り言ったので、その後はグズついた気持ちにはなりませんでした。さすがに参ったなとは思いましたが、それきりで終わりました。
「生かされるってどういうことなのかな?」
ステージⅤの最悪の状態でも、私は苦しくもなく普通の状態で生かされている。このことには、何か意味があるんじゃないか、そう感じるようになりました。
がんが
最悪の状態で
生かされていることの
意味を考えた。