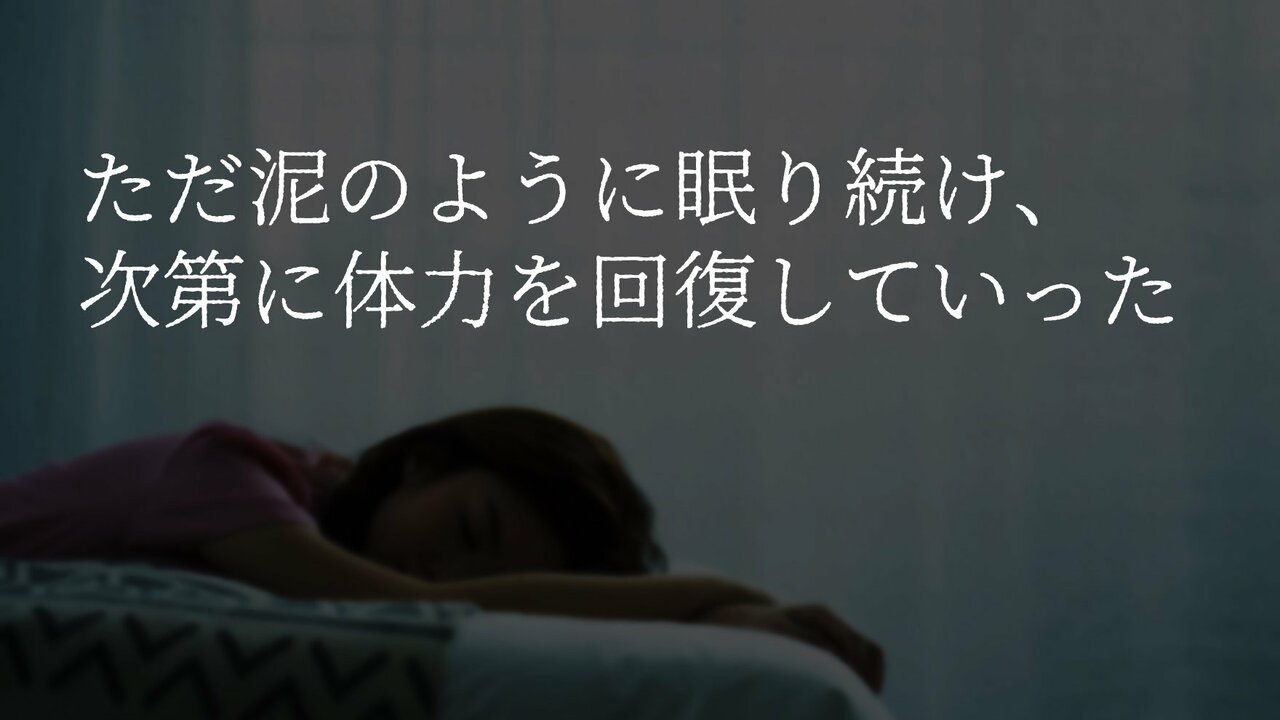第二章 がん細胞との会話
16 元気すぎるがん患者
入院中、私はとにかく元気でした。院内の売店へ行くのにも、最初は看護師さんが付き添ってくださいましたが、あまりに元気なのでそのうちついて来てくれなくなりました。いつも「一時間くらい散歩してきます」「コーヒー飲んできます」と自由行動をしていました。病院の裏から上野の公園へ行けたので、一人で遠足していたのです。
後からお聞きしたところによると、化学療法室で抗がん剤治療の処置をしてくださっていた二十人くらいの看護師さんたちも、「本当にあの方、がんなのかしら?」と話していたそうです。見舞客が来るたびに、私が「せっかく来てくれたんだから、下の喫茶店でも行こうか」と誘うので、「大丈夫なんですか!?」とよく驚かれました。
私ががんになっても変わらない様子を目の当たりにして、皆さんビックリし、「勇気をもらった」と帰っていきました。中には泣きながら入ってくる人たちもいて、こちらの方が「何しに来たの? どうして泣いているの?」とオロオロするばかりでした。
また十日に一度、必ず電話をしてくる人もいて、声で判断して、「ああ元気そうですね」などと言うのです。そのうちに私は頭にきてしまい、「あなた、私が悪くなるのを皆に話すために電話してくるの?」と言ってしまいました。本当に心配して電話をくださっていたのでしょうけれど、「こちとら元気よ、ご心配には及びません」と言いたくなったのです。
正直、心配ばかりをされると、ときとして気が重くなることもありました。その一方で「巣鴨のお地蔵さんが身代わりになってくれますから、これで患部を洗ってください」とお地蔵さんの体を洗ったタオルを持って来てくださる方があったり、「朝一番で裏山の神社にお百度参りしていました」とか「毎日太陽に向かって村松さんが回復されるようにお祈りしています」というようなメッセージをたくさん頂戴して、温かい励ましが胸にしみました。
自分のことを思ってくれる人の有り難みを感じつつ、心配され過ぎると鬱陶しく感じたりして、本当に身勝手なものです。そんなことを思ったり考えたりする余裕があったのも、元気だった証拠だと思います。
四回目の抗がん剤を受けたときに、生理的に「ああ、もう受けたくない」と思いました。体のだるさや脳の動きが悪くなるのを感じたり、尿の出が悪くなったりして、正常な体が壊れていくような感覚を覚えたのです。
「抗がん剤ってこういうことだったんだ!」と身をもって知りました。医師に「もうやりたくないんです」と伝えると、「二月からは変えましょう」と言われたので、弱い抗がん剤だけにするなど何らかの新しい措置が取られることになっていました。
早速、そのことをがんにも報告しました。「がんちゃん、抗がん剤はやっぱり私にはあんまり合わなかったみたい。また違ったやり方であなたに協力してもらうことになりそうだけど、よろしくね」

心配してくれる
有り難みを感じる一方で、
心配され過ぎることの
鬱陶しさを感じた。