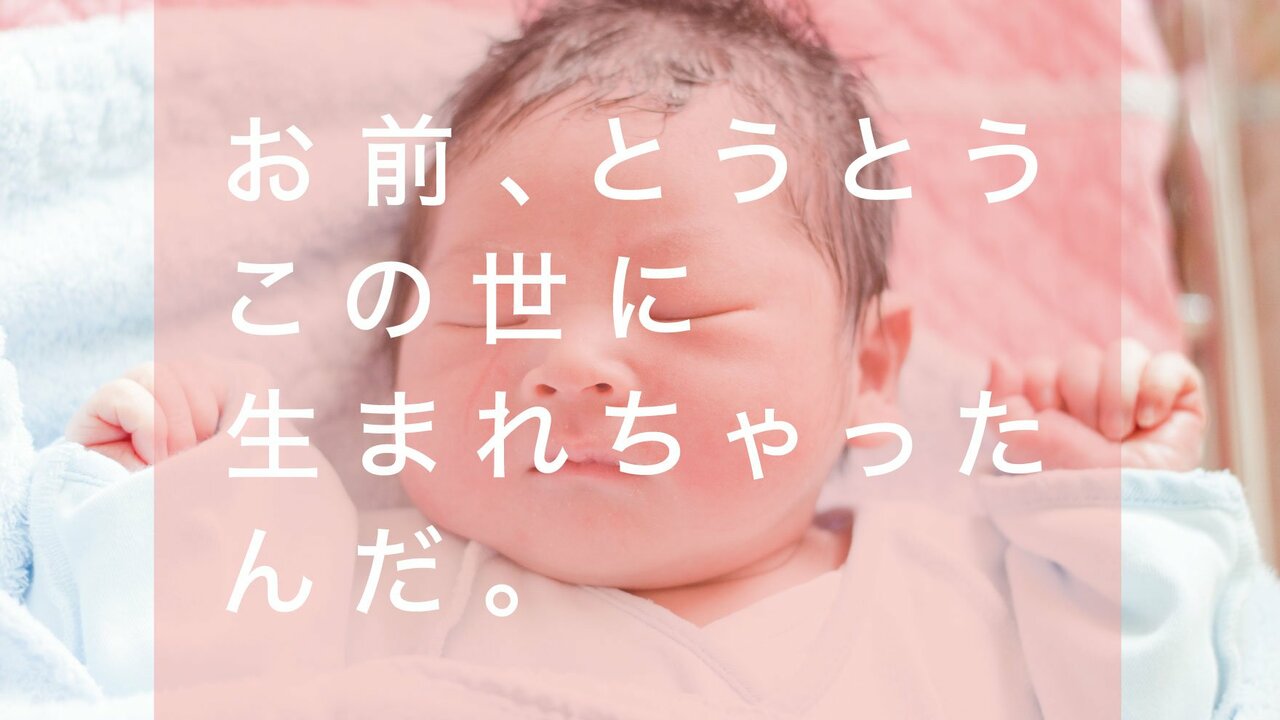『八汐の海』
十一月には室町の養母の誕生会に復帰した。長い空白がある。養父と連れの重信は宗近の父に似てきた。宗近の父も故人である。八十五で亡くなって、葬儀場で本宅の親族と離れた席で二人、養父と重信さんといっしょになった。もう室町の養母はいなかった、会うのはそれ以来。
バスクのどこかの小さいロマネスクの教会の祭壇画を写メールで送ってきて葵に似ている、あの人は僕らの守護聖人だった、と。いつも僕ら。母とではない僕ら。一人称複数への嫌悪はほとんど敵意に近づいていたが、守護聖人、で救われた。そしてその人の地上の喜びであった君を僕らは愛さずにいられない、と。
草色のワンピースに砂色のコート、取り敢えず外出着。外苑通りのフレンチレストランだった。蟠りがあったのは淳だけだから、仕事の経験を重ね鷹原兄弟を知った今では二人への嫌悪は独り善がりだったと反省される。昔変わらぬ偉丈夫の二人に代わる代わる抱き締められると目頭が熱くなる。彼らの父性愛は特別なのだ。
落葉し始めた銀杏並木が街を一種宗教的な祝祭色に彩っている。
「ミダス王が触れた街」
「葵さんが言ったんだよな」
葵は聖公会の執事の孫娘だった。母を語るならその出自を言わざるを得ない。
室町と重信は高校のボート部で出会ってからずっといっしょである。室町が商社に、重信がボート部のある会社に就職して生活の地盤ができたから男二人の人生に脅威はないはずだった。
罠にかかるのはこちらの落ち度なのだろうか。つれなくされた(室町の性格を考えればほとんど言いがかりである) 従姉妹だか再従姉妹だかその親だかから腹いせに男色の嫌疑をかけられて室町が窮地に立った。事実、二人は初めからホモセクシャルな仲だった。気が付いたのは何時だったかと問われれば、艇庫からボートを出した時、と口を揃えて言うだろう。けれども外に漏れたはずは絶対になかったのだ。わが身の護り方を心得なければ連れの身を危険に曝す。
「事実を否定するのも癪だしなあ」
「独身主義だと言ってしまおうか」
海外勤務で逃げる手もあった。
「この先どこへ行っても追っかけられるんだろうな。職場が絡むともっと厄介じゃないか」
若さの勢いだ。逃げ隠れはしないという矜持がある。汚い手で触れるな。
時宜を得て葵との見合い話が持ち込まれた。敬虔に育った娘は初対面で決めてしまった。
慇懃に断って逃げようとした室町は、可憐な娘に誠意を尽くすつもりで重信も呼んで、断る理由が娘の欠点にあるのではないと打ち明けた。何たることか、娘はそれはそんなに不道徳なことなのかと反問した。
「慈愛と信頼では足りなくて? どうしても性愛が必要ですか?」
こんな問いは後にも先にもこの時だけだ。彼らは年長であるからたじろぎながらも
「あなたは大それたことをわかって言っているの?」
「君、悪いが世間知らずのお嬢さん、はっきり言うが、僕らは性愛も求めているんだ」
と諭したり、少々は苛めたりもしたのだが
「未熟だとおっしゃりたいなら、ただ程度の違いだわ」
「もっといい心を持つようになりたい。あなた方の契りを決して損なわない」
二人は苦戦した。
聖公会の教会で挙式し、しきたりや社会契約上の手続きも終った頃、室町が無垢な妻に
「なんでこんな、別れる理由のある男との結婚を志願したの?」
と訊くと
「あなたを大好きになったから」
「僕が君を抱くことはないよ」
「わたしもそれがいい」