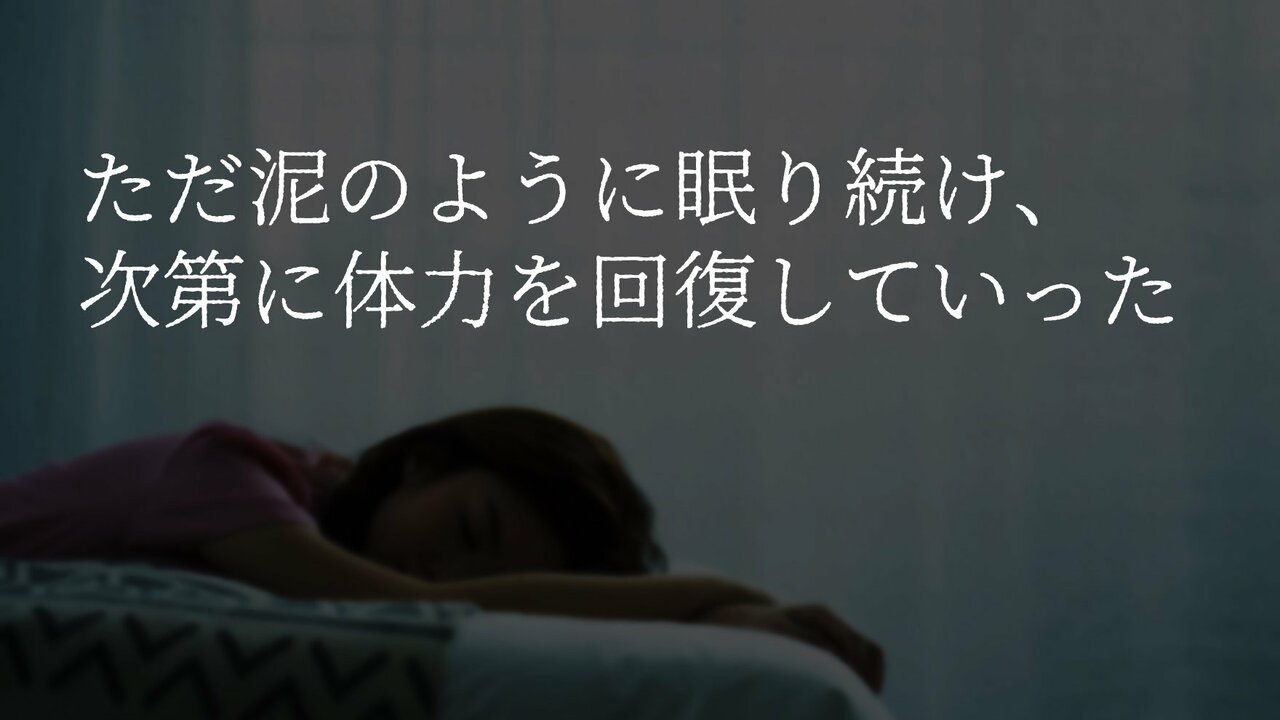第二章 がん細胞との会話
15 幼いときに意識した「死への恐怖」
余命三カ月と言われて、驚かなかったと言えば嘘になります。人並みに「健康で長生きをしたいな」という気持ちはありましたから。けれど私はある人との出会いと別れをきっかけに、死ぬことが怖くなくなっていました。そのことについては、もう少し後の章でお話ししたいと思います。
最初に「死」を意識したのは小学校五年のときでした。家業に深刻な問題が起き、母から「一緒に死のう」と言われたのです。私の父は戦後、友人三人と畳会社を興して社長になりました。
ところがほどなくして、そのうちの一人に今の価値で一千万円ほどの大金を持ち逃げされてしまったのです。途端に資金繰りが悪化し、窮地に追い込まれた父は、ストレスから浴びるほどお酒を飲むようになってしまいました。
そんなとき、母と二人でお風呂に入っていると、「のり子さん、私と一緒に死のうか?」と言われたのです。私は「いやだーー!!」と泣いて訴えました。いきなり「死」というものを突きつけられて、幼心にその怖ろしさを悟った出来事でした。再び母からそのことについて触れられることはなく、私も誰にも話すことはありませんでした。
六十代後半になってから、「実はお母さんに死のうと言われたことがあったのよ」と双子の妹に打ち明けたことがあります。すると彼女から、「えー! 私もお父さんに応接間に呼ばれて同じことを言われたのよ」と聞かされました。
妹もショックのあまり、「いやだーー!!」と部屋から飛び出したそうです。お互いにお互いを怖がらせたくないという思いから、ずっと話さずにいたのです。性格は異なるけれども、「ああ、やっぱり私たちは双子なんだな」と感じ入りました。同時に子どもたちに死を持ちかけた当時の父母のつらさを思うと、心が絞めつけられる思いがしました。
困難にもくじけずに四人の子どもを育ててくれたことには感謝しかありません。私たちが中学に上がるころには、父の仕事はまた軌道に乗り、何の憂いもなくお嫁に行くまでの時間を実家で過ごさせてもらいました。父が常日頃私たちに言っていたことは、「勉強しなさい」ではなくて、「真っ正直に生きなさい」ということ。
正直に自分が生きていても騙される人はいます。それに対して父は「騙される方がいけない。騙す人を見抜けない自分が悪いのだから、人を恨むのは筋じゃない」と話していました。私は「何言ってるのよ、自分も騙されたくせに」と思っていましたが、父は自分の言葉を実践して、決して誰のことも責めることはありませんでした。そしてこれがこの世の勉強だと教えてくれたのです。
そんな父は長年、全日本畳事業協同組合の理事を務めたことから、その功績を称えられ都知事から表彰を受けました。賞を授与されているその後ろ姿を見たとき、私はこういう真面目で真っ正直な人が父でよかったなと誇らしい気持ちになりました。父からは自分の信念を貫くことの大切さを教わりました。

私も自分の信じた道を歩みたい。たとえそれが期待外れだったとしても、自分が決めたのならいいじゃないか、また道は開ける、そう思っています。幼いころに「死」を強く意識したことは、結果的にその後に良い影響を及ぼしたと考えています。
「一度きりの人生だから、後悔のないように生きたい」という信条で精一杯やってこられた気がするからです。それはがん患者になって、なお一層明確になりました。生きているものは、いつも死と背中合わせにある。だからこそ充実した生を送りたい。その思いを強くしています。
死と生は背中合わせ。
だからこそ充実した生を全うしたい。