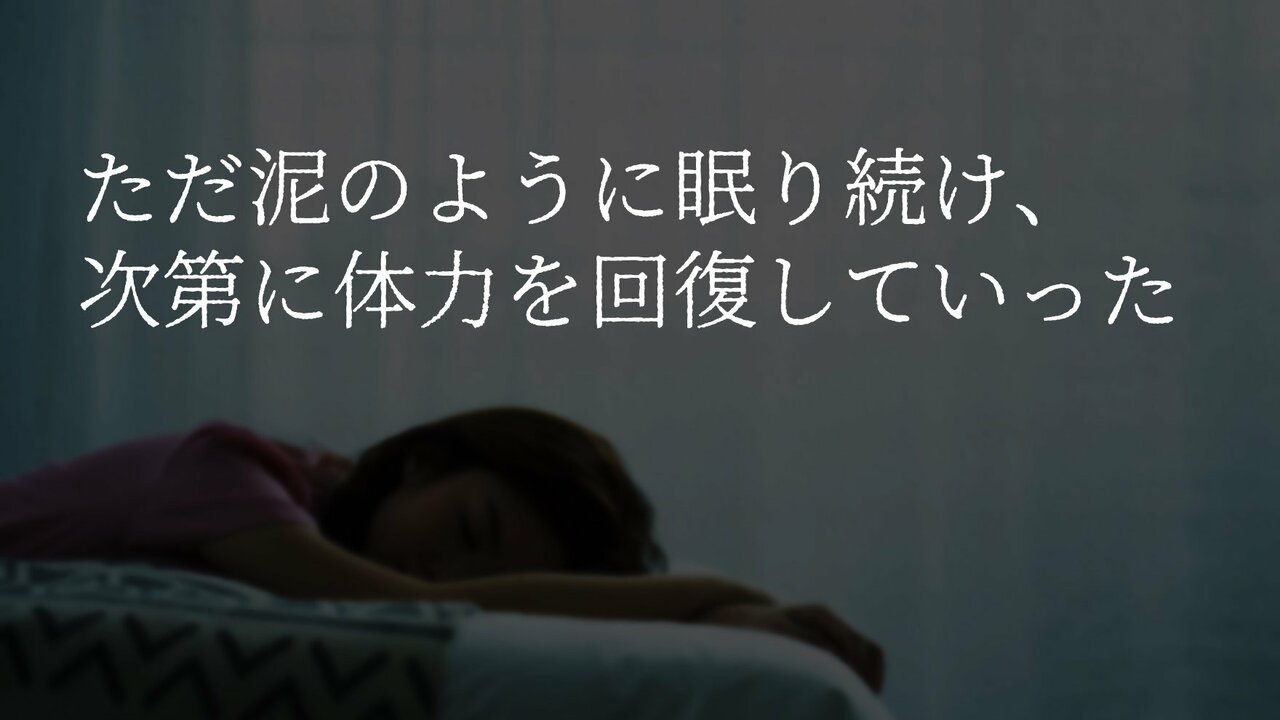第二章 がん細胞との会話
反発精神がもたらしたもの
誰しも医師から重い病について説明されたら、「先生、それならどうしたらいいんですか?」とすがるように尋ねるのが普通でしょう。自分の体のこととはいえ、病気に関しては素人ですから、専門家である医師に助けを求め、すべてを委ねるのは自然なことです。
けれど私は違っていました。最初から反発していたのです。
もともとこの病院で三、四カ月に一度は検査を受けていたにもかかわらず、私の肺がんを見つけたのは人間ドックだったということにも不満を感じていました。そして何より私は人の言う通りに生きない人間でしたから、医師に余命三カ月と宣告されても、少しもピンときていませんでした。最初から「がんでは死なない」と思っていましたし、医師の言う通りには生きないとはなから決めていました。
私は常日頃、人の言うことの真逆に考える性質なので、今回はその反発心が病気と向き合う上で大いに役立ったと思います。私の反発精神は家庭環境によって育まれたと言えます。
祖母がとても躾に厳しく、畳のヘリを踏んだだけでものさしで叩くような人でした。口を開けば「あなた方は、世が世であれば、~の家柄なんですよ」とか、「女は強くなるとロクなことがないから、働いてはいけません」というような明治以前の古いしきたりばかりを話していました。

左から父、筆者、母、祖母、双子の妹、祖父
私は姉弟の中で一番の跳ねっ返りでしたから、「世が世ならって何なのよ、今と関係ないじゃない!」と反抗しては、祖母とよく喧嘩をしていました。やがて人が敷いたレールの上を歩くのはいやだ、何事も自分で責任が持てれば、自分の信じた通りにやるべきなのではないかと考えるようになりました。
そうした性質から、とにかくがんの治療に関しても何でもかんでも医師のいいなりにはならずに、自分の考えをしっかり持って判断していこうと決めました。それがもし裏目に出ることになったとしても、自分がよかれと思ったならいいではないかとすることにしたのです。
この姿勢はその後の治療のさまざまな過程においても一貫していました。もちろん幾たびも迷いが生じることもありましたが、結果的に良い方向へと向かわせる流れをつくったのではないかと感じています。
持ち前の反発心が、
医師の宣告通りには
生きないという
強い気持ちにさせてくれた。