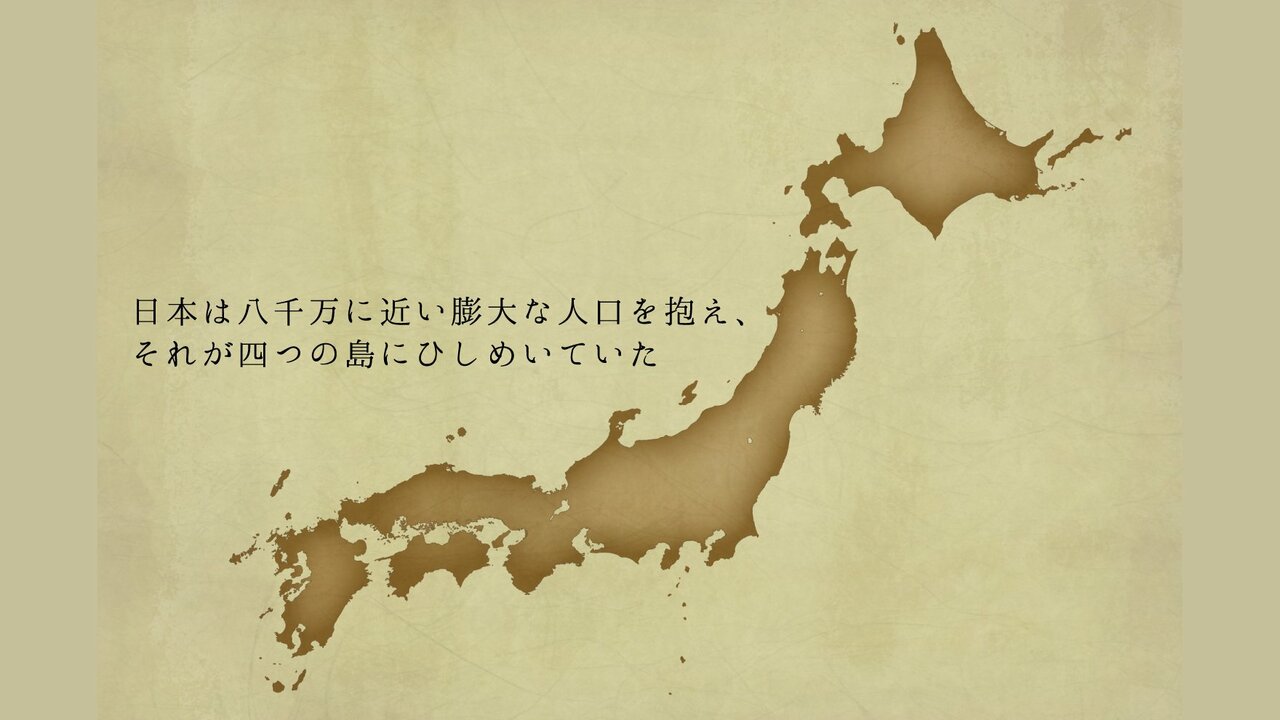第二章 破 絶歌
「魔界の住人、少年A 酒鬼薔薇 聖斗」を聖書から糺す
ちょうどその頃、とある出来事を通して恨みの対象は猫に集中し、恨みそのものが質的に変異し、猫殺しという行為は彼にとっても制御不能になっていました。小学六年生の頃には猫殺しはもはや解剖ではなく、殺害そのものが目的と化し、殺害方法も残虐を極めこれでもかと言わんばかりになりました。小学校を卒業するまで二十匹以上の猫を殺しまくったとのことです。
彼の幼い生命哲学が「命」を「物」として認識し、「死」もまたその裏返しの「物」と理解したのは当然かもしれません。我が国における大前提が進化論教育とそれへの信仰であり、教育方針が唯物論のすすめだからです。教育熱心な国民はそのように教えられ、それが真理であると躾られてきたのです。
国全体の教育方針と人間観が究極のところ、人間とは即物的な「物」であると教え込もうとするのであれば、少年Aほど真に受けてしまった哀れな被害者はいません。著者の髙山文彦氏はこの事実にも気づいていました。
曰く「ひとつの国にとって自殺行為とは、伝統的なものを根こそぎ奪うことばかりではなく、最終的にはこれからの時代を生きていかなければならない子供という未来の大人たちから、生と死の根拠を奪い去るということである」と述べるからです。著者はこの国の教育方針である進化論と、そこから派生する人間理解のための世界観が的外れであるということは、既に承知していたのです。
さて、猫殺しが繰り返された結果家の付近から野良猫はいなくなってしまったとのことですが、それには理由がありました。猫殺しの最中に今まで体験したこともない興奮を覚えた、性的快感を得た、という意味のことを周囲にもらしていたのです。
精神鑑定書にも人間は皆自分と同じように、殺しの中で性的興奮を覚えるものだということが彼の言葉として記されています。それだけに友人のリアクション「おまえ、おかしいんとちゃう?」の言葉は、想像もしない衝撃だったようです。
神戸家裁の調書にも「自分は他人と違う、異常だ、生まれてこなければよかった、人生は無意味だ」という内なる葛藤はこの時から始まったと記されています。少年Aは猫殺しをやめることができない、中毒患者となっていたのです。
そのたびごとに落ち込む自己嫌悪、「酒鬼薔薇聖斗」という新しい人格を自分の内側に創り上げたのはその頃です。「猫を殺して楽しんだりする自分にたいして、酒鬼薔薇聖斗という名前をつけた。僕自身を嫌だと思う気持ちを紛らわすための理屈をつけようと思った」とのことです。
彼は狂気と錯乱の中で猫を殺しまくっていたわけではありません。少年Aには動機があり、理由も説明できており、途中の筋道にも整合性があり、保身と責任転嫁の理屈まで用意することができたのです。この頃の少年Aは、既に「魔界の住人」であり、しかもその世界の祭司となっていたのです。
その頃夢の中に現れたのがバモイドオキという神であり、光の塊のような存在であったとのことです。曰く「バモイドオキ神は、僕が唯一信頼できる存在です。姿は見えない。何にも与えてくれないけれども、脳内宇宙にずっといる」。
小学五年生の時に愛する祖母を失い、彼の魂は孤独な「根無し草」としてさ迷い始めました。親兄弟、学校の友達、全ての集団からもドロップアウトしたのです。
他者に対する人間観も歪みに歪み、中学二年生にして、「人の命はそんなに大事なんですか。人の命も、蟻やゴキブリの命と同じやないですか」と平気で言える有様です。しかし、「自分の命は大事や」なのです。