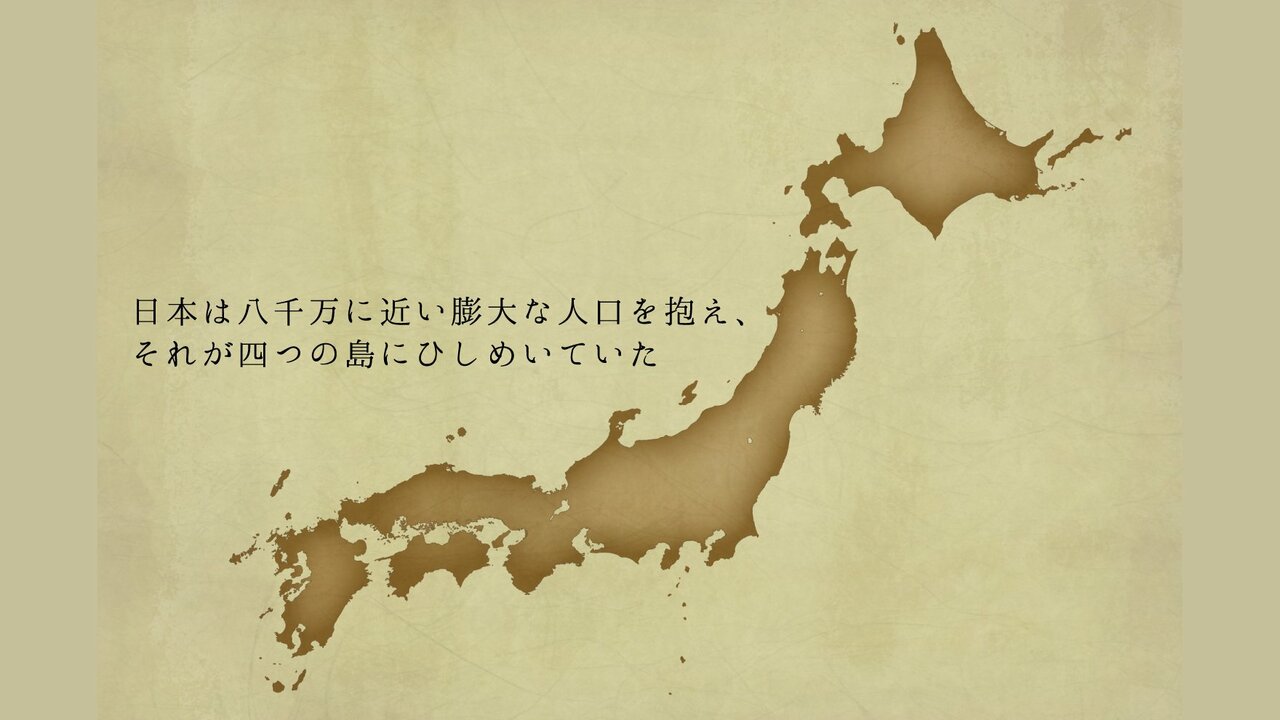第四章 目覚めよ日本
出来レースの「為にする」事後法
「日本人である」という均一的国民全体を洗脳するのは、そういう意味では容易だったのかもしれません。日露戦争の勝利以降、日本に脅威を覚えた欧米列強はアメリカの対日戦略であるオレンジ・プランを筆頭に、「日本人とは何か?」という研究に着手していたのです。
その長所短所や得手不得手、国民性の細部に至るまで徹底調査され四十年に亘り調べ尽くされていたのです。もちろん、打倒日本のためにです。
その洗脳プログラムを実行に移した世紀のイベントが、いわゆる「東京裁判」という茶番劇です。時は昭和二十一年のことでした。
インドのパール判事が「日本無罪論」を唱えたのは、世界中から袋叩きにされ敗戦にまで追い込まれた「日本と日本人」を可哀想に思ったためばかりではありません。体裁だけの裁判、見せしめの「為にする」復讐劇は裁判そのものへの冒讀であり、断じて許されるものではないと、裁判自体の無効を公言しただけなのです。これこそが歴史と文明への挑戦であり、有罪無罪以前の話だからです。
パール判事曰く、「時が熱狂と偏見をやわらげ、また、理性が虚偽からその仮面を剝ぎとったあかつきには、そのときこそ、正義の女神はその秤の平衡を保ちながら、過去の賞罰の多くに、そのところをかえることを要求するであろう」。
GHQの将軍様が日本を去ってから、早七十年です。「平和と人道に対する罪」などという事後法によりでっち上げられた侵略戦争という大噓、その濡れ衣を鵜呑みにして戦前の「日本と日本人」を訳知り顔で蔑むだけのクリスチャンたちには、一刻も早く正気に戻っていただかねばなりません。そんな福音宣教に祝福などあろうはずはないからです。
濡れ衣は、脱がねばなりません。着たまま乾かそうとするので話がこじれてしまうのです。
今ではGHQの将軍様本人の懺悔録までが解禁となり、一般公開されるまでになりました。実はマッカーサーは、「我々の方が間違いだった」という言葉まで残していたのです。東京裁判の開廷命令を下した張本人が、朝鮮戦争を指揮することで目が覚めたのです。
明治以降の日本が採ってきた政策は、朝鮮戦争におけるアメリカの立場そのものであると気づいたのです。朝鮮半島に一方的に侵入したのが清国であり、それが日清戦争の発端になりました。朝鮮半島に軍港を作るために侵入したのが帝政ロシアであり、それが日露戦争になりました。
今回、朝鮮半島にソビエトロシア連邦と中国共産党軍に後押しされた北朝鮮が突如として侵入したために、旧日本軍なきあとのアメリカ軍がその代理戦争を戦うはめになり、ようやく日本という国が置かれていた生存権ともいうべき地政学的な意味について、マッカーサーはやっと理解できたのです。しかし日本人は鎌倉時代の二度にわたる元寇以来、朝鮮半島こそが日本列島の脇腹に突きつけられた匕首であると、心底知っていたのです。