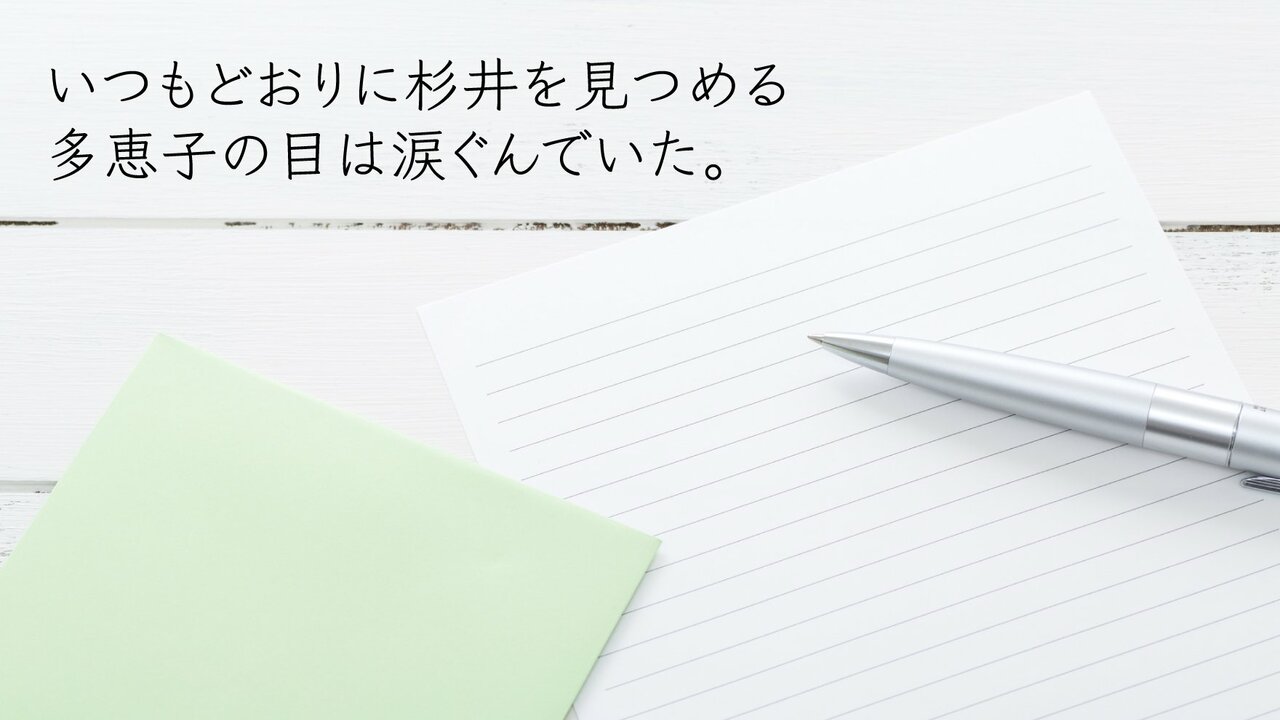休日に母と食事
やがて天ぷらが運ばれてきた。たえは、それに一、二度箸をつけると、
「残してももったいないから、全部お食べ」
と杉井に勧めた。上等な油で揚げた天ぷら、純白で温かな米、杉井は三人前を一気に平らげ
た。連隊の中では望むべくもない味だった。食欲も十分過ぎるほどあった。しかし、たえを前にしての食事は、腹がいっぱいになるという物理的な幸福感を超越した至福を杉井にもたらすものだった。食事を終えた後、杉井は連隊での生活のことを次々とたえに話した。たえは、ただ懐かしそうに杉井を見つめながら、黙ってそれを聞いていた。たえには泣き言でも何でも言えると思っていたが、いざとなると、むしろ無用な心配をさせるべきでないという気持ちが強くなり、結局連隊での辛い話は一切しなかった。
気がつくと、三時間が過ぎていた。杉井は、
「お母様、もう馬の手入れの時間がきますから、自分は帰ります」
と言い、二人は店を出た。たえを市電の停留所まで送り、停車している電車を指して、
「これに乗って、名古屋駅で降りて下さい」
と言うと、たえは、
「分かりました。この次の電車にしますから、お前はお帰り。元気でね。さようなら」
と言った。杉井はたえと別れ、営門に向かった。途中振り返ると、たえは風呂敷包みを大切に抱えながら見送っていた。徴兵以来、時に淋しそうな目をするのを見て、たえがあまり喜んではいないのではないかと感じてきたが、この瞬間、生命をも保証されない戦地に息子を送りたくないという母親としての自然な情愛は、国民は皆お国のためにすべてを捧ぐべしとする国家の理念にはるかに優越するものであると、杉井は確信した。