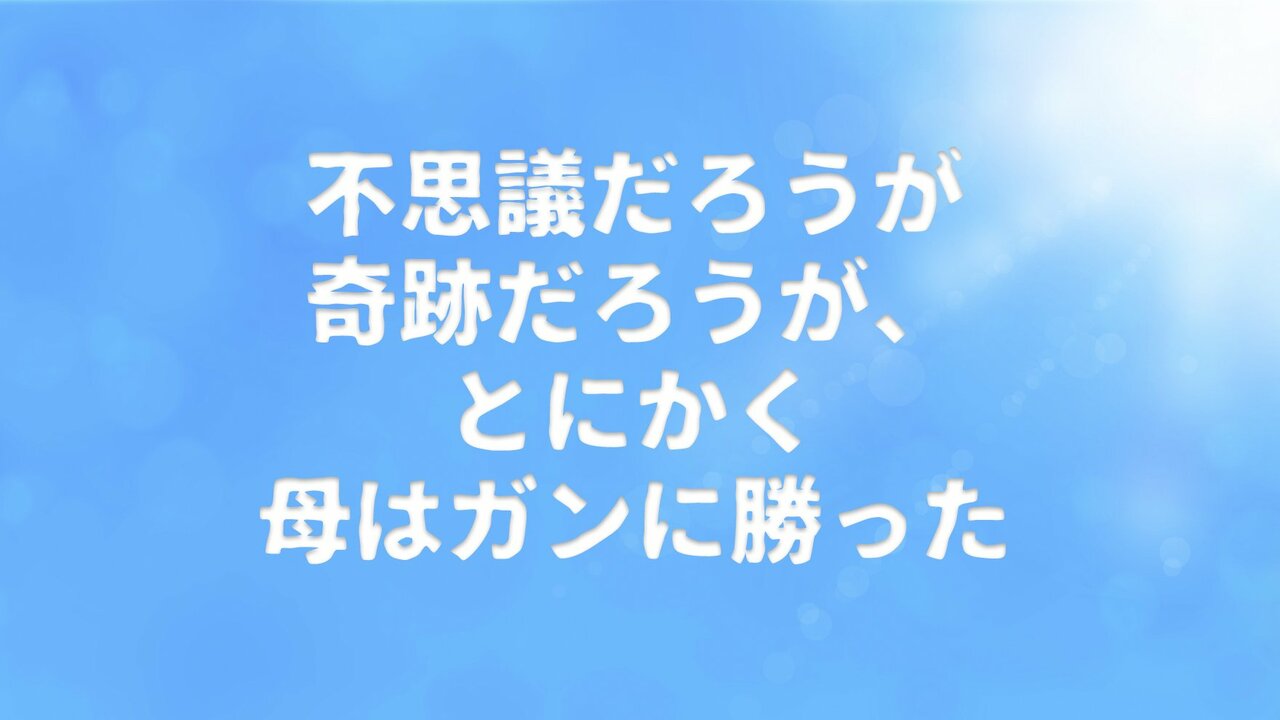第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
三月七日(月)曇
否、初めてではない。妙なことに、ふと、あの日の事を思い出していた。
二十年ほど前、事業がうまくいかず、融資の抵当になっていた家を銀行に差し押さえられる事が決まった日の夜であった。
私は独り自室のベッドに横たわり、むせぶ涙のやりばに往生していた。そこへ、不意に母が入ってきた。
咄嗟に腕で目をおおったが、その隙間からこぼれた一雫を母は見逃さなかった。
「お前、泣いているのかい」と母は言い、「目薬をさしたんだ」と、私はうそぶいた。
母は私の肩を抱き起こし、「男だって泣いてもいいんだよ。男泣きっていう言葉はそのためにあるんだ」と言って、私を抱きしめた。
私は堰(せき)を切ったように、誰はばかることなく大声を上げて泣いた。
今、あの時と同じように、母と私は強く抱きしめ合っている。
言葉は既に何も無く、ただ涙を共にするだけ。
母は体力がなく、時々泣き声をやめ、しばらくヒクヒクしたあと、またオンオンと声をあげ「怖い、怖いのよ……」と、呻(うめ)く。
そうして、どれくらいの時を過ごしただろうか。ひとしきり泣いたあと、母は私の名を呼んだ。
*
いま母は、否、おそらく誰もが、自分という存在がこの地上から無くなってしまうという想定を理解できない。今ある意思・思考は何処へ行ってしまうのかという認識が計れない。だから、恐怖せざるをえない……。
何年か前、難病をかかえた対馬孝一という友が言っていた。
「人がいつか死ぬという事は解っているけれど、その期限を言い渡されると、その瞬間から恐怖が始まるんだ。それが一年でも十年でも二十年でも関係ない。『君の病気は治らない。でも、同じケースで最長十八年生きた人もいるよ……』って、何の慰めにもならないんだよ。まるまる生きたって十八年でしょ。それに向かって秒読みを数えるだけのことだ」
絶えた命は一旦宇宙へ還り、また新しい姿を得る。それを本当に信じる事が出来れば、人は死を恐れなくなるのだろうか……。