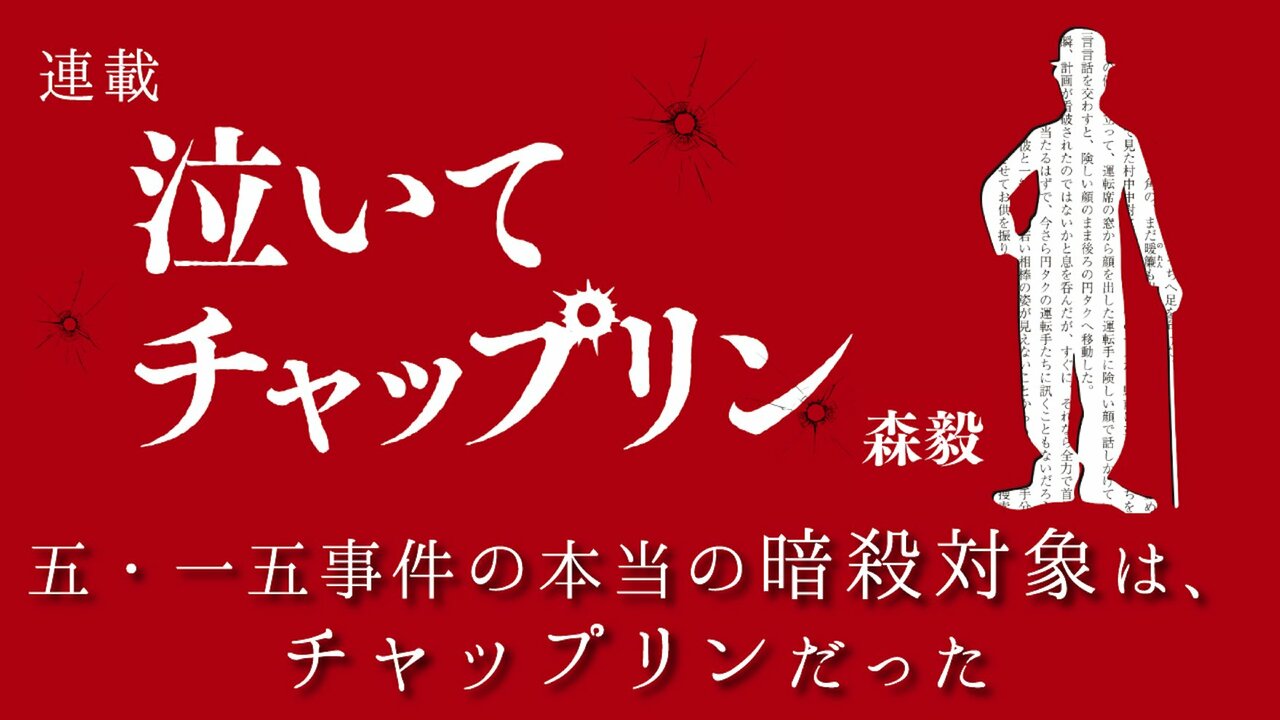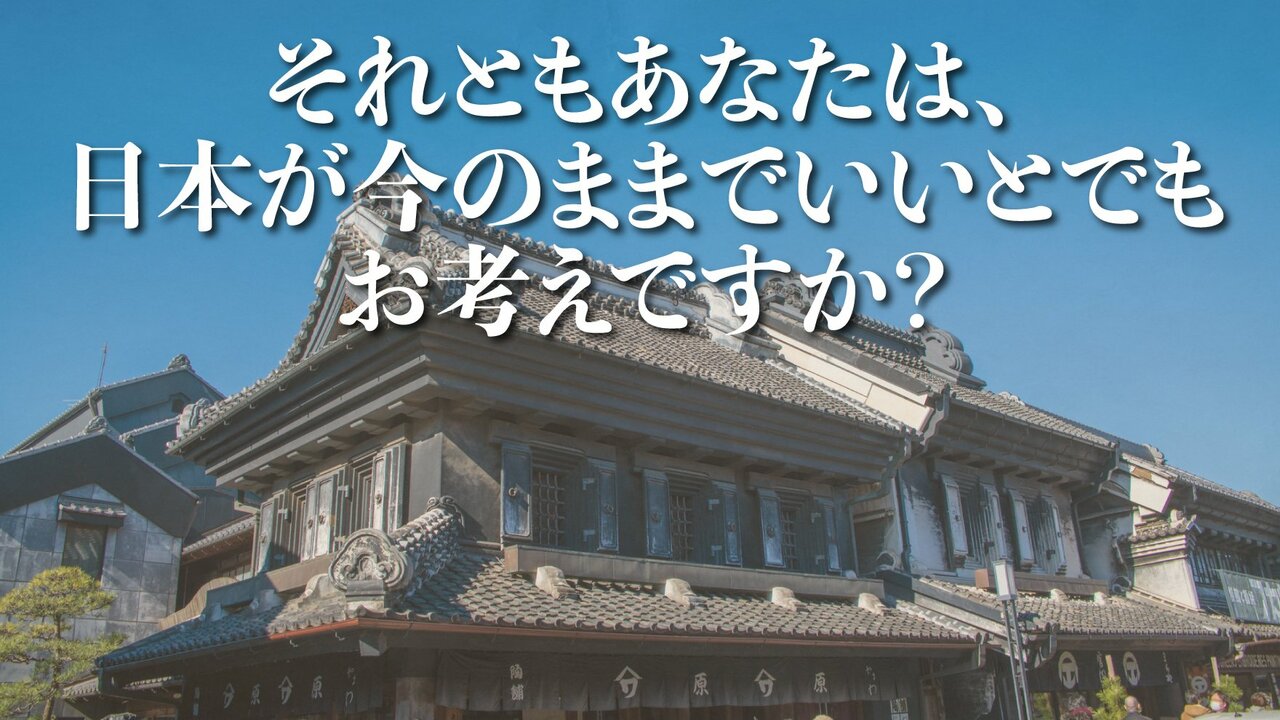西田は歩一の山内俊一大尉とは陸士の同期生で、共に青年将校の国家改造運動の先駆者といってもよかったが、八年前に健康上の理由で軍を辞し、今は急進的な一部青年将校等のテキストともいうべき、『日本改造法案大綱』の著で知られる北一輝(きたいっき)の下で働いており、今なお青年将校等に強い影響力を及ぼしていた。
また軍を辞してから一緒になった妻初子と夫婦二人きりの暮らしだったが、その住まいは借家とはいえ、子供が三人もいる木坂の家の倍は部屋数がありそうな、高級住宅の部類にいれてもいいような家だった。
その理由の一つは、青年将校等の、いわば「鹿ヶ谷(ししがたに)」、つまり密会場所としているためだった。したがって、もし田島中尉が何らかの重大な決断をしたとすれば、真っ先に西田に相談するのではないかというのが木坂の読みだった。
が、今宵はすでに雨戸はすべて立て(閉め)られており、その隙間からは蜘蛛(くも)の糸のような細い灯りが幾条か洩れ出ているものの、外から窺ったかぎりでは静かなもので、読みは外れたようだった。
玄関のガラス戸もすでに施錠されていた。
その戸を軽く叩くと、待つほどの間もなく玄関の灯りが点り、妻の初子が顔を出した。
小柄で子供もないせいか、その目は少女のような、キラキラとあどけない輝きを宿していた。
初対面だったが、木坂と申しますが、と名を告げただけで、その目が竦(すく)んだように見開いた。
名前ぐらいは聞いていたのだろう、木坂はちょっぴり同情しながらも、
「あ、いえ、別にご主人に用があってお伺いしたわけでは……今日は、田島中尉殿にお目にかかりたいと思いまして」と、いきなり来意を告げた。
はたして、初子の目は元来の輝きをとり戻し、小首を(かし)げ、そのキラキラとした目で、問い返した。
「えっ、田島さんですか?」
木坂は読みが外れたことを認めると同時に、そのあどけない仕草が意味するところから、千駄ヶ谷と代々木(よよぎ)が隣り合わせの町だったことにハタと気づいた。
「あ、いえ、でしたら村中中尉殿でもよろしいのですが……」
と木坂は、来たついでに、それだけでも確かめておこうと探りをいれてみた。
「あら、でしたら生憎(あいにく)ほんの一足ちがいで、ついさきほどお帰りになりましたが」
「そうですか、それは残念なことを。でしたら仕方ありません。いや、こんな夜分に突然お邪魔して申し訳ありませんでした……ではこれで」
と、笑顔で踵(きびす)を返し、玄関の戸に手をかけた時だった。
「村中くんに何か伝言でもあれば伝えておきますよ」
という男の甲高い声に振返ると、和服姿の西田が懐手をして立って見下ろしていた。
西田と面と向かうのは、彼が北一輝の『日本改造法案大綱』を下敷きに書いた、『天剣党趣意書』という、クーデターを扇動するガリ版刷りのパンフレットを、百名余りの陸士の同期生や後輩たちに、一方的に郵送した容疑で検挙したとき以来だった。
目の前に現れた彼は、口髭を蓄え、いま流行りの洒落た縁なしメガネをかけ、黒々とした髪をピタッとオールバックにして、士官学校在学中には同期生だった秩父宮殿下の、いわゆる「ご学友」の一人にも抜擢されるなど、秀才の誉れ高い毬栗頭(いがぐりあたま)の青年将校だったころの凜(りん)とした面影は微塵もなく、いうなれば、得体のしれない成り金の青年実業家といったところだった。
また事実、世間では青年将校等のカリスマ的な存在と思われている北一輝の下(もと)には、「政党と結託して膏血(こうけつ)を搾(しぼ)る財閥」というレッテルが貼られ、青年将校等の非難攻撃の的になっている三井や三菱などが、その矛先を和らげようと人目を避けて訪れていたのであるが、西田はその応対を一手に引き受けており、これといった職業も資産もない彼がこの不景気な世に借家とはいえ、千駄ヶ谷の閑静な住宅街に分不相応な一戸を構えていられるのもそのためだった。
もっとも、彼はそれを「敵の弾丸をもって敵を倒す」という、諸葛孔明(しょかつこうめい)が「赤壁(せきへき)の戦」で藁人形を乗せた舟を浮かべて敵に矢を射らせ、その矢を使って戦った故事に倣った兵法の一つであると同志たちには弁明していたが。
何れにしろ木坂には、これが彼の本性ではないかと見えるほどの変わりようで、多少面喰らいながらも、また村中中尉に言伝などあるわけもなく、頭をひと撫でして、
「あ、いえいえ、ご伝言いただくような話ではありませんので。ですが、あるいは、もう村中中尉殿からお聞き及びかもしれませんが、恥を忍んでいいますと、今夜わたしの部下が、何処でどう間違えたのか、村中中尉殿に大変失礼な真似をしてしまったそうですのでお詫びしなければと、それで夜分をも顧みずお邪魔したような次第でして、ただそれだけのことですので」
と笑顔で、冗談とも皮肉ともつかないような苦しい言い訳をしてお茶を濁した。
「ほう、いったい何をやらかしたんですか?」
と、意外な答が返ってきた。
木坂の笑みも消えた……村中中尉が今夜のことを、すくなくとも笑い話のネタぐらいにはなるようなことを何も話していないとすれば、田島中尉が帰ったことも知らせていないのではと思えた。ということは、そこには同志であり先輩でもある西田元少尉にも話せない何か重大な秘密があるからにちがいないとも考えられた。
ひょっとすると、若い血気盛んな「士官学校組」が独自の急進路線、すなわち過激な「直接行動」に踏み切る兆候ではないかとも考えられたが、そんな疑念を悟られないためにも、木坂は大袈裟(おおげさ)に手を振って応え、話の舳先(へさき)を変えた。
「いえいえ、そんな部下のヘマを吹聴(ふいちょう)するようなことは。それにしても、なんとも嘆かわしい世の中になったもんですねえ。いかに上司の命令とはいえ、わたしらが将校殿のお供をしたり、夜分にお宅にお邪魔しなければならないなど、これも時勢というか、やはり秕政のせいですかねえ」
はたして、西田は目を輝かせて渡りに舟と乗ってきた。
「ほう、あなたが政治を批判するとは愉快ですねえ。しかしそこに気づかれたのであれば今一歩進んで、我々を見張ったり、尾行するような無駄なことはやめて、我々に協力すべきだと思いますが、いかがですか?
刻下(こっか)の政治、経済、軍事と軟弱外交、そして国民の膏血を搾る財閥と、それを擁護する横暴な官憲、いったいどこに大日本帝国の真の姿がありますか。それともあなたは、日本が今のままでいいとでもお考えですか?」
と、この初手からたたみ込む青いといえば青い、紋切り型といえば紋切り型の論法で、彼等は優柔不断な上官や朋輩を籠絡(ろうらく)し、心ある者を辟易(へきえき)させていた。
潮時だった。
「いえ、わたしら憲兵隊の下士官ごときに何ができますか。ただ上司の命令で走り回っているしか能のない人間ですので、つい愚痴っぽいことを口走ってしまいましたが、これ以上長居をして、またつまらないことを口走ってもいけませんので、今夜のところはこれで失礼します」
と、木坂は当たり障りのない答で受け流し、あらためて玄関の戸に手をかけた。
が、西田はすっかり勢いづき、
「いやいや、そんなご謙遜には及びません。あなたの武勇伝は聞こえていますよ。
なあ初子、お前にも話したろう。この方が参謀本部の暴れ馬といわれている橋本中佐と、長少佐をお縄にした荒木陸相閣下も一目置く、特高主任の木坂さんだ。今後も、何かとお目にかかることになるかもしれないから、よく憶えておきなさい」
と、一歩さがって控えている妻にも余裕綽々(しゃくしゃく)の笑顔を見せた。
「お縄にしたなどととんでもない。参謀本部のエリートの方々をお縄にするなど、憲兵隊の下士官にどうしてできますか。今も申しましたように、それもただ上司の命令で、しかもあの時は、荒木閣下直々のご命令でお二人を憲兵隊の司令部に丁重にお連れしただけのことです……それに、その件は一切なかったことになっていることでもありますからね」
と木坂は、それが別れの挨拶でもあるかのように苦笑し、かぶりを振った。
それは元号が昭和と改まって早々の、「おらが大将」こと田中義一(たなかぎいち)元陸相の「軍事機密費横領疑惑事件」から、一将校の桃色事件のもみ消し工作まで、軍部の乱脈ぶりを嫌というほど見てきた二十年余の憲兵ぐらしのなかでも五本の指にはいる、おそらく生涯忘れないであろう後味の悪い事件だった。