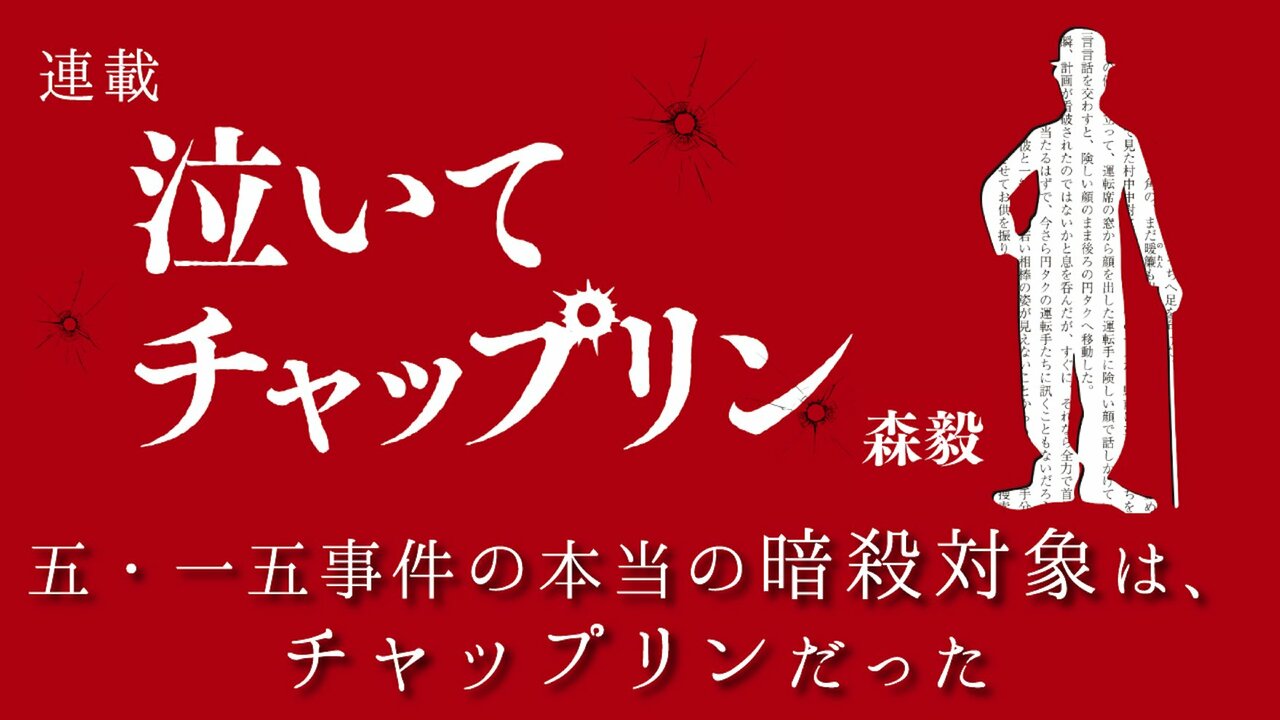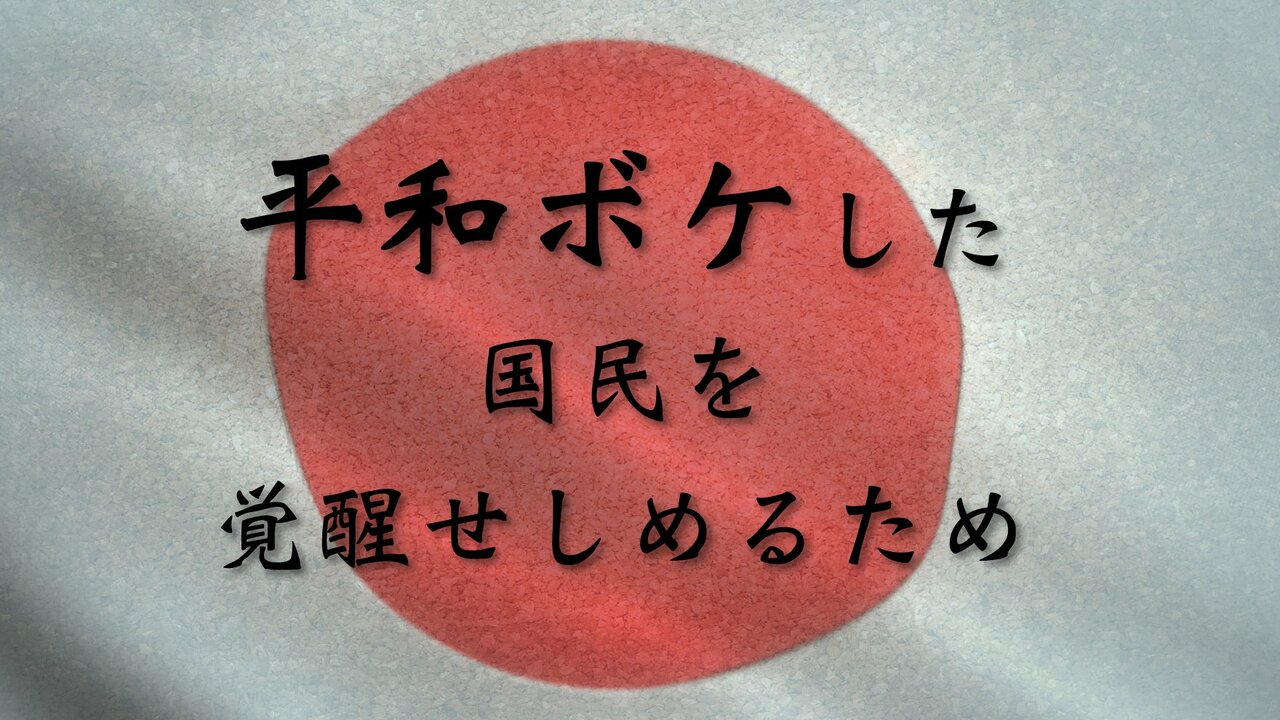「ええ、私自身、そのような成り行きになってしまったことに少々驚いているのですが、これは元はといえば、今いわれた古賀くんや中村くんと、それに三上中尉らが中心になって『海』の同志たちが立てた計画でして、それは、今月十五日の日曜日の夕刻に決行するというものでした。
日曜日なら、士候等も自由に外出ができるという理由もあってのことですが……その計画というのは、時期尚早とする『陸』と、すでに機は熟しているとする『海』との隔たりが埋まらず、三月の陸海合同の会合が不調におわった直後からすすめられていたそうです。
後藤くんらは、私や村中くんに反対されるのは分かっているので、内緒で古賀くんたちと連絡をとり合っていたのですが、彼等の様子が急によそよそしくなったので、一カ月ほど前、後藤くんを問い質(ただ)して、私もはじめてこの計画を知った次第です。
ご承知のように彼等は、なかでも後藤くんは吉田松陰(よしだしょういん)の信奉者で、『知行合一(ちこうごういつ)』を旨とし、『機はわれより拵えて敵とす』という、まさに『猛士』といってもいいような男ですが、その計画は、犬養首相と君側(くんそく)の奸牧野(かんまきの)内大臣を芟除(せんじょ)し、政友会本部をはじめ三井三菱の本店や日本銀行、警視庁、それに東京郊外の数カ所の変電所を襲撃して、帝都東京を騒乱状態に陥れ、いまだ逡巡している同志だけではなく、平和ボケした国民を覚醒せしめるため、自ら警世の乱鐘となって散ろうというものでした」
「なるほど。つまり捨石覚悟の魁(さきがけ)になって散るということかな」
「そうです。士候の一人が、『私は未熟者でなにもできませんが、死ぬることだけはできますので喜んで捨石になります』と笑っていいました。もちろん捨石というのは、その先の手を読んだうえでの一石で、その先の読みもなく、ただ討死するのは犬死にひとしい行為であることぐらいは彼等も承知しているはずですが、
『三軍も帥すいを奪うべし、匹夫の(ひっぷ)志(し)を奪うべからず』といいますし、死を覚悟している者にはそんな道理も通じません……しかし、その前回の会合でも、
『こんにちの兵たちの家庭が苦しむような状態で、どうして安心して戦争にゆけるか』と、栗原少尉も相変わらずの熱弁をふるっていましたが、それもまた一理で、今や国民の、ことに農民の窮状は一日たりとも蔑ないがしろにすることができないのも事実です。
大尉殿にこんなことを申し上げるのはまことに僭越(せんえつ)ですが、伊藤博文(いとうひろぶみ)公も、維新前夜の若い頃には『攘夷(じょうい)派』の急先鋒で、英国公使館を焼き討ちしたと聞いております。
また、大隈重信(おおくましべのぶ)侯も、
『明治維新を去る三、四年前においては、天下の志士は(ただ)に前途を観察する能(あた)はざりしのみならず、大概皆紛乱の場に輾転(てんてん)したるに過ぎざりし。……有りのままを言えば、かかる際に処したる人は、眼界茫洋として東西を弁(わきま)う能(あた)はず、彼方へ泳がんと欲して此方へ流され、北へ向かはんとして南に却(しりぞ)き、遂には意外の方向に於て彼岸に達するが如し。唯其称賛すべきところは、気力と忍耐と臨機の智能にすぎず』と述懐しております。
さらに、維新前夜の先覚者の筆頭が吉田松陰とすれば、維新後の文明開化、すなわち、日本の近代化の先覚者の筆頭にあげてもいい福沢諭吉(ふくざわゆきち)は、『黒船』の大砲に屈して調印した、『日米修好通商条約』という屈辱的な不平等条約や、『アヘン戦争』によって中国を侵略したイギリスの非道なやり方などから、国際外交は、先進列強国が未開地の発展とか文明化のためというような美辞麗句(びじれいく)をいくら並べようが、詰まるところ殺すか殺されるかであると断言しています。
そして、晩年に著(あらわ)した自伝でも、孔子(こうし)の『文事ある者は必ず武備あり』という訓え通り、外交と軍事は車の両輪という考えの上に立って、『国民一般を文明開化の門に入れて、この日本国を、兵力の強い商売の繁盛する大国にしてみたいとばかり、それが大本願で、自分ひとり自分の身にかなうだけのことをして』と、慶応義塾を開設し、『さらに大いに西洋文明の空気を吹き込み、全国の人心を根底から転覆して、絶遠の東洋に一新文明国を開き、東に日本、西にイギリスと、相対しておくれを取らぬようになられまいものでもない。一国の独立は国民の独立心からわいて出てくることだ。できることかできないことかソンナことに躊躇(ちゅうちょ)せず、自分がその手本になってみようと思いつき』と、その決意のほどを述べています」
「ああ。そればかりではなく、福翁(ふくおう)は、日本人の体格向上のため西洋に倣って肉食をするよう推奨し、ビーフシチューやスキ焼きの味まで教えてくれた大恩人だからね。つまり、兵力や商売だけではなく、食の文化にいたるまで、全国の人心を転覆したというわけだ」
と、山内大尉は笑った。
「ええ、たしかに……しかし、そのおかげで、これも、福沢諭吉自身が述べていますが、時には西洋カブレの売国奴と謗そしられ、時に暗殺者の影に怯えながらも、国民一人一人の自立が独立国家の基礎であり、日本が近代国家として生き残る唯一の道であると自らその範を示し、
『こっちの身にかなうだけを尽くして、ほめるなりそしるなり喜ぶなり怒るなり、かってしだいにしろ』と覚悟して、若者の教育に尽力しました。そして後年、
『顧みれば一国全体の大勢は改進進歩の一方で、しだいしだいに上進して、数年の後その形に顕われたるは、日清戦争など官民一致の勝利。さきに死んだ同志たちにも見せてやりたかった』と、往時を振り返り、まるで書生時代にかえったように感激しております。
しかし福翁はさすがに、そんな戦捷(せんしょう)気分に流されず、すぐにつづけて、
『実を申さば日清戦争なんでもない。ただこれ日本の外交の序開(じょびら)きでこそあれ、ソレホドよろこぶわけでもないが』と気を引き締めております。
そして、これもご承知かと思いますが、福翁は日露戦争には反対していて、日清戦争の数年後には、
『世の中をみれば、ずいぶん憂うもの少なからず、近くは国人がみだりに外戦に熱して始末に困ることあるべし』と、そうした好戦的な風潮が過熱し、満州の権益を巡って日露が戦争に発展するのではないかと懸念し戒めていましたが、日清戦争から十年、伊藤博文公の外交努力もむなしく、日露戦争が勃発したのは福翁が亡くなった四年後でした。
しかし、その日露戦争の勝利もまた、まさに近代国家としての日本が試された試金石であり、冷酷非情な弱肉強食の国際社会の洗礼であると同時に、官民一致の勝利であったといってもいいかと思います。
それからおよそ三十年。今また満州事変によって好戦的な風潮が熱を帯びはじめたうえに、年々悪化する日米関係にくわえて、共産主義国家になってもすこしも変わらないソ連の、いえ、こちらも以前にまして露骨になった極東のソ連軍の不穏な動きもさることながら、『八路軍(はちろぐん)』(中共軍)を支援し、支那(しな・中国)の赤化を目論んでいるソ連に備えるためにも、国家改造が焦眉(しょうび)の急で、それやこれやの観点からも、士候等の決起を一概に時期尚早と否定することはできないと思うのです。
しかし私は、それも致し方ないことで、国内社会の情況や国際情勢の変化で、つまり時代の変遷(へんせん)によって人々の考えも変わるのは必然的なことで、それは人類の、いわば『歴史の必然性』ともいえる宿命的なことではないかと思います……あるいは、それもまたありふれた強硬論にすぎないという謗(そし)りを受けるかもしれませんが……」
「いやいや、きみの説はもっともだし、士候等の気持ちも痛いほど分かるが、しかし現実的なことをいえば、つまり事の成否を第一に考えれば、ただ逸(はや)る気持ちにまかせての決起は、アいやいや、そんなことは今更いうまでもないが、なのに、きみまでが敢(あ)えてそれに加担するというのは何故かな? 私には信じ難いというか、まだ狐につままれているようでピンとこないよ」
と、山内大尉はかぶりを振って苦笑した。
「ええ、いま申しましたように、私自身もいまだ夢見心地とでもいうか、目が覚めたら最前線に飛び出していたといった心境ですが、彼等に国家改造の急務であることを説いてきた私が高処(たかみ)の見物って法はありませんし、『隗(かい)より始めよ』ともいいますので。
しかし今回、彼等が独自の判断で決起することを決断したこと自体が証明しているように、如何(いかん)せ、我々の結束も、まだまだ一枚岩とはいえませんし、そうした観点からも、いまだ時期尚早といわざるをえませんので、私も当初はなんとしてでも彼等を説得し、翻意させなければと思っておりました。
最後の手段としては、彼等を犬死させないためにも、憲兵隊に密告することも已むをえないと考えておりました。あるいは、そのために退学処分になる者も出るかもしれませんが、ここは私情を棄て『泣いて馬謖(ばしょく)を斬る』の非情も致し方ないと考えておりました……。新聞でチャップリンが来日することを知ったのは、将(まさ)にそんな時でした」
山内大尉はさらに訝(いぶか)しげに目を細め、田島を見つめた。
「つまり、きみが決断したのは、そのためだというのかな?」
田島はきっぱりと頷いた。