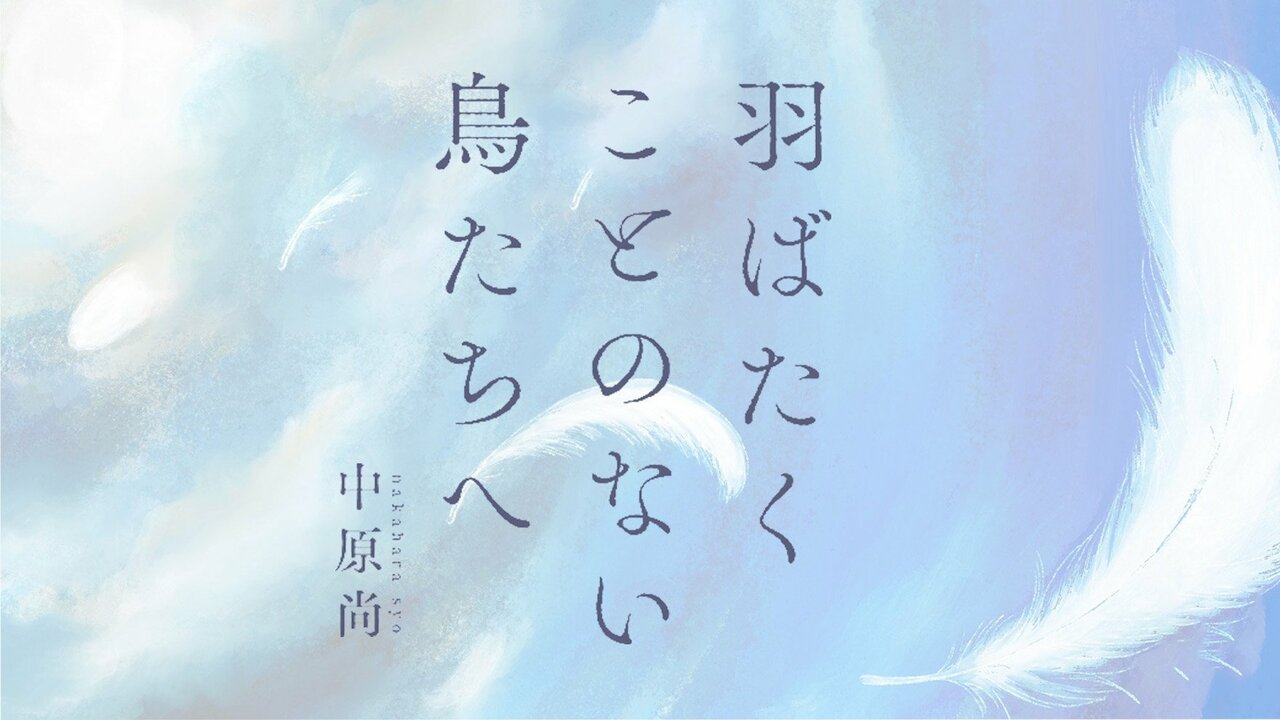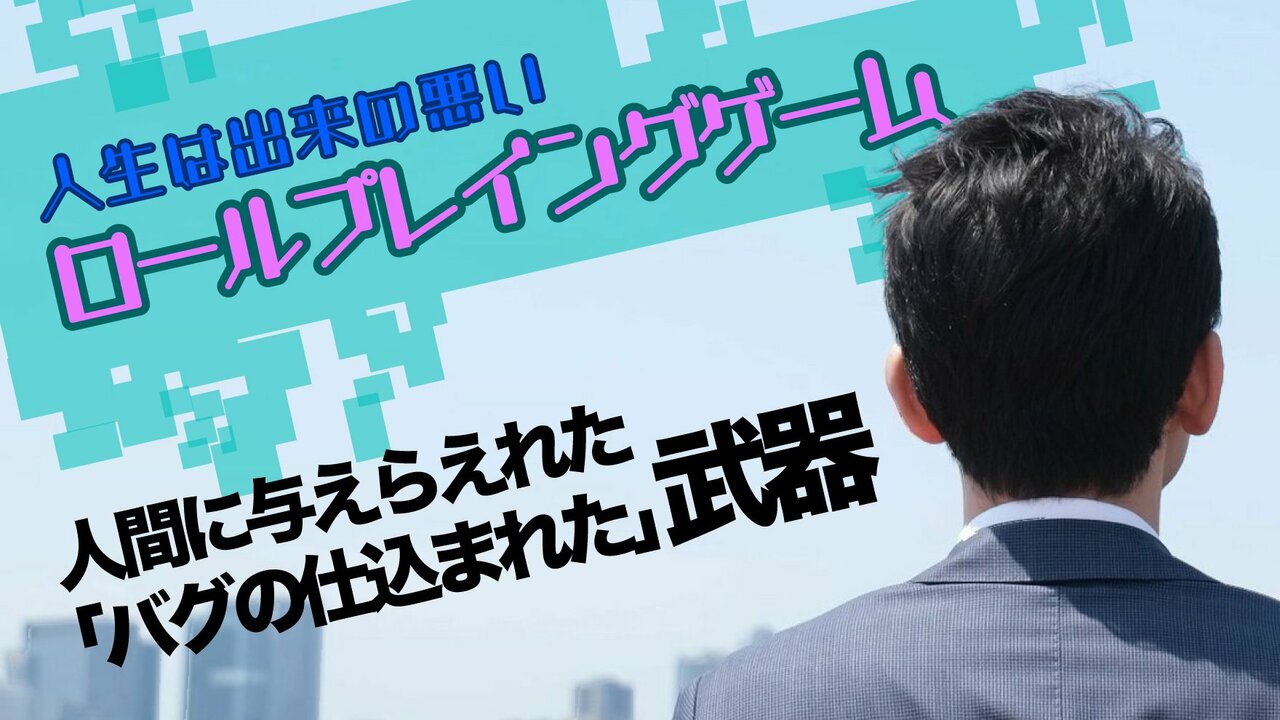六月二十八日(東京都杉並区)
不快な夢だった。
いったい、何にそのような不快を感じたのか。僕はそれを検証しようと試みた。だが、部屋に充満する蒸し風呂のような空気のせいか、まだ醒めやらぬ思考回路のせいか、夢のイメージは言語的に説明可能な形態をとる前に、触れた瞬間に溶け落ちる雪のように僕の認知様式の網からこぼれ落ちていった。あとに残ったのは、あれは不快な夢だった、と語る他に表現しようのない漠とした喪失感だけだった。
半日近く眠っていただろうか。頭が重い。日光に焼けた薄いカーテンの網目に濾過されて黄色く変色した太陽の光が部屋に染み込み、六畳一間の空間を橙色に染めている。もうだいぶ陽が高い。
仰向けのまま枕元に手を這わせてタバコを探ると、ティッシュに丸めて放ったままにしてあったコンドームに触れて、ベタリとした生温い感触が指先に走った。僕はそれをベッドから払い落とし、ライターとマルボロライトの箱を手に取った。理沙の姿はもう部屋には無く、化粧水の透明なガラス瓶だけが、テーブルの上で部屋の澱んだ光を鈍く反射させていた。
体重を少し傾けただけでギシギシと鳴く建て付けの悪いパイプベッドの縁に腰掛け、タバコに火を灯し、テレビをつけた。お昼のワイドショーが、先日起きた未解決の連続殺人事件をネタに、被害者の名前を連呼しながら、ああでもない、こうでもないとはしゃいでいる。今日も世界は平和らしい。