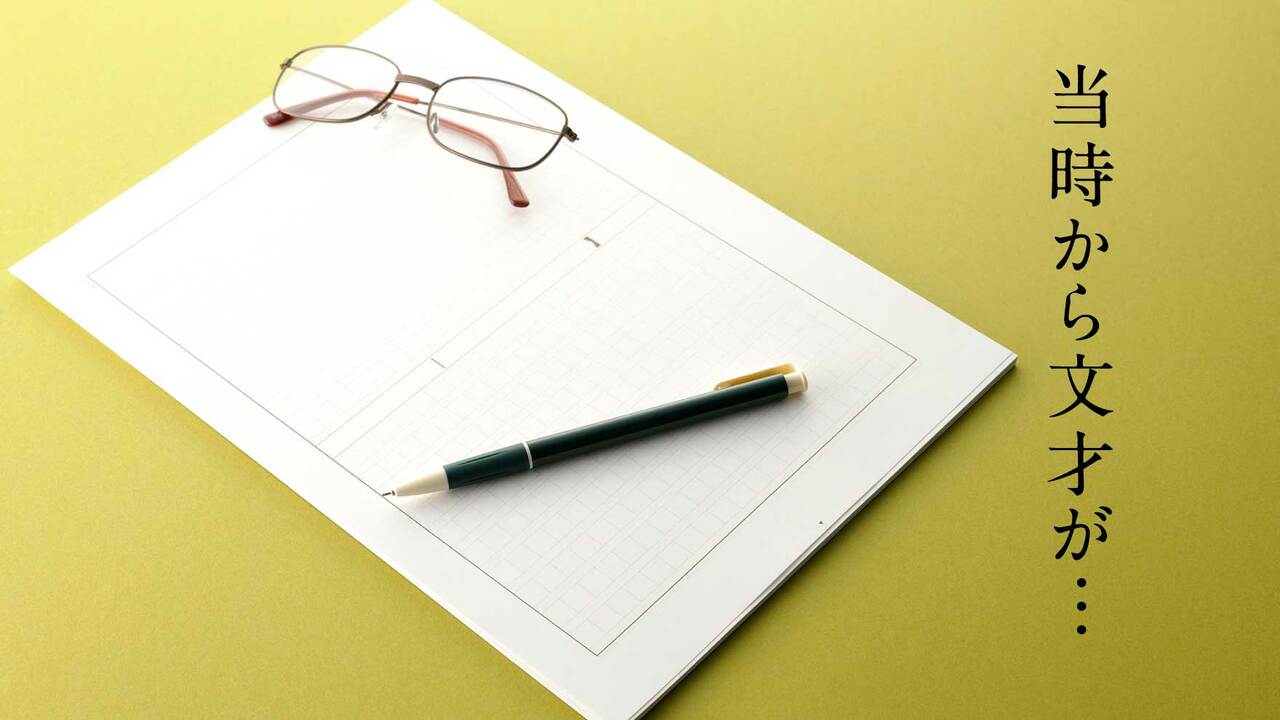プロローグ
一同がカクテル・ブレークを楽しんだらしいのを見回して、松野は気分を一新するかのように斉田の学友だという後藤沙織に顔を向けた。
「女性を後回しにして申し訳ありませんでした。後藤沙織さんは斉田さんと大学で同期だったとお聞きしていますが。あなたにも故人のエピソードを何か伺いたいのですが?」
「私は斎藤さんと(ごめんなさい、ペンネームよりも本名の方が言いやすいものですから……)大学の文芸部でご一緒した旧姓物集、今は後藤沙織という者です。私たち文芸部の仲間は卒業後皆散り散りになってしまって仕事もバラバラ、年賀状をやり取りしている人も数えるばかりになりました。
でも斎藤さんが著名な作家になられたお陰で皆あの頃のことを懐かしく振り返っていると思います。こんなウイルス騒ぎさえなければ文芸部のOB&OGで追悼会をしても結構集まって来たんじゃないでしょうか。本当に早過ぎる死です。残念でなりません」
「斉田さんはその頃から文才があったんですか?」
「もちろんです。しかも彼の凄いところは授業のレポートでも同人誌の短文でもああでもないこうでもないなんて苦しまずに魔法みたいにすっと書けたことです。書くスピードが凄かったわ。男の人たちは前の晩にコンパで飲みまくって大騒ぎして二日酔いで作文どころではなくても、あの人はけろっとした顔をして『はい、出来ました』でしょ? あの頃から文学部に面白い、凄い人がいるって評判だったわ。
そう言えばこんなことがあったのを思い出しました。一度文芸部の合宿で長野の大学のヒュッテに行ったことがあるの。男性が五人、女性が私を入れて七人。その時に猛烈な雨が降って更には夏だって言うのに夕方にはみぞれになって、私たち二晩足止めを食ったのよ。それで誰からともなくあのイギリスのバイロン卿のスイスの別荘での物語創り競争の真似みたいなことをしようって言いだしたんです」
――イギリスの詩人・バイロンは貴族の出身で裕福だった。彼のスイスのレマン湖畔の別荘で詩人のシェリーや急進的政治学者ウィリアム・ゴドウィンの娘メアリー・ゴドウィン(のちのメアリー・シェリー)など作家や詩人が集まって休暇を過ごし、怪奇譚を披露しあったことがあった。一八一六年、ディオダディ荘の怪奇談義と呼ばれる有名な出来事である。
「テーマは『妖怪』か何か、ホラーだったわ。誰かが風雨の吹きすさぶ暗くて寂しい山小屋にぴったりだって言い出してね。誰が一番怖い話を書くかって。だけど男の人たちは結局その夜も大酒を飲んで悪ふざけばかり言っていたからちゃんと書いた人がいたかどうか……。でも斎藤さんだけは朝になるとちゃんと出来ていたんです。どんな話だったかは忘れたけれど皆で投票したら斎藤さんのものが一等賞ってことになって」