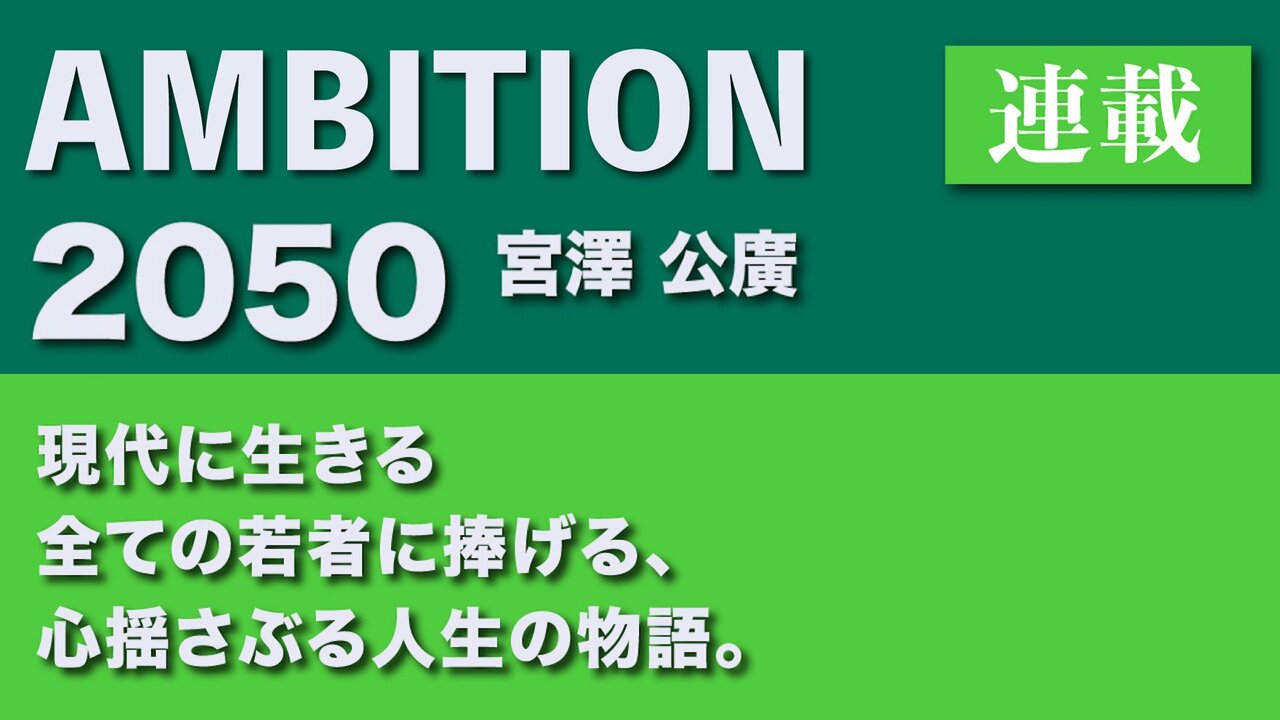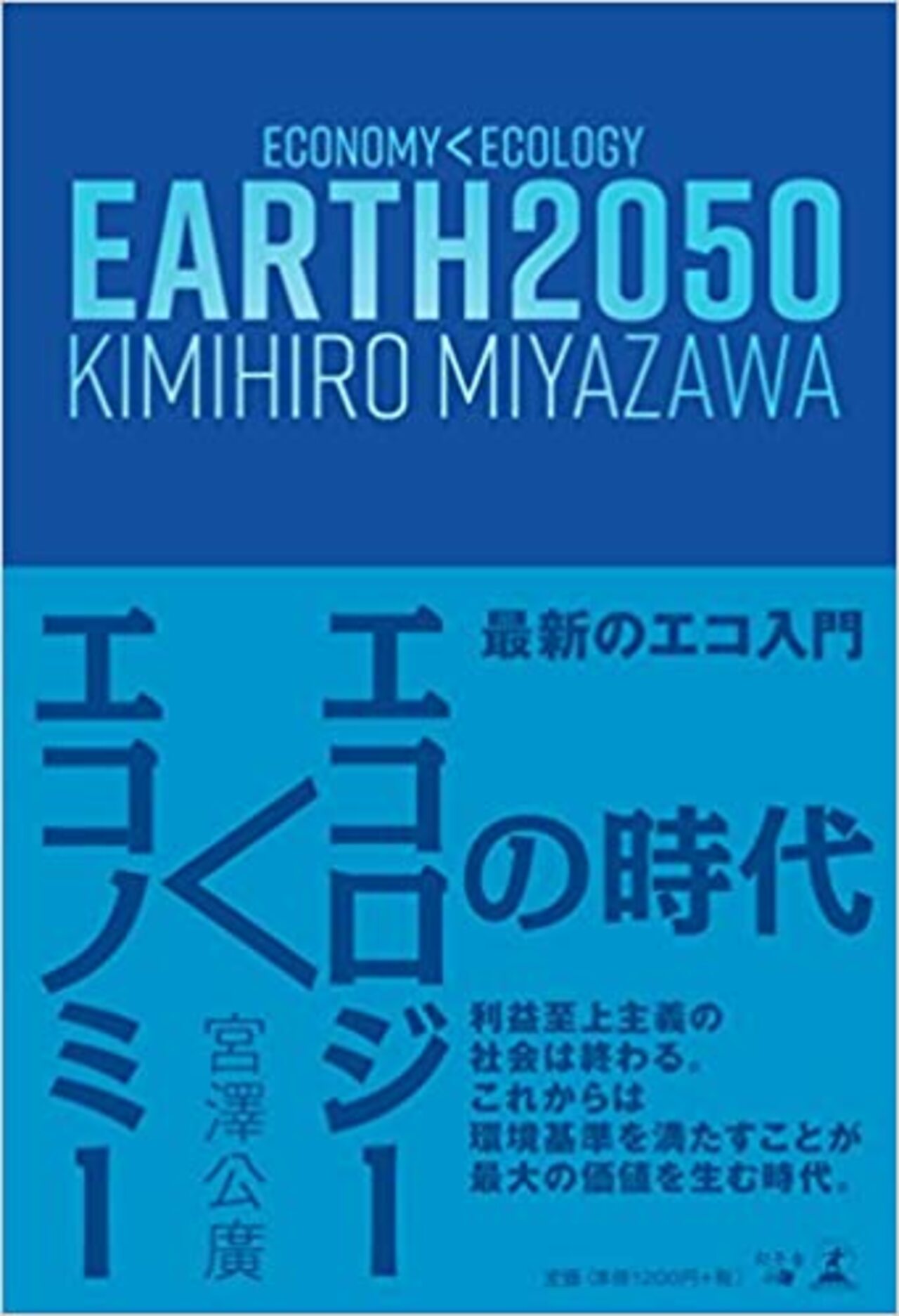第二章 奔走
【10】
その一報は、青天の霹靂だった。二〇〇五年六月、太陽新聞の一面に特大級のスクープが掲載された。北海道の食品加工業者であるキマラフーズが、牛や豚の安価な内臓などを配合したミンチ肉を、“牛肉百パーセント”と偽装していたことが明らかになったのだ。
朝四時に社会部デスクの鶴田から電話を受けた宮神は、寝間着のスウェット姿のままで自宅最寄りのコンビニに駆け込み、太陽新聞を購入した。白抜き文字の“牛ミンチ偽装 内部告発で発覚”の文字を読んだとたん、軽くめまいがした。いったいどういうことだ。消費者に直接被害を及ぼしていることを考えれば、快清食品の事件よりも悪質ではないか――。
一度自宅に戻った宮神は急いで着替え、マンションのある蔵前からタクシーに乗って銀座の本社を目指した。本社への異動を命じられたのは、二〇〇三年の秋だった。快清食品の事件をはじめとする一連の食品問題の調査報道を高く評価され、社会部の遊軍記者として招かれることになった。
本社勤務は、大半の記者が憧れるポジションである。宮神もご多分に漏れず、栄転の辞令によって仕事への自信を深めた。期待に応えるため、本社に異動になってからの宮神は、より一層、食品問題の調査に力を傾けていた。その仕事ぶりから、いつしか同業者からも食品問題のエキスパートと目されるようになっていた。
仕事に対する自信を深めていた宮神にとって、キマラフーズの食品偽装は寝耳に水以外の何物でもなかった。どうしてこんなにショックを受けているのだろう……。宮神は、タクシーの車中で心の整理を始めた。自分の手でスクープを書けなかったという悔しさは、もちろんある。
しかし、もっとも大きく心を占めているのは徒労感だった。快清食品の一件以降、食肉業界の膿を出し切ろうと、宮神は全国を駆け回って取材を続けた。結果、同様の偽装工作を行っていた企業を、次々と白日の下に晒した。HACCPの啓蒙にも宮神なりに全力を尽くした。その後、大きな事件がなかったことから、食品業界に自浄作用が働き始めたのかもしれないと、記者としての仕事に手応えを感じていた。
しかし、宮神の考えは甘かった。市井の人々の信頼よりも、利益の追求に重きを置く業者がまだいたのだ。宮神は自分でも驚くほど大きな舌打ちをした。そのせいか、バックミラー越しに運転手と視線が合い、気まずい思いを味わった。
「キマラフーズはとんでもないことをしでかしたな」
鶴田が顔をしかめながら言った。宮神は無言で頷いた。ユニオン通信の編集フロアは、蜂の巣をつついたような騒ぎになっていた。いつもならかすかに聞こえる首都高速道路を走る車の音も、今日に限ってはまったく聞こえなかった。
「これからどうやって動く?」
「とりあえず内情に詳しそうなネタ元に連絡を取って、立ち入り検査の時期を聞きます。結果もいち早く教えてもらえないか打診してみます」
「わかった。謝罪会見は別の人間に行かせるから、お前は自由に動け。あとは、牛肉の卸先の取材だな」
「記事によると、冷凍食品を扱う志村屋の食品に使用されていた疑いが強いとありました。誰かを行かせるといいかもしれません」
「よしきた。三沢に担当してもらう。進展があったら、逐一報告をしろよ」
「わかりました」
鶴田との打ち合わせが終わると、宮神は携帯電話の通話ボタンを押した。二度のコール音を経て、相手の声が聞こえてきた。
「久しぶりだな」
神戸時代に知り合った太陽新聞の青柳だった。青柳は、記者としての手腕を買われ、宮神より一年早く本社に異動していた。今朝の一面記事で青柳の署名を認めた宮神は、軽い嫉妬とともに、信頼のおける友人がスクープをものにしたことに、痛快さも感じていた。
「やられたよ。さすがだな」
「自分でネタを引いてきたわけじゃないさ。告発者が、長年うちの読者だったらしくてな」
「運も実力のうちだ。ほかの社には情報が漏れなかったのか?」
「じつはな、初めは地元の行政機関に持ち掛けたそうだが、断られたそうだ。告発者は、彼らが解決に向けて動いてくれれば実名を出さずに済むのにと、腹を立てていたよ」
「食の安心安全を守ろうと必死になっている役人は多いが、どうやら持ち込んだところが悪かったようだな」
「ああ。その後、地元紙とテレビ局にも話を持ち込んだが相手にされず、うちにお鉢が回って来たってわけさ」
「お題目と笑われるかもしれないが、報道機関の使命は権力の監視だろう? 志がなければこの仕事は務まらないぞ」
「俺も正直、がっくり来たよ。まあしかし、まずは目の前の仕事をやらないとな。落ち着いたら一杯やろうや」
「そうだな」
電話を切った宮神は、右手の人差し指と中指に挟んだ短い鉛筆を眺めた。先がすり減ってもうほとんど芯が残っていないそれは、記者としての情熱を失いかけている自分のようにも見えた。
立ち入り検査が行われたのは、太陽新聞によるスクープのあった二日後だった。知己の関係者の話によると、ミンチ肉には内臓だけでなく、パンや水までもが混入されていたという。宮神は、謝罪会見では明らかにされなかった事実を後追いでスクープし、太陽新聞への遅れを挽回した。
キマラフーズはすぐに事業の継続が難しくなり、七月には自己破産を申請した。十月になると、社長が不正競争防止法違反で逮捕され、騒動がすっかり収束した翌年三月、懲役四年の実刑判決が下った。
事件には一区切りがついたが、宮神の日常は否が応でも続いていく。札幌地方裁判所の傍聴席で判決を聞いた宮神は、ペンの力で不正を防げなかった自分が腹立たしく、無力感を拭えぬまま、地下鉄を使わずに歩いて札幌駅を目指した。