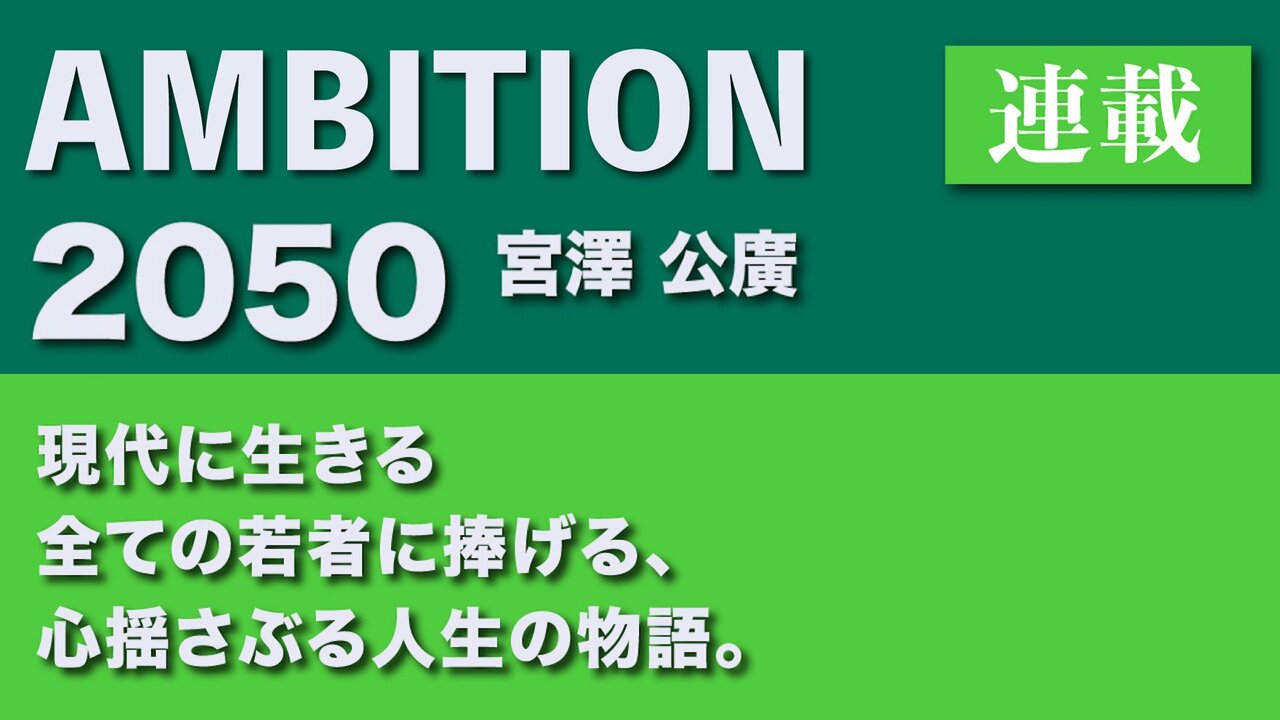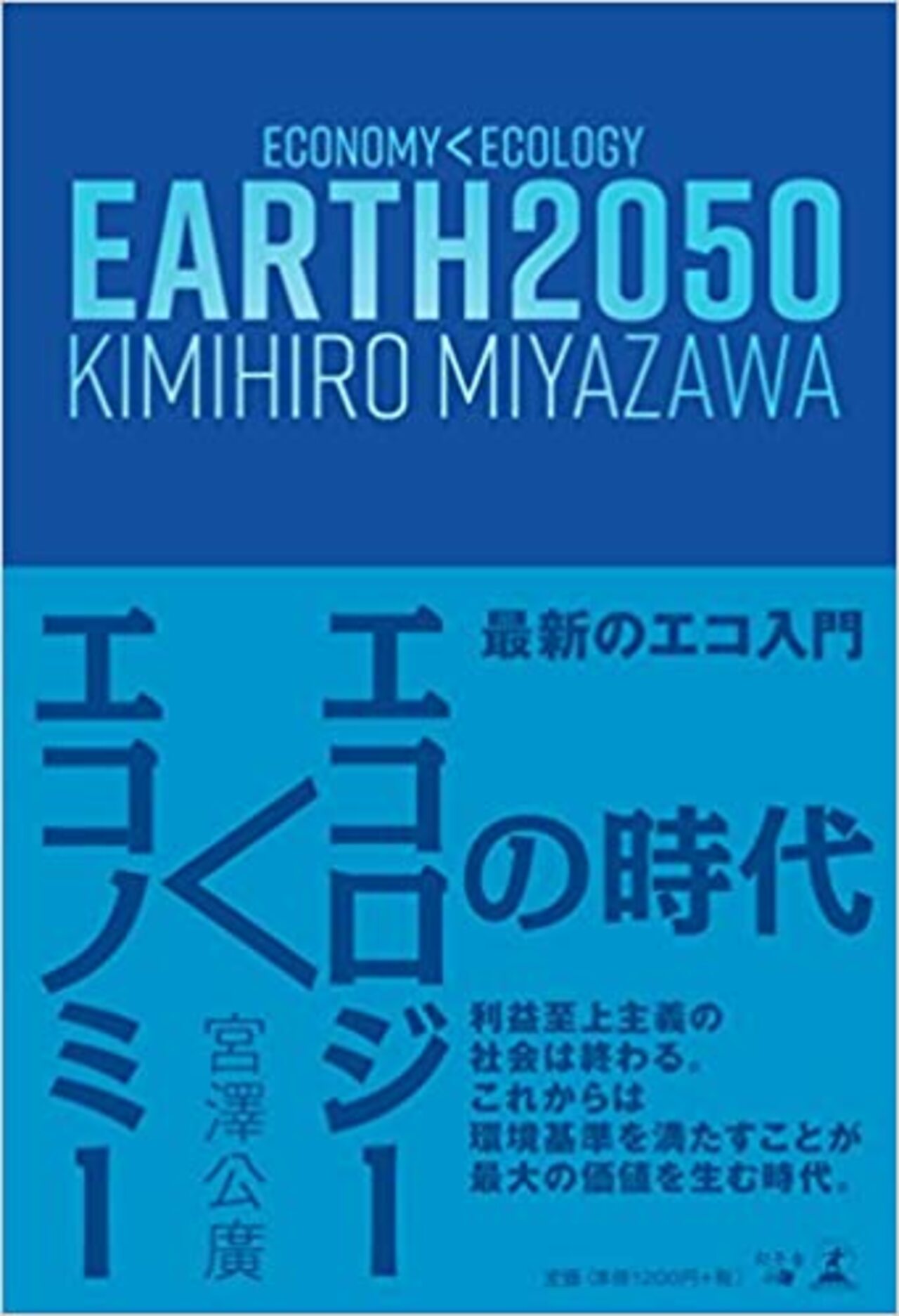第二章 奔走
【11】
「元気そうだな」
そういって、上杉は笑みを浮かべたまま握手を求めてきた。宮神も右手を差し出し、力強く握りしめた。それだけで、十数年の空白が埋まったように思えた。
しばしばメールで連絡を取り合っていたものの、実際に上杉と会うのは大学の卒業式以来だった。上杉は、宮神が卒業してからも大学に二年ほど在籍した。だが、米国旅行中に見学に行ったダニエル研究所で、天才学者にして実業家のダニエル教授にその才気を見いだされ、大学をあっさり中退した。
上杉にとって大学は、単なる通過点に過ぎなかった。社会に出れば大学で学んだことなど、ほとんど役に立たない。上杉はそのことを大学に入学したときから知っていたから、進級や卒業のために単位を取ることには、何の価値も見出さなかった。
その結果、今は世界のエリートが憧れるダニエル研究所に入所し、精力的に研究を行っている。キマラフーズ事件以来、仕事に行き詰まっていた宮神は、久しぶりに上杉と連絡を取って弱音を吐いた。すると、四月に出張で日本に行くから、食事でもしようという返信があったのだ。
ふたりは宮神の職場からほど近い新橋駅前のSL広場で待ち合わせた。気疲れしない赤提灯で飲みたいというのが上杉のリクエストだった。
「日比谷公園の桜が満開だぞ。花見でもするか」
「桜なんか見ても腹の足しにならん。花より団子だよ。早く飯を食おう」
宮神は同僚と行きつけにしているガード下の赤提灯に上杉を案内した。この店は、新鮮な魚を安価で提供しており、今日も混雑している。
「じゃあ、再会に乾杯!」
生ビールのジョッキを眼前に掲げ、互いにぶつけ合う。上杉はジョッキに口をつけるとあっという間に飲み干し、「くーっ、旨い!」といって膝を叩いた。ピッチが早いのは、昔から変わっていない。
近況を語り合い、新鮮な魚料理を味わいながら、次々に杯を干していった。上杉は日本酒を豪快に飲みながら、ダニエル研究所における仕事について、ユーモラスに説明してくれた。
「仕事、楽しそうだな」
「忘れたか? 俺は楽しめないことはやらない主義だ。そっちはどうなんだ?」
「記者はそもそも楽しいという職業ではないが、やりがいはある。ただな、ずっとこの仕事に誇りを持っていたけど、最近はどうも虚しくてなあ。ペンは無力だよ」
いつの間にか宮神は、仕事の悩みを上杉に打ち明けていた。
「弱音を吐くなんて、お前らしくないな」
「一連の食品偽装事件のことは、上杉も知っているだろう?」
「まあな」
「俺は、長年食品の安全について調査報道を続けてきたんだ。食品偽装なんか続けていたら、国民の信頼を失うぞと警鐘を鳴らし続けてきた。それでも、食肉業界の隠蔽体質は一向に改善しない。俺に記者としてできることは、もうないのかもしれん」
宮神はそう言って焼酎を呷った。上杉は「思案どころか」と笑ってから、意外な話題について切り出した。
「しかし、ここはいい店だな。俺を海鮮居酒屋に誘ってくれたのは、何か理由があるのか」
「いや、ただの気分だな。焼き鳥でも食いたかったか」
「逆だよ。焼き鳥やモツ焼きの店に連れていかれそうになったら、申し訳ないが寿司でも提案しようと思ってたんだ」
「肉がダメになったのか。ということは、何か病気か」
「違うよ」
上杉はそういって笑った。
「じつはな、俺はアメリカに行ってからベジタリアンになったんだ。といっても、魚や乳製品はたまに食べる。いわゆるペスクタリアンってやつだな」
「聞いたことはある。でもまたどうして?」
「今、世界の人口は六十五億人だ。あと数年で七十億人を超す見込みなのは知っているよな」
「ああ」
「じゃあ、世界の家畜の数は知っているか」
「いや、知らない。教えてくれ」
「七百億。人間の十倍だ。ダニエル研究所で調べたデータによれば、七十億の人間は、一日に百九十七億リットルの水と、九百五十万トンの食料を必要とする。そして家畜は、七百億頭のうち、たった二パーセントの牛だけで、一日に千七百億リットルの水と、六千万トンの食料を食べている」
「たった二パーセントの家畜でそれだけの量が必要なのか」
「ああ、そうなんだ。家畜がそれだけの食料を必要とする一方、十億人の人間は飢えで苦しんでいる。要するに、家畜が消費する膨大な量の穀物を人間に回せば、飢餓の問題は解決できるんだ。それに、人間が肉や卵、乳製品の摂取を減らすことができれば、家畜の飼料用の畑を自然に戻せる。その自然に野生動物の生態系が戻れば、地球温暖化も食い止められるはずだ」
「なるほどな」
「まだある。食肉をやめれば、がんや脳卒中、心臓病や糖尿病のリスクを低減できるというデータもあるぞ。そのうえ、俺は今、大型犬と暮らしていてな。犬は可愛がるのにどうして家畜を食べているのかと自問し続けた結果、陸生動物を食べないことに決めたんだ」