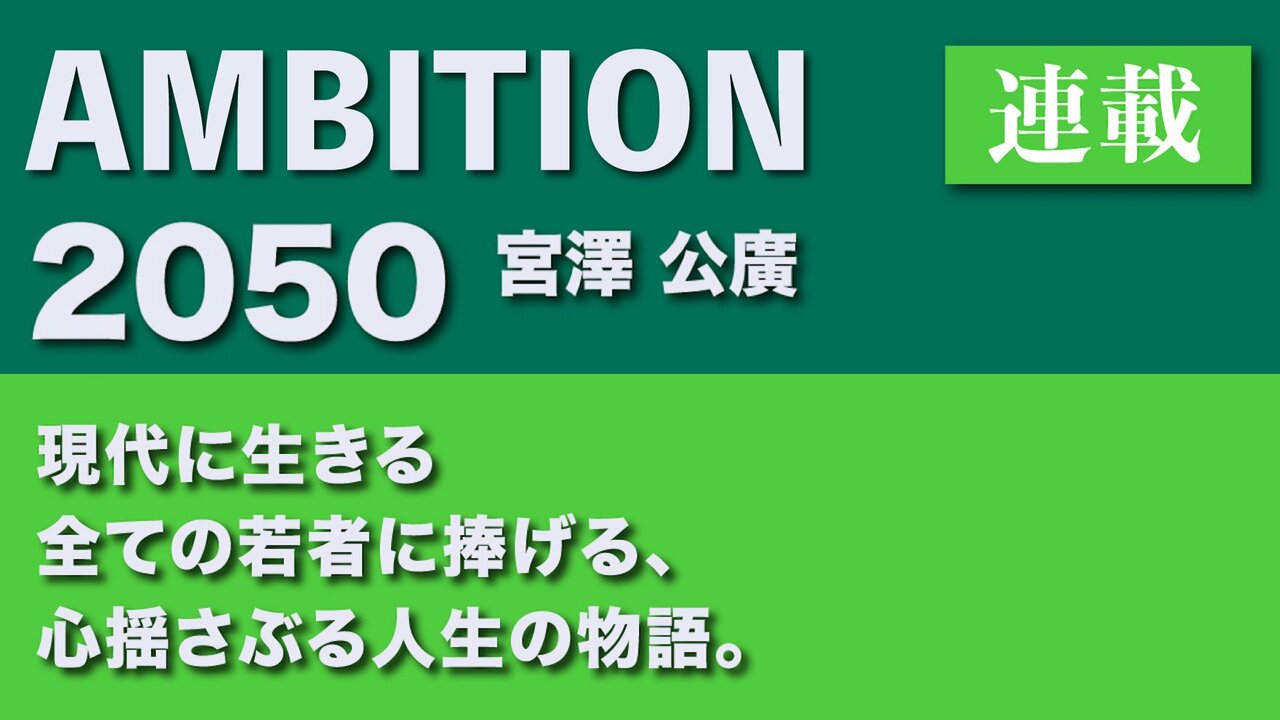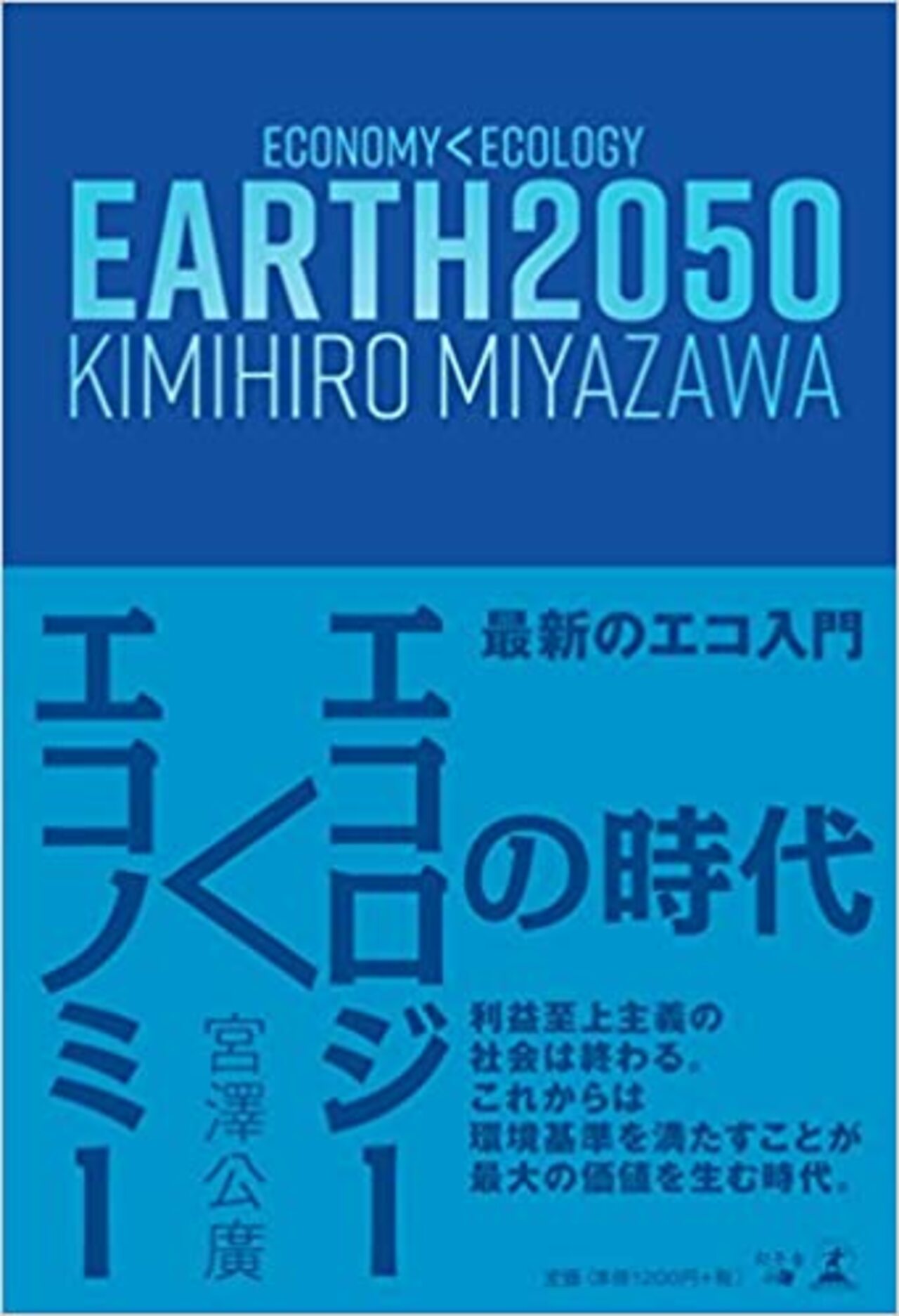第二章 奔走
【6】
宇都宮支局に勤務して二年目の夏、宮神は県北部のとある町で、永禄の時代より続く夏祭りの取材をすることになった。この祭りで最も注目されているのは、市街地に設置された舞台で行われる野外劇だ。伝統的な所作狂言は重要無形民俗文化財に指定されており、県内はもちろん、県外からも多くの観光客が訪れる。
祭りの中日となる二日目の午後、宮神は焼けつくような陽射しを避けるために神社の木陰で涼をとっていた。近くには法被姿の男衆がたむろし、めいめいに世間話をしている。聞くともなしに耳を傾けていると、白髪を短く刈り込んだ還暦ほどの男性の声が耳に飛び込んで来た。
「ここ二、三日、水道水がくさくてよ。俺もおっかあも怖くて飲んでねえんだ」
夏場に水道水から匂いがするという話はよくあることだ。湿度が高い時期に湖沼やダムに藻が大量発生するとカビくさく感じるようだが、飲料水として問題はなかったはずだ。宮神は、少し離れた場所で話を聞き流した。
それでも何かが引っかかっていたのか、取材後、支局に戻った宮神はデスクの秋山に報告した。頭上で両手を組み、少し考え込むような素振りを見せた秋山は、「その男は水道水がカビくさいって言ってたのか」と、質問してきた。
「そういえば、どんな匂いがするかまでは話していませんでした」
「何やってんだ!」秋山の雷が落ちた。
「物事を憶測で決めつけるな! 祭りは明日が最終日だろう? もう一回行って、その男を見つけてこい!」
毎度のことながら、秋山にみっちり絞られるのは精神的に堪える。帰宅後、宮神は普段より一本多く缶ビールを空け、酔いに苛立ちを紛らわせた。
翌日、昼過ぎから現場に入った宮神は、祭囃子で賑わう雑踏の中を歩き回った。運良く昨日の男性を見つけたのは、午後二時を過ぎる頃だった。
声をかけた直後は怪訝な顔を見せた男性だったが、名刺を手渡すと「なんだ、記者さんか」と安心してくれた。男は青木という名前だった。宮神は盗み聞きしたことを詫びつつ、詳しい話を聞かせてほしいと頼み、その流れで男性の自宅を訪れた。
キッチンの流し台で水道の蛇口をひねると、何とも言えないケミカルな匂いが鼻腔を刺激した。
「水道局には連絡しましたか?」
「してねえ。この辺りは東京の宅地開発業者が開発した土地だから、私設水道だ。要するに水道局が引いている水道じゃねえから、行政の管轄外なんだよ。水源は裏山に業者が掘った井戸で、ポンプで汲み上げて各戸に供給してるんだ。業者には水を調べてくれって何度か電話したんだけど、一向に進展がねえな」
「ご近所の方たちとは話しました?」
「ああ、みんな困ってるよ。近くに産廃の処理場があっから、どうしても良くねえことを考えちまう。ただ、ここ何日かは稼働していねえみてえだな。いつもは何やらガチャガチャうるせえのに、物音ひとつしねえんだ」
夏型の気圧配置が連日続いているせいで、雲ひとつない晴天だった。宮神はハンカチで汗を拭いながら商店街まで歩き、公衆電話から秋山に取材結果を報告した。すると、「デベロッパーのペリアス環境開発は本社の知り合いに調べさせる。お前は産廃業者を徹底的に洗え」と、有無を言わせぬ口調で指示された。
諏訪間商会という産廃処理施設は、青木の自宅から徒歩で十五分、鬼怒川沿いの場所にあった。一面に田園が広がる風光明媚な地域だけに、スクラップ置き場が景観を損ねているのは一目瞭然だ。広大な敷地内に足を踏み入れ、事務所らしき平屋の建物を目指す。
両開きの玄関ドアを何度もノックするが、一向に返事はない。窓から内部の様子を覗くものの電気はついておらず、薄暗い空間に人のいる気配は感じられない。諏訪間商会はすでに、この地から逃げ去ってしまったのではないだろうか。宮神は妙な胸騒ぎを抱えたまま、社用車を駆って田園地帯を貫く県道をひた走った。