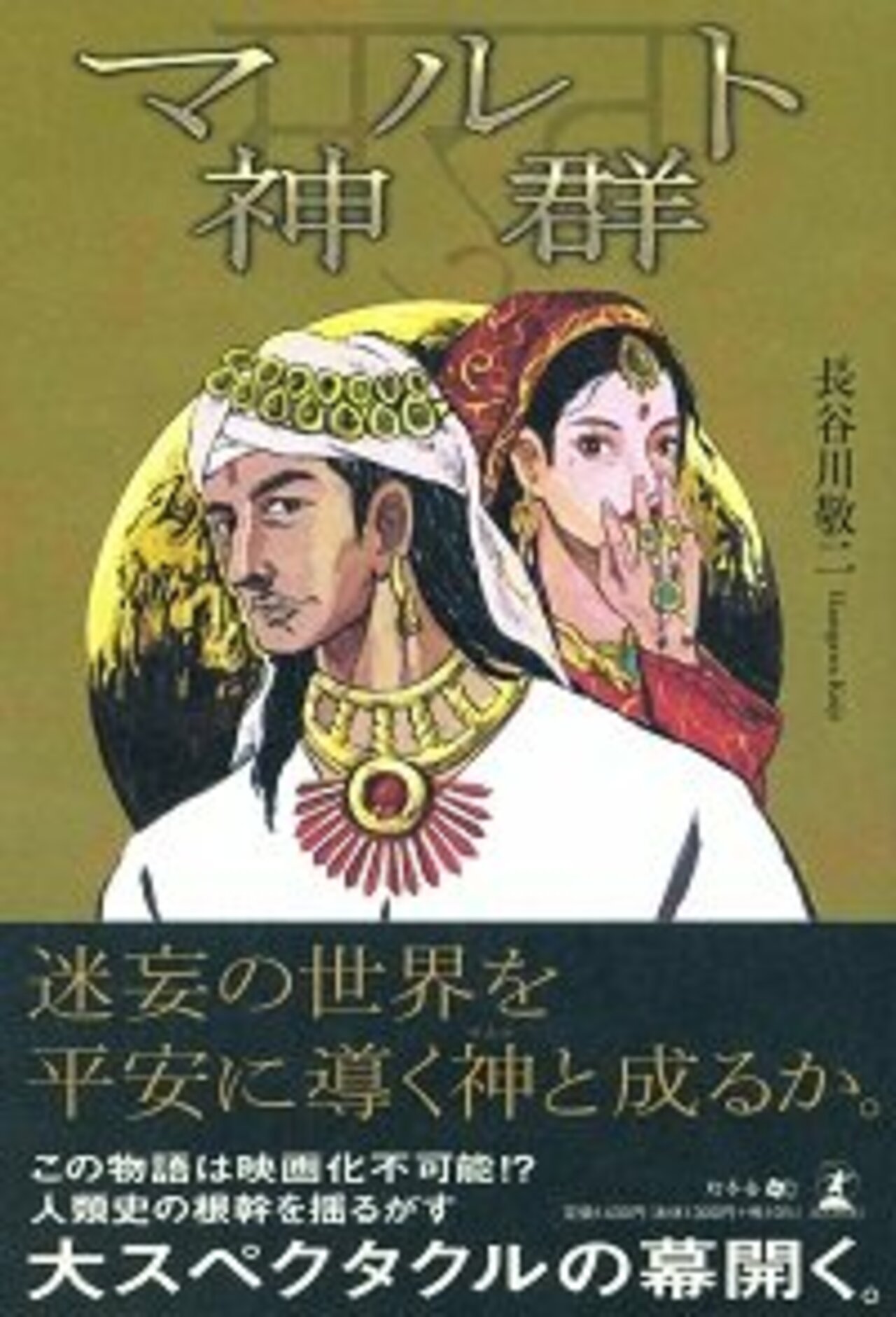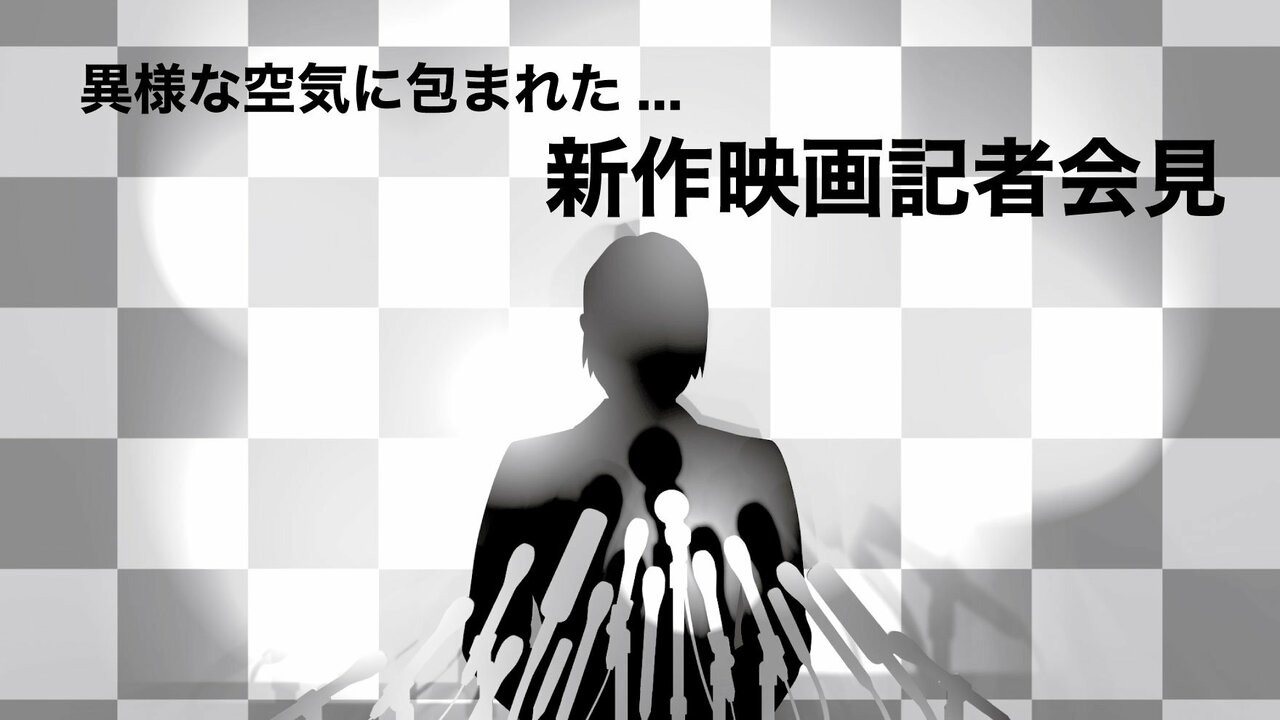私はその前にやっておかなければならないことが生じた。あの有名な放送局からの依頼だった。婆須槃頭の特番を組むのだという。その司会とナレーションをやってほしいのだという。私は承諾した。どうやらインドでのこと、「マルト神群」の上映に駆けずり回ったことなどが考慮されたらしい。
私は打ち合わせに放送局に出向いた。プロデューサーは秋山孝志というまだ若い男だった。私は彼とずいぶん話し込んだ。秋山は映画「マルト神群」の感想をこう述べた。
「インド映画の範疇を大きく逸脱していますね。とにかく今まで観てきた楽天的でコミカルなインド映画とは全く違う。神話でもって西洋世界の概念、大枠を大きく踏み越え、足蹴にしているようにさえ感じる、とてつもなくてとんでもない作品です。一番気になったのが悪魔に扮したマルトとキリストとの新約聖書マタイ伝第四章で有名な荒野の対話シーンです。あれはキリストを神格化するための出来レースだったというのが主旨のようですが、西洋人としては我慢がならないでしょう。そこまで踏み込む必要はあったのでしょうか」
私も同感だった。あれは一線を超えた、というべきものではなく、涯鷗州も婆須槃頭も地雷を踏んでしまったか、というのが正直な気持ちだった。(人はパンのみにて生きるものにあらず。神の口より出ずる言葉によって生きるものなり)キリストは、悪魔の、石をパンに変えてみたらの誘惑にこう答える。実際はこれはキリストの言葉ではなく、旧約聖書の申命記に記されてある文言である。それをキリストは引用した。悪魔の企みを一蹴したのである。
悪魔の荒野での誘惑は続く。婆須槃頭は悪魔を演ずるにあたり巨大化した猛獣をモチーフにしたと思われるが、それはイエス・キリストを小脇に抱きかかえて、高見の場所やエルサレムの宮の頂に運び込む際に効果を出している。その圧倒的な巨大性は悪魔のしたたかさを表出するのに実に効果的だ。
しかし、映画は裏話としてマルト神群の一つの狂気じみた芝居性をすでに明かしてしまっている。イエスの神格化を図らんがための狂言を画策し、実行したまでである。イエスもそれを承知で乗ってしまっている。(神を試してはならない)と、悪魔の誘いをすべて拒絶する。これもあらかじめ出来上がっていたストーリーだということになる。
これではキリスト教社会は、秘事をばらされたようでたまったものではなかろう。インド神話世界から見た一神教世界とはかくもおぞましいものか、と涯監督は嘆息しているかのようである。
しかし、私は危惧してしまった。このようなことをしてキリスト教社会から報復は受けないのであろうか。また反面、よくぞ映画の特性を使ってここまで描き切れたものだと感心もした。
いずれにせよ、マルト達はキリスト教世界にも大きく足跡を示しえたのである。