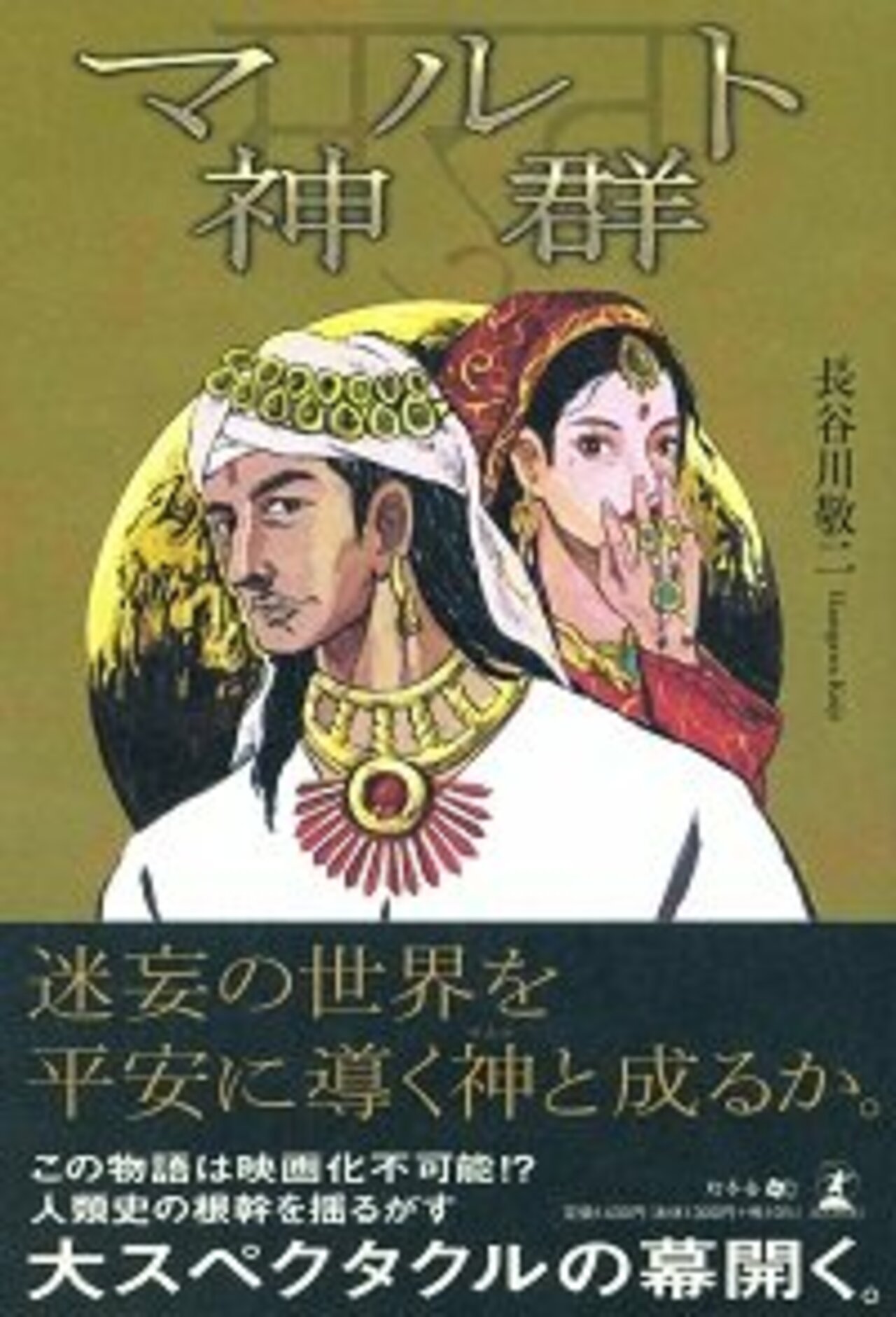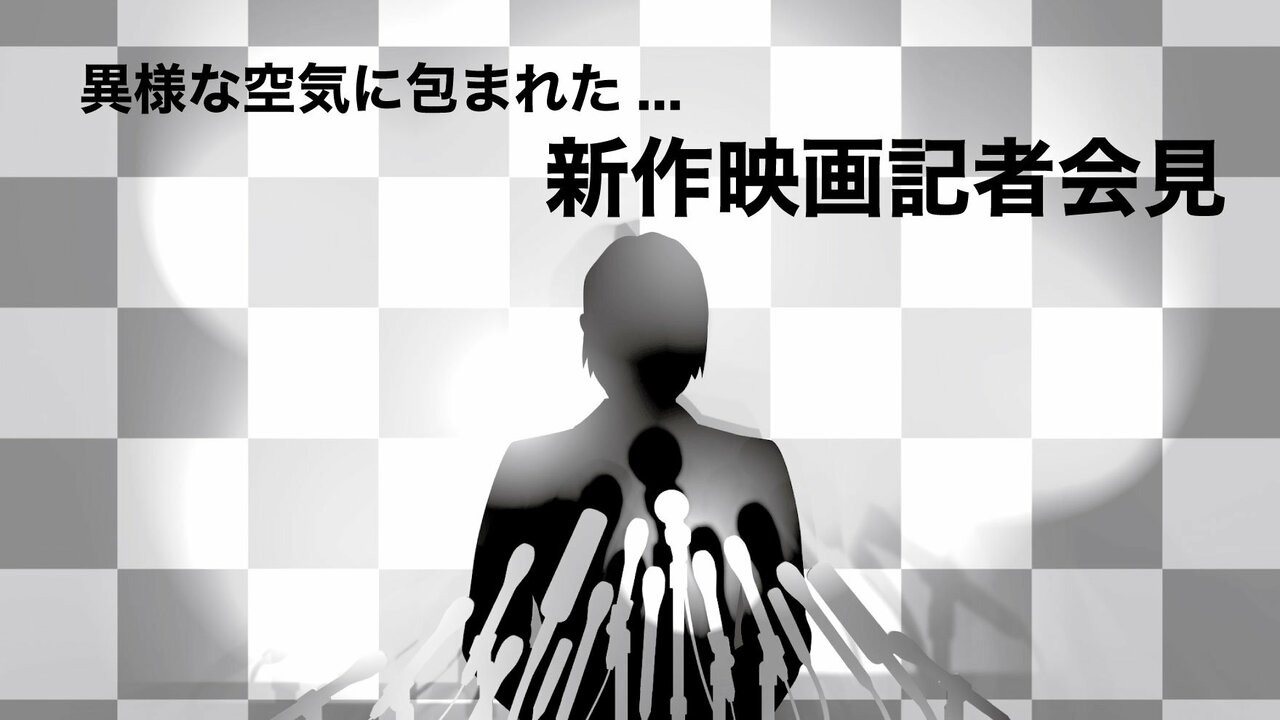【前回の記事を読む】地雷を踏んだ映画…「キリスト教社会から報復は受けないのか」
新藤由美子が映画の道に進んだ理由
秋山プロデューサーはまたこうも言った、
「監督の涯鷗州さんですが、あの人はインド神話を見事自家薬籠中の物にしましたね。それはいいのですが一つ困ったことが。というのはインド映画を作り上げるのにアメリカ資本と技術提携などをしたことです。それによってアメリカ映画の勢力がインドを席捲しそうになるという代償が生じますが、彼はそれを予想しなかったのでしょうか。いずれにせよ禍根を残しましたね」
私はこれに反発した。
「そうかもしれないが。こうも言えるのではないでしょうか。逆にインド映画がこれを機に、アメリカ資本を丸のみにして世界進出を図る良いチャンスができたのではと。インド映画の世界流布はこれを機に活発化していくことでしょう」
秋山プロデューサーはかすかに微笑んでこう言った。
「笹野さん。私は全共闘世代の最後の生き残りです。あなたにも経験がおありでしょうが、私は若いみぎり、とにかく反米、反米で過ごしてきました。その気持ちはかすかではありますが今でも残っています。
私は私の生まれる前、一九六九年五月十三日の東大で行われた東大全共闘と作家三島由紀夫との討論会を先輩諸氏から聞いたことがあります。あの時三島は単独で敵の懐に飛び込んできた。楯の会を結成してから一年余り、「祖国防衛」の三島の信念は日を追って強まり、そして翌一九七〇年十一月の三島事件です。
翌年に楯の会は解散して会員たちはその片鱗も消し去って雲散霧消状態です。しかし、三島はとにかく東大に単独で乗り込んできた。楯の会のボディガードはあってもなきが如しだったし、駒場九〇〇番教室の千人近い全共闘の学生は、数を頼んで押しつぶしにも懸れなかった。とにかく三島一人の気迫と頭脳とスター性に圧倒されっぱなしだったと聞いています。
同じ年の一月本郷の安田講堂の活動学生の立てこもりが警察機動隊によって強制排除されますが、その件も討論に出てきました。三島はこう言いました。
(あの時安田講堂のてっぺんから飛び降りて自殺をする奴は一人もいなかった。所詮ままごとだった。堂々と心置きなく革命に命を懸けるやつはいなかったのか。私は君たちの熱情は肯定するのに)
(君たちの中に一人でも天皇万歳と叫ぶ者がいたとしたら、私は喜んで君たちと手を取り合って行動を起こすだろう)
常日頃から天皇制粉砕を叫んでいた私たちにこの言葉はこたえました。三島由紀夫の説く天皇とは、天皇制という打倒されうるような具体性をもつものではなかった。それは日本の文化、伝統、よすがの支えとしての、芯としての、媒体としての存在だった。そこが今になってやっと解りだしたのです。