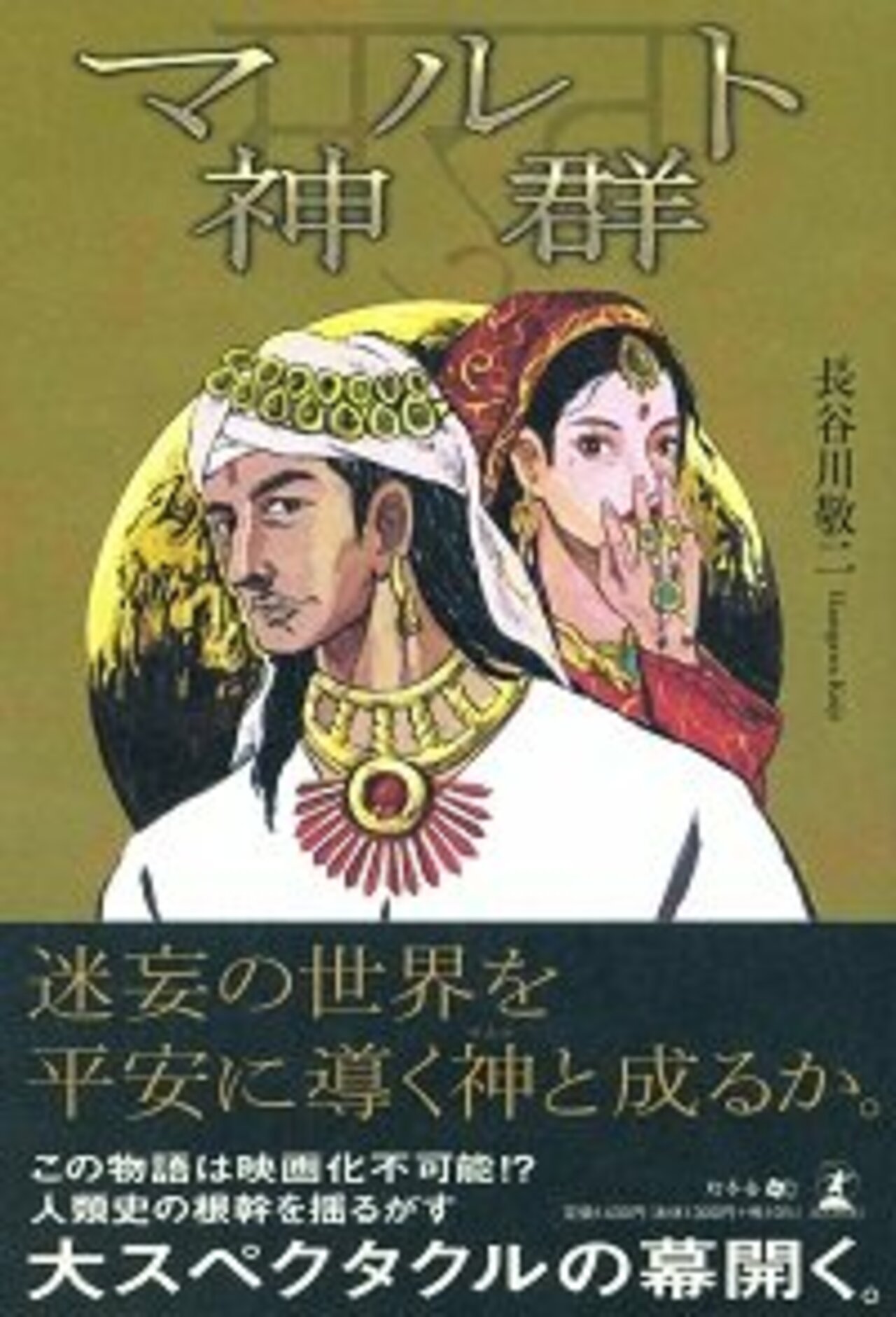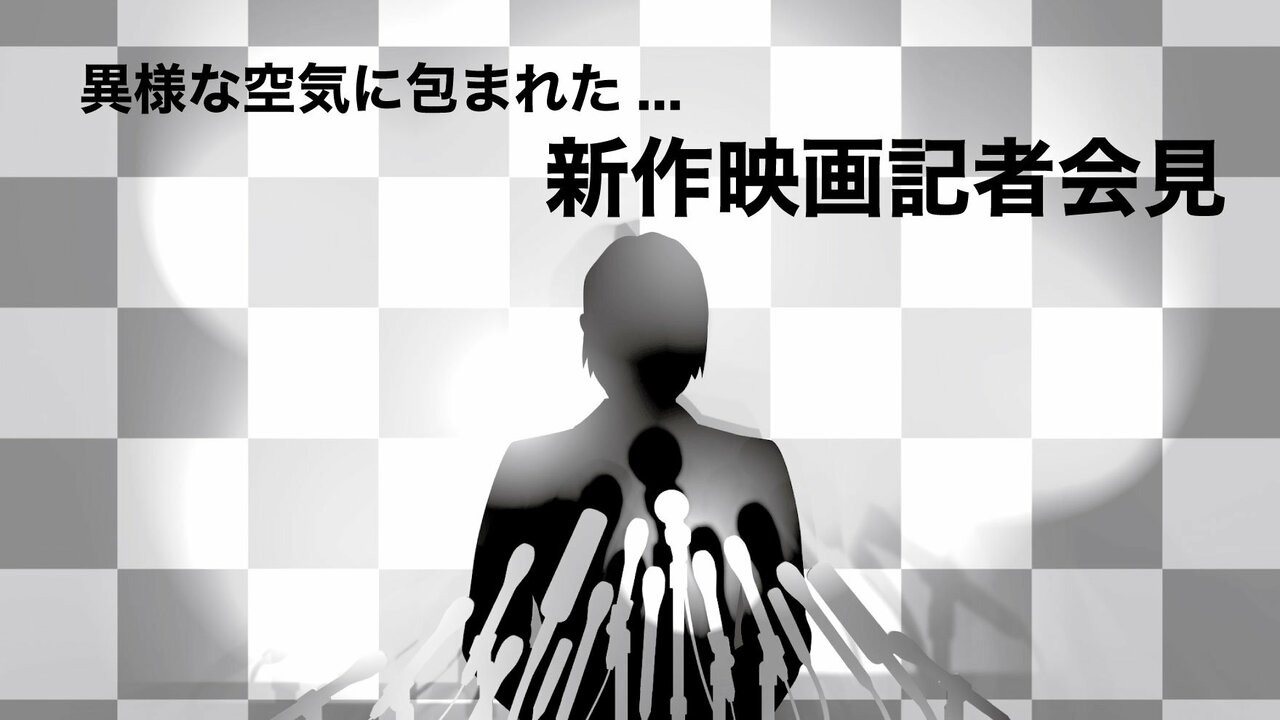第一章 宇宙開闢の歌
その男は自らを日本人とは名乗らなかった。
インド、コルカタの映画撮影所で出会ったその男について、笹野の直感は日本人だと確信しかかっていたのに、別の感覚が彼に躊躇することを強いていた。
身長は優に一九〇センチを超えている。浅黒いと言って良い肌は日焼けしただけではなく、もともとがそうなのか、周囲のインド人と比べてもさして違和感はない。
どのような鍛錬でもって鍛えられたのか、分厚い胸周りと、今にも頭上から振り下ろされんばかりの太い腕(かいな)がまず目を引いた。
体重だって百キロ以上あることは間違いない。容貌、これが笹野にとって、どう表現していいか一番憚(はばか)られるのだが、周囲のインド人たちと決定的に違うのは、険しさというものがすこぶる稀薄なのである。
インド人、特に若い男女によく見られる大きな眼(まなこ)で相手を見据える時の、あの眼光の鋭さはこの男からはさほど感じられない。眼光鋭いというよりも、何か途方もなく遠くのものを見据えているといった眼差(まなざ)しなのだ。
鼻梁(びりょう)と耳殻(じかく)はぎっしりとしたボリュームを湛え、その形体はインド人に近いものがある。そう厚くもない唇はしっかと閉じられてはいるが、その両端はやや吊り上がっていて、第三者に警戒感をいだかせない印象を与えている。
何よりも笹野を戸惑わせたのはその男の容姿にコーカソイド(白色人種)の痕跡(こんせき)を見出したからだ。
(白人との混血……)
年の頃は、二十代後半位だと見て取れた。
同行の記者内山が重ねて日本語で訊いた。
「あなたがこの映画の主人公ですね」
「………」
男は無言である。さらに質問してみる。
「この映画の撮影はいつから始まったのですか」
「……それは監督に聞いてくれ。撮影の邪魔でないときにな」
男の最初の声がこれだった。太い低音(バス)でやや控えめながら明瞭な日本語だった。男の視線は言葉を発した時、しかと内山を見据えていた。少しのやましさも、ひがみもない目だった。
頭上から降りかかってくるような声に幾分怯みそうになりながら、内山が男の扮装を見て尋ねた。
「古代のインドの衣装のようですが」
「古代のでも、インドのものでもないと言っておこう。通年(つうねん)のいで立ちだよ。もっとも人間の着る衣装じゃないがね」
虚を衝かれたかの様に内山が黙りこくった。通年という言葉が出たことで、笹野はこの男が日本で長く暮らしたことのあるまぎれもない日本人であることを確信した。しかし、人間の着る衣装ではないとはどういうことなのだろう。
長い髪の一部を束ねて頭上に置き、それを被り物が覆っている。残りの髪は肩まで無造作に垂らしている。腕輪、イヤリング、足首の輪、それに胸背部を覆い尽くす甲冑まですべてが黄金色である。
それらすべてはインド神話に出てくる神々の衣装とでもいうべきなのだろうか。