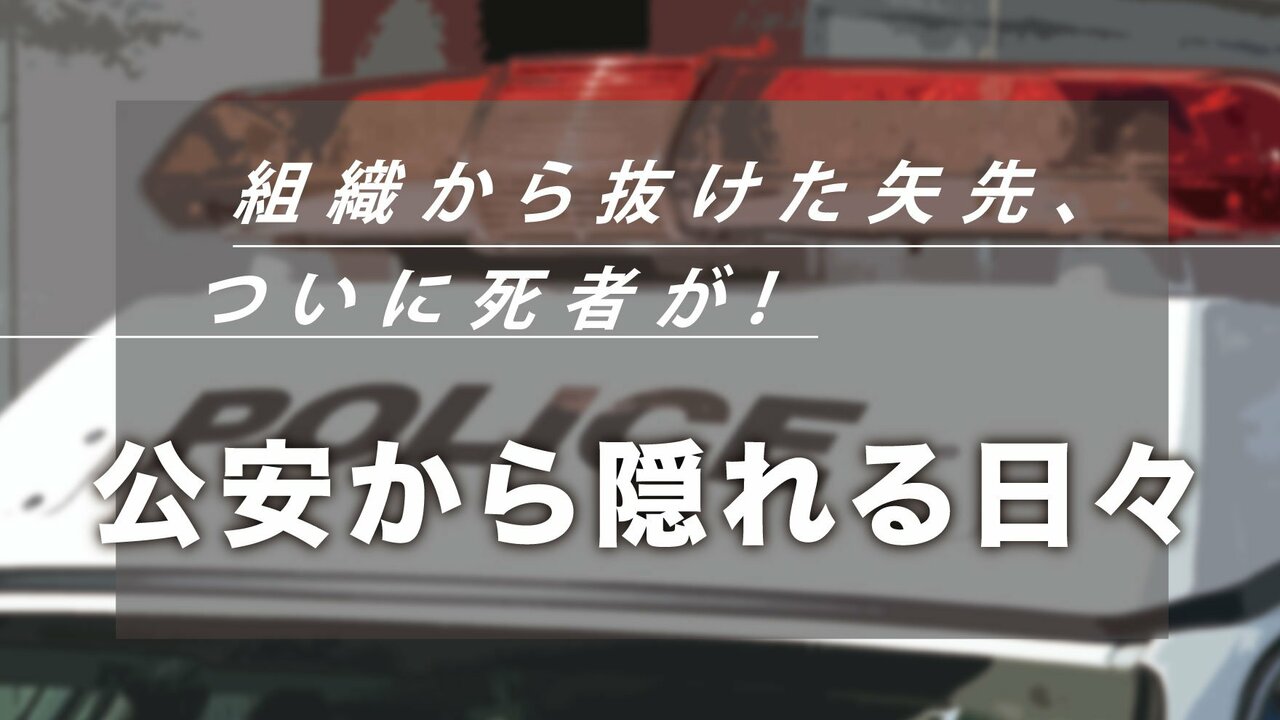私は彼女の言葉を聞きながら、ただ黙って肯くしかなかった。それでも、動物の檻に入れられるような恐怖が残った。
閉塞された集団が死へと追い詰められたなら、人間性を失うのはむしろ当然のことに思われた。
施設のスタッフに促されて、古い階段を軋ませて、二階のミーティング場に上がると、十数人のメンバーに紹介された。彼らは笑顔と拍手で私を迎え入れてくれた。私はそれをも不思議な気持ちで受け止めた。
なぜなら、私は久しく孤独の中で生きてきて、人間扱いされたことも、仲間扱いされたこともなかったからだった。
しかし、確かに、彼らは私と同じ病を患った同じ仲間たちであり、同じように世間から見捨てられた同じ仲間たちだった。私はそんな彼らにやっと共感らしきものを覚えて、安堵したのだった。
勿論、施設の生活は辛いものだった。ここでは自分の考えを使ってはならないという。ここは鉄格子のない刑務所だったのだ。
それでも、皆が絶望を背負いながら、互いに笑い合っているようなところがあった。皆が自分の死を前にして、仲間たちと何かを共有しようとしていた。
といっても、中にはやはり意地の悪い、変質者のような人もいて、人を攻撃しようと目を光らせていた。ここは人間の光明面と暗黒面とが、ないまぜになった矛盾の場でもあったのだ。
それでもなお、ここで生き抜いていくためには、自分を超えた永遠的なものを信じて、無になりきって行動していくことが必要だった。それが真の自分を取り戻すという回復でもあるだろう。
光と影のはざまで、病の苦しさに喘ぎながら、仲間たちと共にしたここでの生活を、いつかは懐かしく思い出す時もくるだろう。
その時のくることを祈りながら、今日一日をひたすらここに生きるしかなかった。