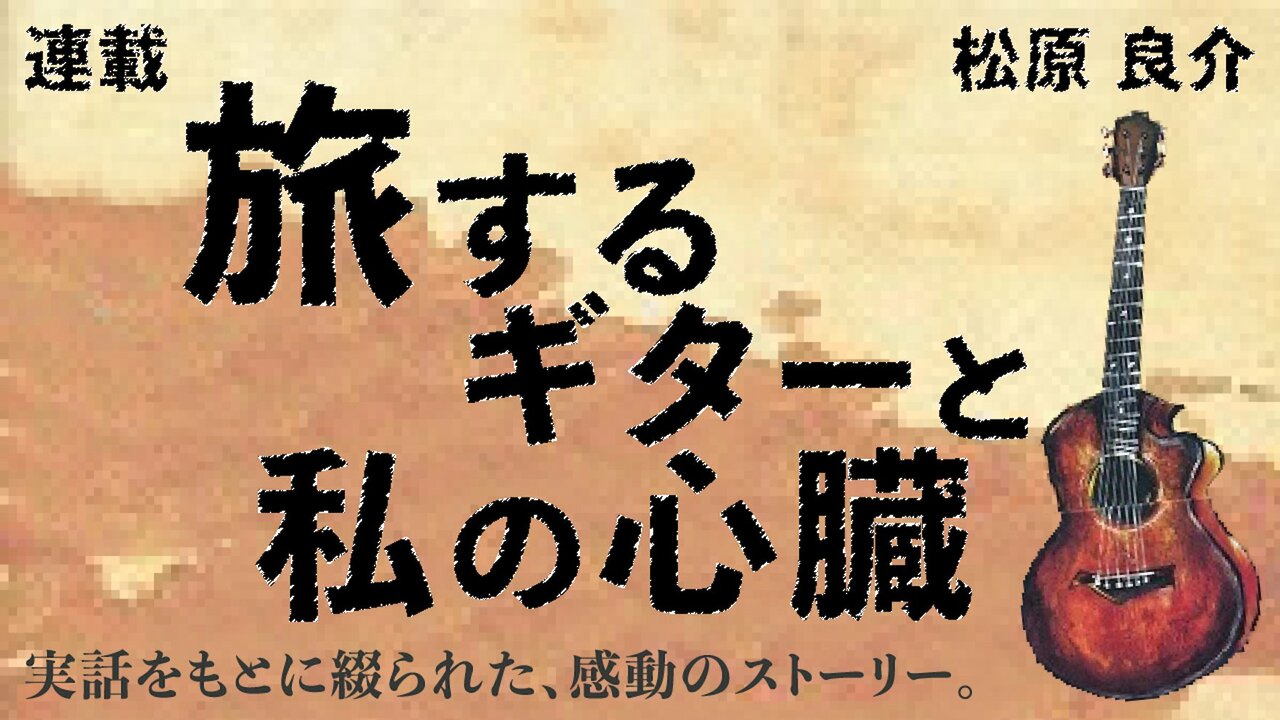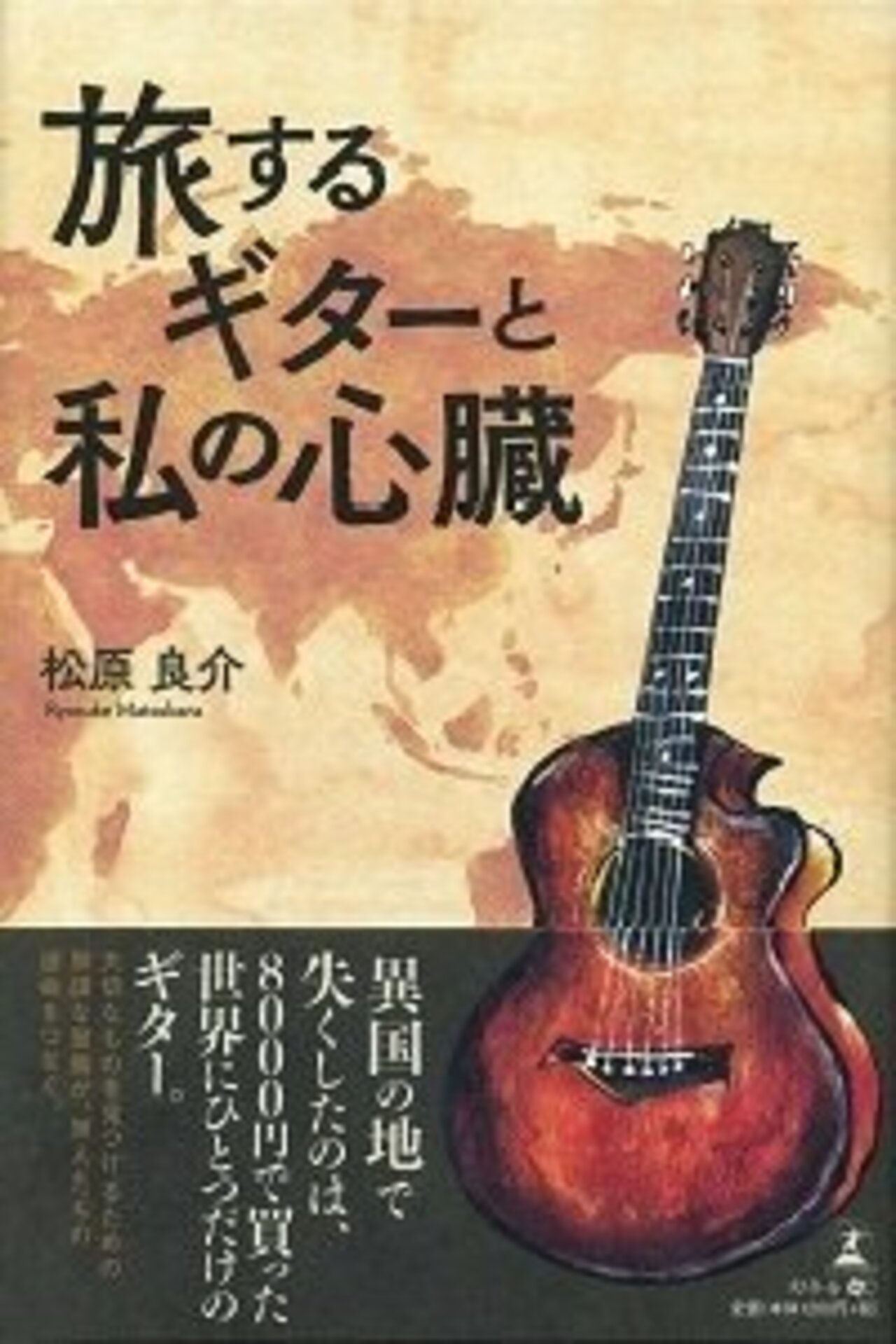〈宇山祐介の事情〉ハッピーバースデーを
2012年4月18日。
私(宇山祐介)は、最年長の教え子である緒形重治のピアノ発表会に立ち会っていた。この2ヵ月間、必死に練習した「ハッピーバースデー」が、いよいよ披露されるのだ。
用意した発表会用の一番広い教室にいるのは私と緒形、そして緒形の妻の静江の3人だけだった。緒形を慕って集まった生徒たちも、教室の外でじっと聞き耳を立てている。
緒形の指は優雅にゆっくりと鍵盤の上を散歩していた。タイトなスーツに身を包んだ緒形がピアノに向かう姿は一流のピアニストのようだ。
一音一音をじっくりと確かめながら、緒形は練習のときと同じように弾いて見せた。あまりのテンポの遅さに別の曲に聞こえてしまいそうなフレーズだったが、彼が弾く音色にはそんなことすら超越する美しさがあった。
ピアノの横には、緒形を心配そうに見つめる静江の姿があった。静江は用意された席に腰を下ろすこともなく、ハンカチを握りしめながら、緒形の奏でる音色を一つ一つ丁寧に拾い上げるように聞き入っていた。緊張した空間を優しく包み込むようにゆっくりと「ハッピーバースデー」が流れていた。
私は一人、教室の隅でその贅沢なコンサートを見守っていた。
この日、緒形は銀座にある高級レストランで静江の60歳の誕生日を祝ったあと、夫婦二人でこの教室を訪れた。緒形が何と言って帰りのタクシーをここに誘導させたのかはわからないが、ほろ酔いだった静江は驚いただろう。なにせ着いたのは駅前の音楽教室だったのだから。
私は緒形との打ち合わせ通り、到着した二人をピアノがある一番広い教室に案内した。そこは教室内の発表会や、コンクールのリハーサルなどで使う部屋だ。
小柄で上品なたたずまいの静江は美しい着物姿だった。廊下を通る二人には、今日の事情を知る生徒たちから期待のまなざしが向けられ、理由がわからない静江は少し困惑した様子だった。
私を含む3人だけで行われた、この発表会は緒形の集大成だった。
「ハッピーバースデー」は一般的に弾くと、どんなにゆっくり弾こうと時間にして1分にも満たないような曲だ。この発表会のために緒形は約2ヵ月間、この教室でみっちりと練習した。
「必ず弾けるようになります」
と威勢良く言ったものの、まったくピアノを弾いたことがない緒形に基礎から教え始めた当初は少し不安だった。緒形もおそらくそれに気がついていただろう。しかし、それを感じさせない様子で緒形は2ヵ月間、愚痴も言わずにただ黙々と練習を続けた。
「どんどん上達していくのが自分でもわかるから毎日が楽しくてね」
緒形は照れくさそうに笑ってそう言った。後から思うと私に気を遣って言ってくれたのかもしれない。
私は優雅に曲が流れる中で緒方と交わした会話を一つ一つ思い出していた。
そして妻のために2ヵ月間練習した、ゆったりとした「ハッピーバースデー」の演奏が終わった。
こちらをちらりと見た緒形に対して、私は何度も小さくうなずいて見せた。
緒形はゆっくりと立ち上がり、静江に向かって小さくお辞儀をした。その姿はまるで名曲を弾き終えたジャズピアニストのように、紳士的で華やかなものだった。静江が、顔の前で優しく手をたたき、まるで憧れ続けたジャズ奏者を見るような眼差しを自分の夫に向けた。ハンカチで拭うことをやめた涙は静江の頬を伝っていた。
見計らったように哲也が花束を持って教室に入ってくると、ふわりとバラの香りが教室を包んだ。得意げに現れた哲也を見て花が似合わない男だと私は思ったが、無事に曲を弾き終えた安堵と彼のコミカルな登場でその場にいた全員が笑顔を見せた。
それまで背筋をピンと伸ばしていた緒形も、このときばかりは胸をなでおろすようなしぐさをみせた。緒形は哲也から花束を受け取ると、静江にゆっくりと歩み寄った。
「欲しいものを聞いても、何もいらない、というキミに本当に困り果ててね」
静江の前に立った緒形は、まるでこれからプロポーズでもするかのように話し出した。
低い声で囁くように話す緒形の言葉は少なかった。ただ最後に「ありがとう」と36年連れ添った妻に短く感謝の気持ちを伝えた。長く人生をともにしてきた二人に言葉はそれほど必要ではないようだった。老夫婦の後ろで構える哲也が、こっちに向かって得意げに眉毛を上げた。
その日の業務が終わり、すべての教室を一通り見回って、私は誰もいないことを確認してから明かりを消してカギを閉めてまわった。明かりを消すと教室は何とも寂しそうに暗闇のなかに消えた。
「おう、おつかれ」
事務所に戻ると哲也が私の顔を見るなりニヤニヤしながら声をかけた。
ニヤついている理由はわかっていたし、私も同じ気分だった。
「うまくいったな! 緒形さんすごいよな、ノーミスだったぜ」
嬉しそうに話す哲也を見て、ようやく落ち着きを取り戻していた私の気持ちもまた高ぶり始めた。まるでライブの打ち上げみたいに興奮した我々の話は、冷蔵庫で冷やしてあったビールの力も借りてさらに盛り上がった。
気がつけば終電を逃してしまい、その日はそのまま事務所に泊まった。
「なぁ、哲也、もう少しここでやっていっていいか」
私は壁にかかったカレンダーに目を向けたまま言った
「ああ、もちろんだよ、お前なら絶対そう言ってくれると思っていたよ。やってみると楽しいだろ? お前向いてんだよこの仕事」
勝ち誇ったような声で哲也は言った。
「ああ」
と私はそのままカレンダーを眺めながら返事をした。
「あ、そうだ、哲也。お前、29日の夜って空いているか?」
私は財布からライブのチケットを取り出して哲也に尋ねた。