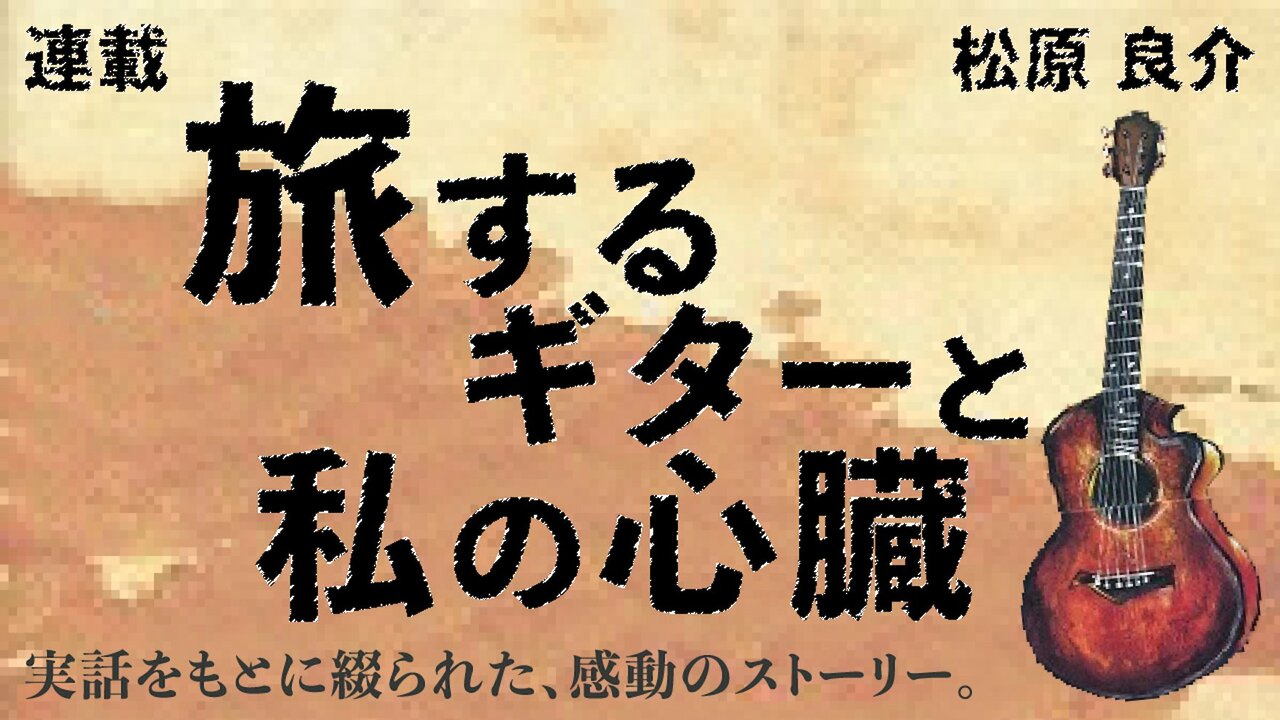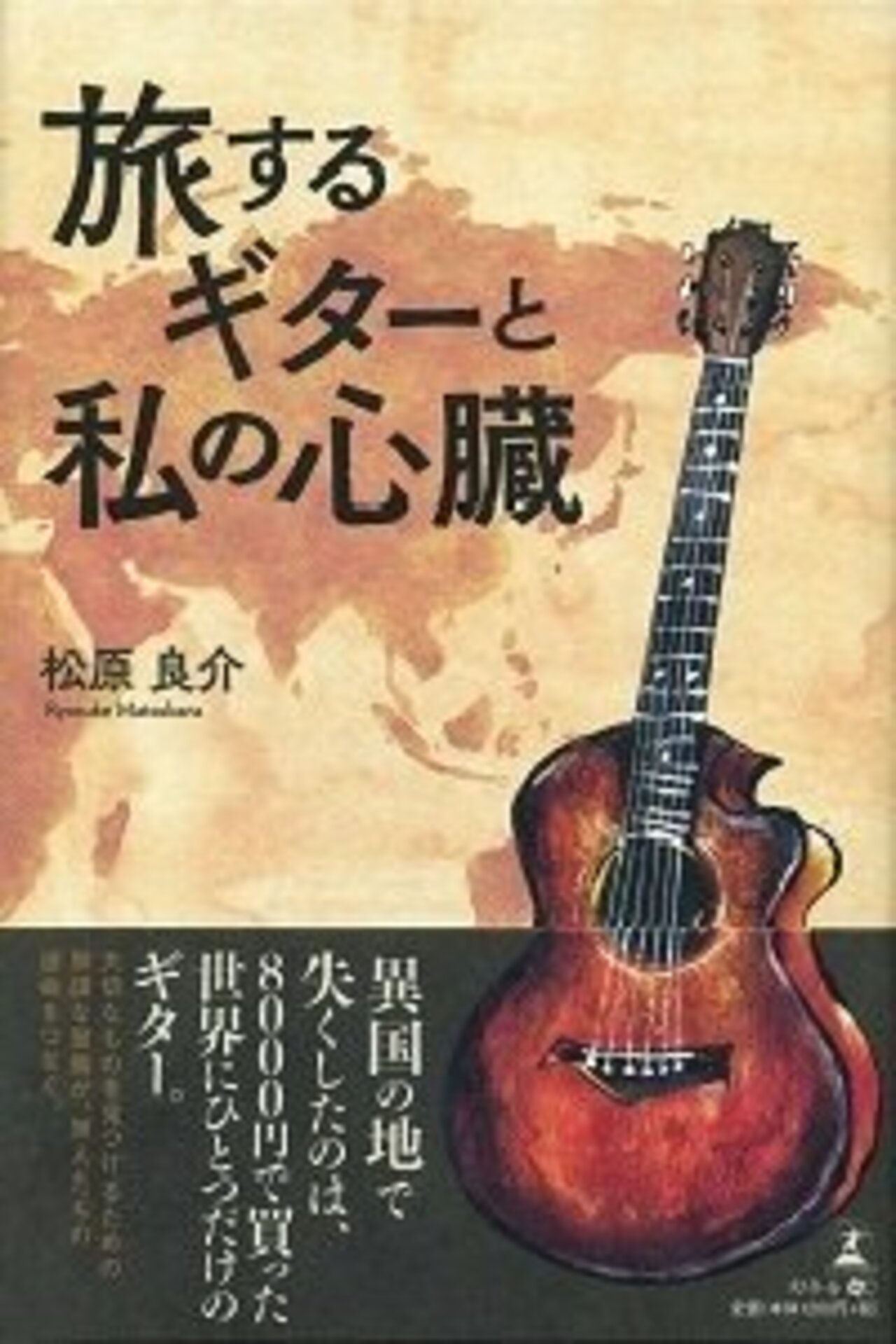2016年4月。札幌市内の大学病院
「ん? 何だこれ?」
私(野崎哲也)は意識を取り戻してすぐに右目の違和感に気がついた。開いたはずの目にまだ3分の1ほど瞼が残っていたからだ。口には呼吸器の管が挿入されていて声を出すことができない。
身体が思うように動かせなかったが、できる限り首を動かして、歪んだ視界で周囲を見渡した。うっすら明るい日差しがブラインドから洩れている。どうやら朝のようだ。
ここに来たときのことはよく覚えていて、ここが病院であることも知っている。昨夜、自宅でシャワーを浴びていたとき、大きく脈を打つような頭の痛みを感じた。同時に車酔いのような揺れる感覚と、指先の痺れを感じた。
少し休めば治まるだろうと思い、その場にしゃがみこんだのだが、痛みに耐えられなくなった頃にはすでに呂律は回らず、歩くこともできなかった。私はうずくまりながら言葉にならない声を上げて、壁を叩いて鳴らした。
幸いなことにリビングにいた母は異変にすぐに気がついてくれた。
受け答えはうまくできなかったが、意識ははっきりしていてそのときの様子はしっかりと覚えているし、搬送されたときの記憶もある。だから今のこの状況も理解している。
それにしても、この歪んだ右目の視界を何と表現すればいいだろうか。
“右目の右側”とでもいえばいいのだろうか。
とにかく、その“右目の右側”に今までなかった何かがあって、私の視界はいつもとは違う形の世界を映し出していた。何度も目をこすったり、瞼の上っ面を引っ張ってみたが、視界が以前の状態に戻ることはなかった。
術後の検査で後遺症がもう一つ見つかった。いわゆる“失語症”と呼ばれるものだ。
失語症は一種の記憶障害で、こっちのほうが何倍も厄介だった。なにしろ頭では理解しているつもりの単語が口から出てこないのだ。
例えば“傘”という単語。
目の前に傘を出されて名称を尋ねられたとき、知っている人間ならば、それを傘だと答えることができるだろう。しかし、私の場合、頭ではわかっているその〝傘〟という単語が口から出てこない。
雨の日にホテルのレセプションで頼み事をしようとしても、「すみません、傘を貸してください」と伝えることができないのだ。
ただし、言い方を変えて自分が知っている単語でカバーすることはできる。例えば、「すみません、雨が降っているときに差すものを貸してください」という具合に。馬鹿馬鹿しいが、そういう言い方ならできるのだ。もしも失語症のことを知らない人と私が話をしたら、その人は相当な苛立ちを覚えるだろう。
喪失した単語は主に幼少期から20代にかけてのものだったが、密接な関係にあった人や物の名称は憶えていた。家族の名前や、毎日乗っていた〝電車〟、毎日飲んでいた“コーヒー”などがそれにあたる。
昔の友人の名前はほとんど思い出せない。思い出せるのは30代になった今でも仲が良く、接点のある数名の友人だけだ。そのほかの友人は、容姿や住んでいる家までの道のりなど、事細かに説明することはできるが、ヒントをいくら与えられても名前が出てくることはなかった。
さらに残念なことに読み書きの能力も喪失していた。
平仮名はいくつか読むことはできたが、小学校で習うような簡単な漢字ですら読み書きができなくなっていた。担当医は、これらをもう一度覚え直すためには、相当な努力とリハビリが必要だと言っていた。
私が心臓に「VAD」と呼ばれる血液を循環させるポンプを装着したのは2015年の夏のこと。
持病の心臓疾患が悪化する以前はペースメーカーを装着して生活していたが、容体が悪化し、その結果として心臓移植が必要になった。
移植待機者は日本臓器移植ネットワークに登録することで、適合する臓器提供者(ドナー)が現れるまでVADを装着して順番を待つことになる。
VADは埋め込み式のペースメーカーとは違って大きさも役割も異なり、バッテリーは充電やメンテナンスが必要なため、体内に埋め込むことができない。今、私の右のわき腹には、1センチほどの穴が開いていて、そこから黒いケーブルが1本、身体の外に出ている。そのケーブルの先にはコネクターが付いていて、そこからコントローラーを経由してバッテリーを2台つなげることができた。
バッテリーは昔のゲームのカセットくらいの大きさで、フル充電すれば2日は過ごせるという代物だ。私はフル充電したバッテリーを毎日取り換えていた。交換の際は病院から特別な指導を受けた人間が立ち会う必要があるだけでなく、私のそばには、常にその資格を持った人間がいなくてはならなかった。なぜなら、VADに何らかの支障があったり、バッテリーが切れたりすれば、心臓に血液が運ばれなくなり、それは死に直結するからである。
私はVADを装着した当初、これはあくまで来たる心臓移植までのつなぎで、ドナーが現れるまでの辛抱だと思っていた。VADを装着したことで症状が劇的に回復したという事例も数多くあったため、私は大きな期待をもって手術にのぞんだ。しかし、私の場合VADを装着したことによる負担は思いのほか大きく、心臓は機能しているとはいえ、健康だった頃の状態とは程遠く、倦怠感が日常的に続くようになっていた。
そこにきて失語症という追い打ちがきてしまったのである。言葉を失ったこともショックだったが、こんなにも早く合併症が起こるとは思いもしなかった私は、いつ死んでもおかしくない状況に自分が置かれている現実を痛感した。
弱っていた私にとって、それはこの世の終わりに思えるような出来事だった。
ちなみにVADは血管内に血栓ができないようにするため、抗血栓に優れたチタン製となっている。ただ、そんなチタンでさえ人体にとっては異物であるため、どうしても血液が固まりやすく、血管内に血栓ができてしまう現象は避けられなかった。
血栓ができてしまった場合、それは血流に乗って全身に運ばれるため、血栓が臓器の血管をふさぐことがある。それが私の場合は脳だったのである。
それでも私は運良く生き残ることができたが、心臓のドナーが現れなければ、血栓のリスクは移植を待つかぎり付きまとうのだ。
そんな状況のなか、わずかな希望もあった。まるで神さまがいたずらに残したとしか思えなかったが、どういうわけか英語の読み書きはできたのだ。英語が喪失しなかったのは、もしかしたら30歳を過ぎてから真剣に学んだからだろうか?
ともあれ、私は見舞いに来る友人や家族と話をするときはいつも英語を交えて会話をした。大してうまくもない英語を話す姿は周囲にはさぞかし滑稽に映るだろうが、こんな状況で恥ずかしいなどとは言っていられない。状況を理解してくれた家族も医師も友人たちも協力してくれた。そしてその変てこな会話の時間だけが、私にわずかな希望を与えてくれた。
だから私は、もし外で急に雨が降ってきたら「雨が降っているときに差すものを貸してください」なんて言い方はせずにこう言うだろう。
「“アンブレラ”を貸してください」ってね。