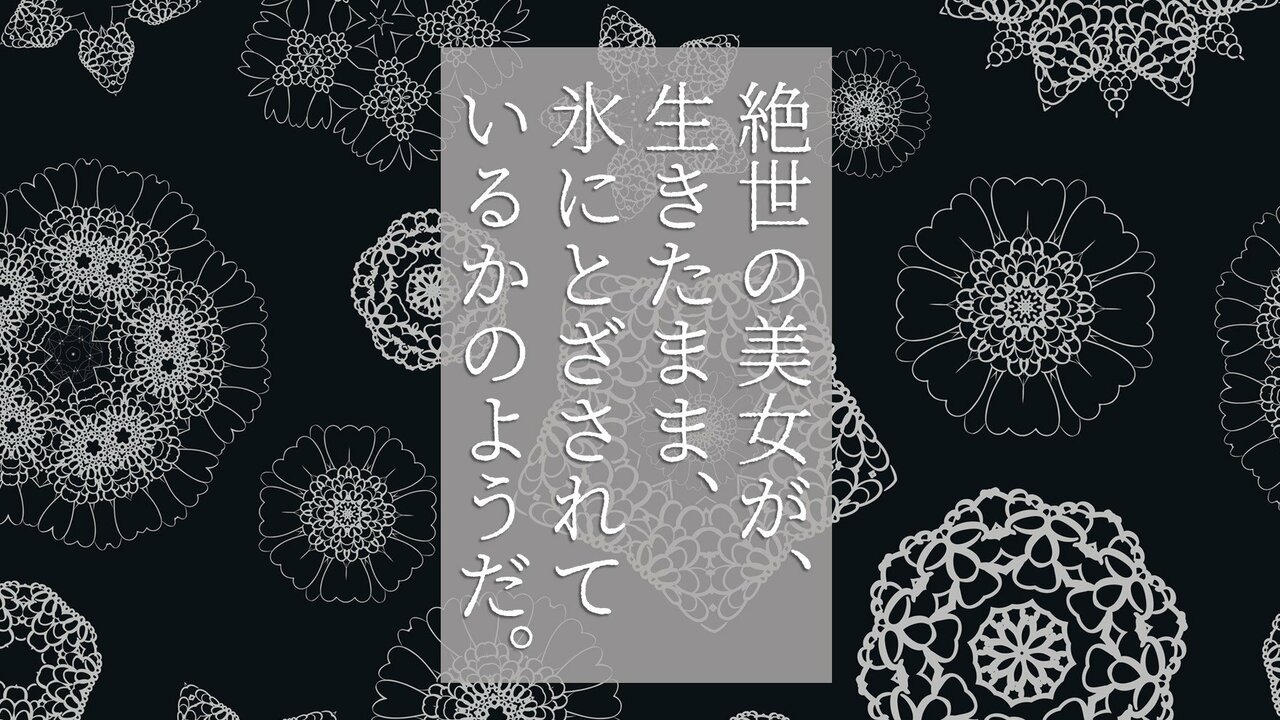序 ─ 嘉靖九年、われ自宮(じきゅう)し、黒戸(ヘイフー)の宦官となるの事
南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)!
ことが終わったあと、私は包丁をにぎりしめたまま、失禁したような血だまりの中に頽(くずお)れ、衙門(がもん)の塀に凭(よ)りかかるようにして、気絶していたという。気絶というよりは、なかば、死んでいたのである。
発見者が佛心(ぶっしん)ある僧侶でなければ、そのままこと切れていたに相違ない。この僧侶は、曇明(タンミン)といい、医療の心得があったので、すぐに胴まわりと両腿をしばって止血し、鼓楼東大街(ころうとうたいがい)にある、大千佛寺(だいせんぶつじ)という寺にはこび込んでくれた。
ここは曇明(タンミン)師修行中の寺であり、住職とも昵懇(じっこん)であったから、十分な治療をうけられるようとりはからってくれたのみならず、ようやく口がきけるようになった私の身の上ばなしをきき、いたく同情してくれた。
そして、自宮した者を宦官として召し上げることはない、との禁を犯して、知り合いの役人あてに、推薦状を書いてくださった。
あとで知ったことだが、自宮者は、「身体髪膚(しんたいはっぷ)これを父母に受く。敢えて毀傷(きしょう)せざるは、孝の始はじめなり」という『孝経(こうきょう)』の精神に反するかどで、罰せられるのだそうだ。
起き出そうとすれば、下腹部に激痛が走るので、寝ることしかできなかった。銭ももっていなければ、なんの役にも立たない私を、この寺の僧侶たちは、三カ月もの長いあいだ、食べさせてくれた。彼らがいなかったら、私はそのまま、無縁ボトケとなり果てたであろう。
曇明(タンミン)師は、ある日の夕暮れ、私を参道に連れ出して、歩かせた。
左右にならぶ五百羅漢の石像に見戍(みまも)られながら、一歩、一歩と、足を前に出した。自宮するきっかけともなった老宦官の、雛(ひよこ)のような歩きぶりがよみがえった。
ああ、自分もついに、こうなったか。
後悔していないかと問われれば、返答に窮する。だが、いずれはこうなるしかなかったのだ。どうせ、のたれ死にから、まぬかれぬ運命だったのだから――。
放浪生活のなかでは、じつに多くの死体をみたけれども、それらのひとつひとつが、わがゆくすえを暗示しているように思えたものだ。ああなっても、かまわん――覚悟して包丁を使ったものの、まだ、生きている。
佛は、いましばらくの生をぬすめと言ってくれた。
見あげれば、人身大の吉祥天(きっしょうてん)像が、ふしぎな微笑みをたたえている。まるで、絶世の美女が、生きたまま、氷にとざされているかのようだ。
優美なお顔をぬすみ見ているのが、ばれてしまった。
「どうだ、美しい佛(ほとけ)だろう」
「いまにも……うごき出しそうですね」
「拙僧も、はじめて見たときは、そう思った。あんまり大きな声では言えないが、この吉祥天に懸想(けそう)する修行僧も、いるくらいだ」
「どんな佛師が、刻まれたのですか?」
「うん……」
曇明(タンミン)師は、声をおとした。
「これは、寺でも一部の者しか知らない来歴だ。他言せぬ、と、約束するか?」
「します」
「この吉祥天をきざんだのは、建文帝(けんぶんてい)の長子、文奎(ウェンクイ)様だという言い伝えがある」
「えっ」
建文帝とは、ほんらいなら、二代目の皇帝と目される方である。
わが明朝には、秘史がある。
明朝をひらいた太祖洪武帝(たいそこうぶてい)は、漢の高祖に比肩しうる英傑であったが、後継には頭をなやませた。皇太子とさだめた長子が、早世してしまわれたことに、端を発する。
太祖には、二十六人の皇子があった。長子である懿文(イーウェン)皇太子が亡くなったいま、皇位継承の正嫡は、懿文(イーウェン)皇太子の子、允炆(ユンウェン)太子である。太子は、天資仁厚、学問をこのみ、伝統を重んじたので、碩儒(せきじゅ)英才、国の柱となるべき人材が、雲集した。
太祖が崩御されたのち、允炆太子は建文帝として即位し、天下は、さだまった――かと思われた。しかし、皇統は、周到な準備のもとに、くつがえされたのである。
武勲赫々たる太祖の四子、燕王が、叛旗をひるがえし、当時のみやこ、南京に攻め寄せた。あらかじめ内通者――とくに、宦官が多かった――を出してしまっていた宮城は、ひとたまりもなく、灰かい燼じんに帰した。建文帝の正室、馬(マー)皇后は、城を焼き尽くす焔にのまれ、むざんな最期をとげられた。建文帝もまた、そこで自害した――と、伝えられている。
燕王は皇帝位に即つき、永楽(えいらく)帝ていとなった。これが、現在の嘉靖帝(かせいてい)へつながる皇統となる。同時に、建文帝と馬皇后の存在は、歴史から抹消された。
いまでも、建文帝のことを語るのは、禁忌とされている。