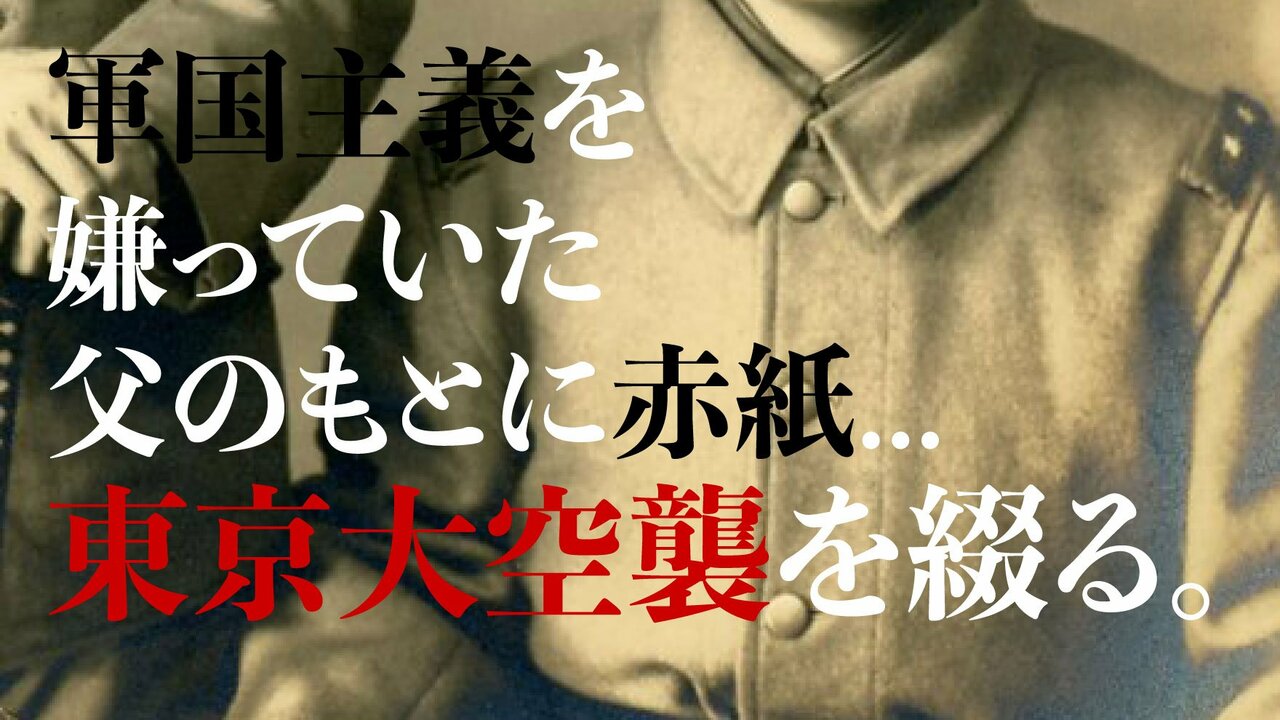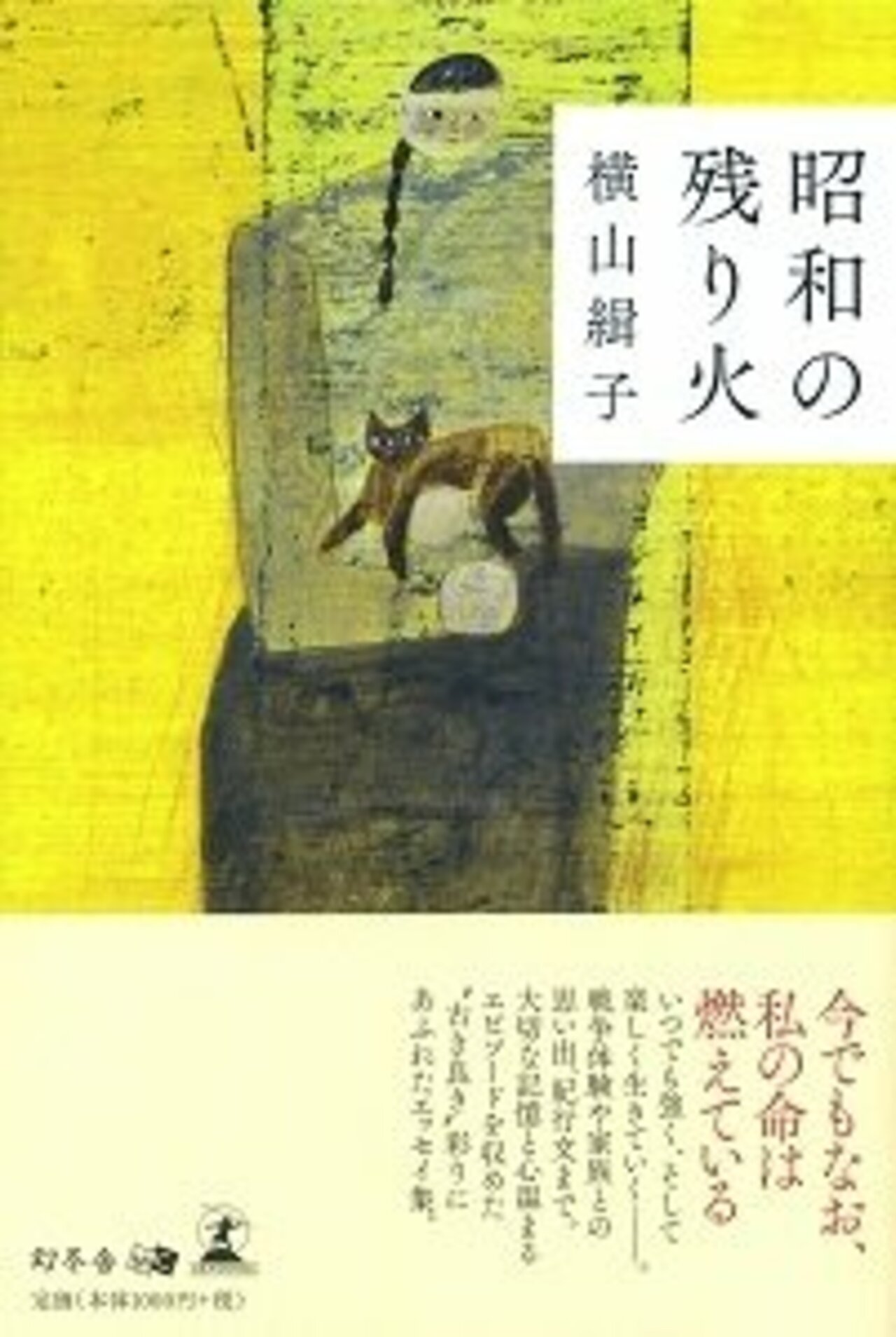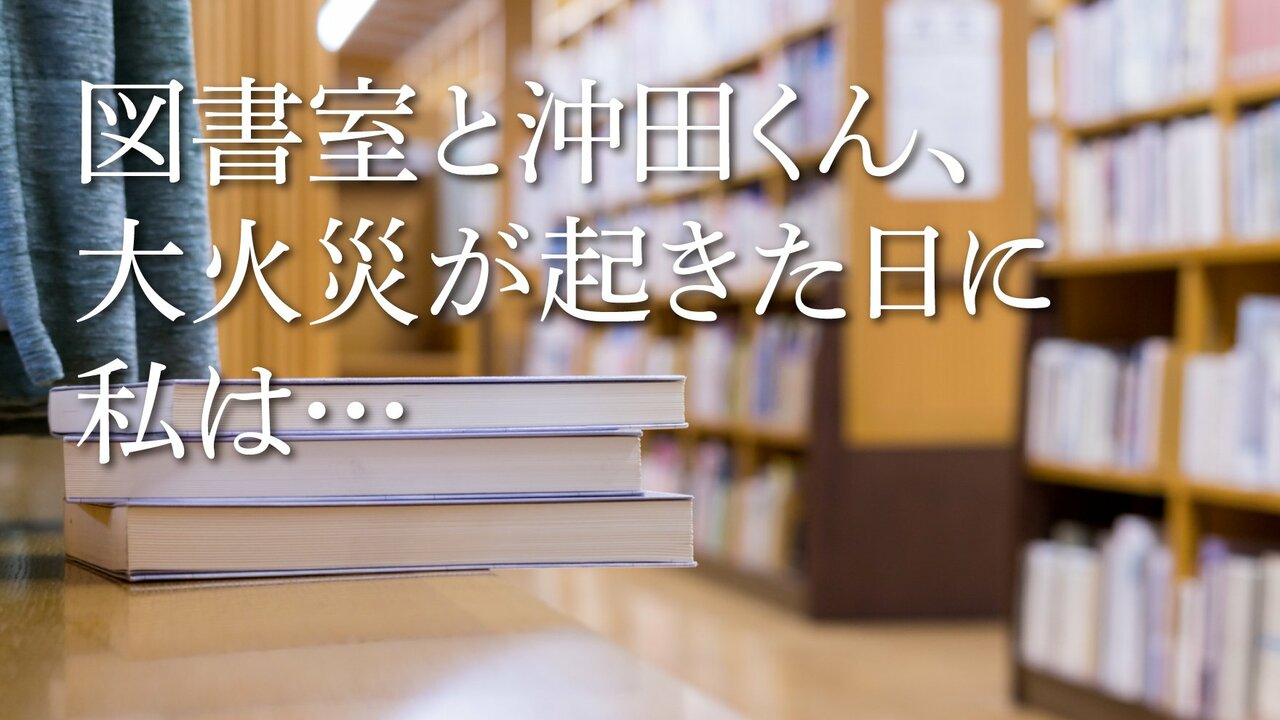【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
私の戦中戦後
家の近くまできたとき、突然空からけたたましいサイレンの音が降ってきた。私は仰天して、その場にしゃがみ込んでしまった。それでもここにいては大変なことになると思い、這うようにして家に帰った。私が初めて恐怖というものを知った瞬間である。
昭和十九年の初夏、私は満五歳で両親と横須賀で暮らしていた。
横須賀には、地の利も手伝って明治の初めから大型艦船の造船所があった。やがて鎮守府が置かれて日本最大の軍港都市となり、名だたる戦艦が次々とこの港から進水していった。そうなると人手が要る。全国から人が集まって人口が急に増え、土地が拡張されていった。皮肉なことにこの頃から終戦までが横須賀という町のいちばん栄えた時代だった。
昭和十六年、日本は勢いよく太平洋戦争に乗り出したものの米英にはかなうべくもなく、次第に追い詰められ、十九年六月にマリアナ沖の海戦で敗れると、西太平洋の制海権は米軍のものとなった。
この頃からではないだろうか、大人たちが声をひそめて、敵の飛行機が飛んできて爆弾を落とすなどと戦争の恐ろしさを語るようになったのは。私はそれを小耳にはさんでいたので、突然のサイレンに腰が抜けるほど驚いたのだ。
明けて昭和二十年、警戒警報のサイレンは三日とあけず空から降るようになった。
大抵は夜だったから、母に起こされて枕元に用意しておいた防空頭巾とリュックを身につけて、海を見下ろす崖の中腹に掘られた共同の防空壕に急いだ。壕に飛び込むやいなや飛行機の轟音が迫ってきて、今にも爆弾が落ちてくるのではないかと息を詰めていると、うなりを上げて遠ざかっていった。
当時どの家も庭に防空壕を掘った。初めのうちは警報が鳴るとそこに入っていたが、防空壕ごとつぶされるというので共同の防空壕に避難するようになったのだ。
横須賀にもっとも被害があったのは二月半ばの二日間だった。十六日の早朝から連続して数百機の艦載機が東京湾に来襲して、そのうちの数機が横須賀に爆弾を落とし、軍の施設や小学校が破壊された。死者は数名程度で大した被害はなかったが、皆震え上がり、町は臨戦態勢に入った。
『横須賀百年史』(横須賀市)によると、「国民学校初等修了者以上を隊員とし市内十九中隊を編成し、手榴弾の扱い方や竹槍攻撃の方法について指導を行った」とある。
男はゲートルに戦闘帽、女はモンペと割烹着を着て防空頭巾をかぶり、バケツリレーによる消火訓練に精をだした。私も外に出る時は必ず背中に防空頭巾を背負った。
手元に、セピア色に褪せた集合写真がある。真ん中の椅子に背広姿の父が掛け、膝に揃えて置かれたその手を小さな手がぎゅっと握っている。父は剃りたての坊主頭だ。前日に雪が降ったと見え、庭にはうっすらと雪が残っている。裏を返すと、〈昭和二十年三月初旬召集に際して〉の文字がある。
三月十一日に千葉の佐倉歩兵隊に入隊せよという召集令状が数日前に届いたのだ。