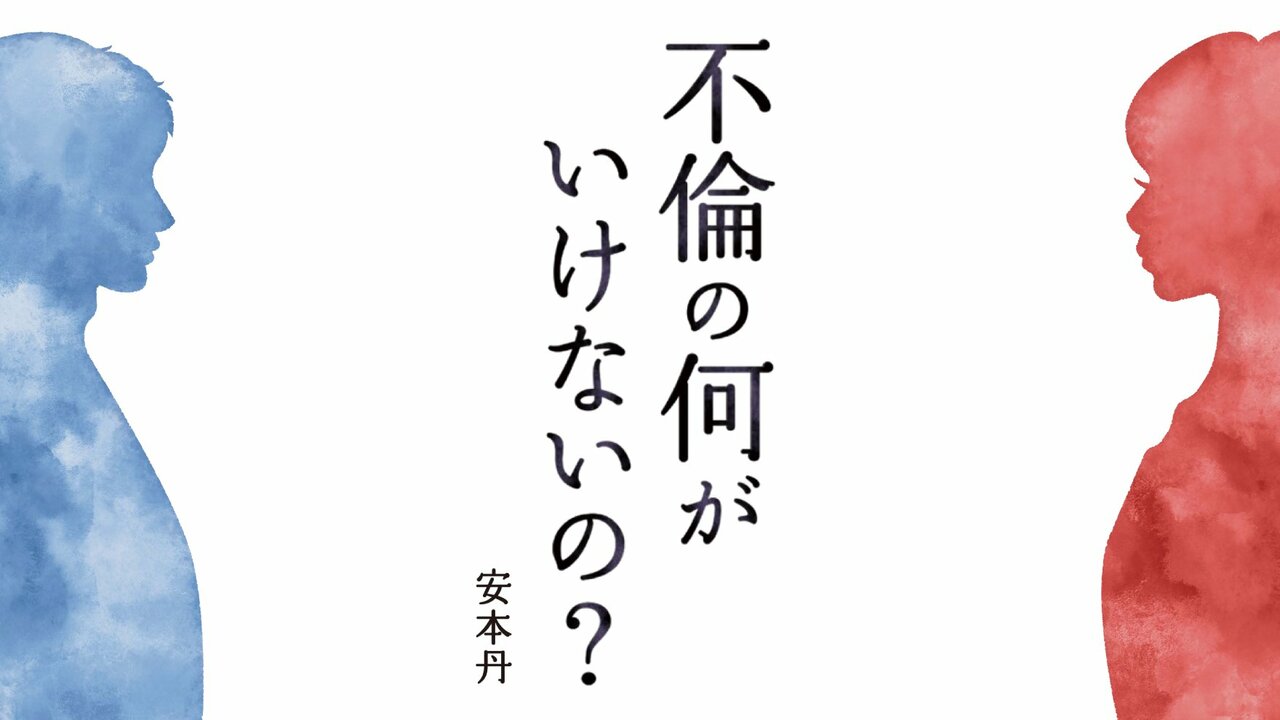第十一章 インフルエンザ
三月七日。夜、公園デートをした。高校生みたいだと思った。
私は待ち合わせ場所にショウ君に黙って愛犬を連れていった。こうすればホテルに行く心配はない。いつものように流されて、肝心な話をしないまま快感だけを求め合うのはもう沢山だった。
高級ブランドショップが立ち並ぶ大通りで私達は落ち合った。澄んだ空気にネオンがキラキラと美しく輝いて見える。なんてロマンチックなのだろう。犬を連れた私を見てショウ君は驚いていた。
私の希望で近くの公園へ行った。公園といえど繁華街の真ん中にある小さな空き地程度のスペースだ。しかしそれでもスケートボードを楽しむグループ、ベンチで話すカップル、一人で煙草を吹かすサラリーマンなど、人の気配で公園内は賑わっていた。
ショウ君は何か温かいものでも飲むかと聞いてくれた。
私は水筒を持っていることは言わずに自販機のお茶を買ってもらった。三百五十ミリリットルのペットボトルの生温かいお茶一本が、嬉しくて嬉しくて仕方がない。旦那が今までにくれたどんなに高価なプレゼントよりも嬉しかった。
ピッタリとくっつける小さなベンチに座ろうとした私を、ショウ君はゆったりとした長めのベンチへと誘導した。彼は常識人だから、人前で恋人ごっこはしてくれないのだろうと前向きに捉えた。もうすっかり忘れてしまうところだったがよくよく考えれば私は既婚者だ。禁断の恋なのだからこの方が都合がいい。
犬のリードをベンチの足に括り付け、会話を楽しんだ。
暖かい夜だ。しかし夜の公園にじっとしていると私の手は冷たく悴かじかんだ。ショウ君と手を繋ぎたい。そう思っても私は彼に甘えられなかった。
仕事では、躊躇なく客の手を取り指を絡ませられた。ショウ君が店に来た時もそうしただろう。しかし今はもうできなかった。彼の柔らかな態度が、逆に私を遠ざけているように感じた。
相変わらずショウ君は私を可愛い可愛いと何度も褒めるのだった。私は照れて視線をスケートボードをする人達へと向けた。
会話の途中でいきなりショウ君が核心をついてきた。
「美雪ちゃんってあんまり男の人に依存しないっていうか。さっぱりしてるよね。そんなに真剣に人を好きにならないっていうか」
本当の自分とはあまりに真逆のイメージに呆気に取られ思わず笑ってしまった。
十年ぶりに恋をして思い知らされた。自分が恐ろしいほどの恋愛体質、男性依存症であるということを。
ショウ君と出会って恋に落ちてから、私の生活は彼を軸に動いている。
朝ヨガをするのも、晩ご飯を食べないのも、ショウ君に抱かれる日のための体重管理。
私の幸せはショウ君に会えること、喜びは連絡が来たとき。悲しみはデートの最後の別れ。苦しみは、連絡が取れない日々。