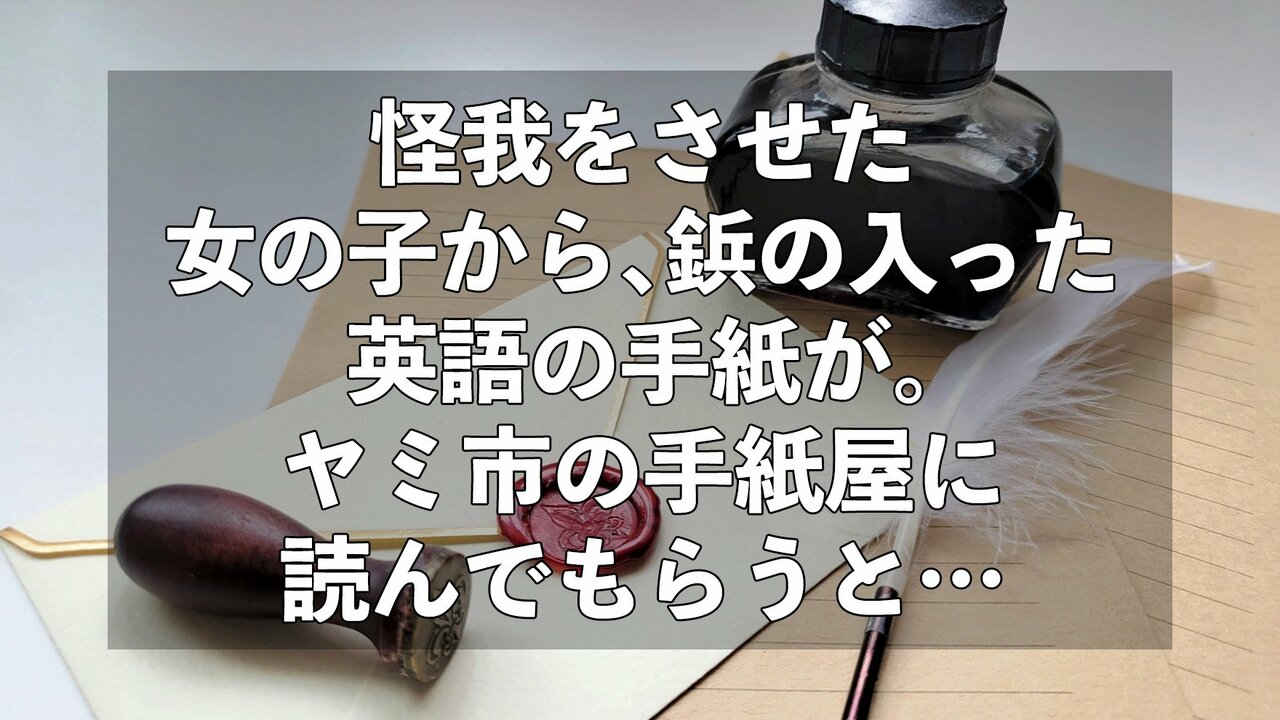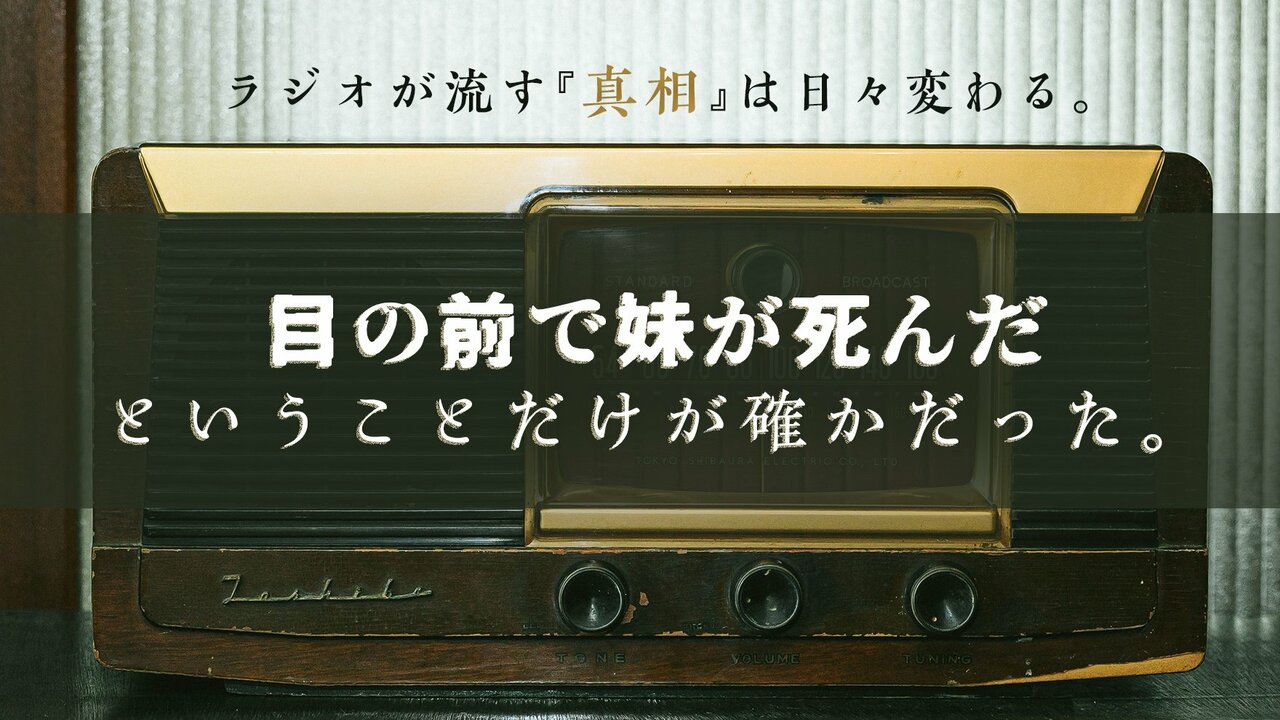鋲
そのとき飛行機はわずかにこちら側の翼を下げた。翼の上面が見えた。翼端は丸かった。ぷっつりと切り落としたようなグラマンのそれではなかった。ぼくは妹に体当たりした。妹はのめるように一メートルくらい先の地面に倒れて畑の上に身を伏せた。すさまじい土煙が畑の上を走り過ぎるのと妹が畑の上に伏せるのと同時だった。
ぼくは金縛りになったように動くこともどうすることもできず、その位置に立っていた。後部銃座が付いているのだ。操縦席に続く後部銃座の天蓋は開いていて、乗り出すようにして撃ってきたアメリカ兵の顔はすぐ目の前に見えた。撃ったのは先頭の一機だけだった。全てが一秒か二秒の出来事だった。三機はそのまま轟音を残して西の空に消えた。
妹はぼくが押し倒したままの姿勢で地面の上に伏せていた。水が湧いてきたのかとぼくは思った。防空頭巾のすその、ちょうど背中のあたりがジワジワと濡れてきた。
そしてたちまち着ているものがぐしゃぐしゃに濡れた。服が黒かったせいか、赤い血を見たという記憶はぼくにはない。ただ水を含んだ雑巾みたいになった妹はもうぼくとは別の世界に行ってしまっていた。
ぼくは茫然と立っていた。風が吹くと妹の防空頭巾の紐が動いてぼくは息をのんだけれど、風がやむとまた動かなくなった。
ぼくはどのくらいそうしていたのだろう。低空を飛ぶ飛行機の爆音と機関銃の発射音を聞いて、どこかの防空壕に入っていた警防団の腕章を付けた男が二人近づいてきて叫んだ。
「そんなところにぼんやり立っていちゃダメじゃないか。敵機がその辺にうようよしているぞ」
言いながら倒れている妹に気が付いたのだろう。
「それは俺達がなんとかする。お前はすぐに防空壕に入れ」
頰に思い切り卵の白身をなすりつけられたような感触が来た。ぼくの大切な妹が《それ》になってしまったのだ。
でもぼくは言った。
「お願いします」
一刻も早く母に知らせなければ。