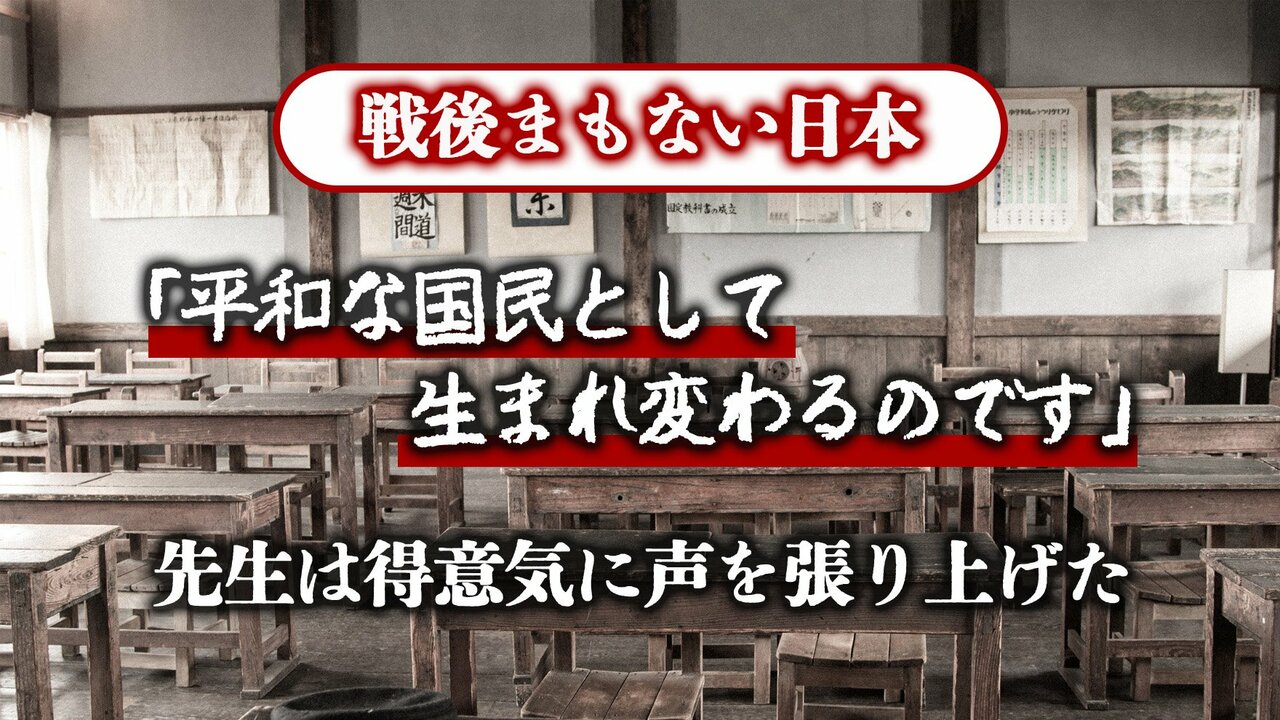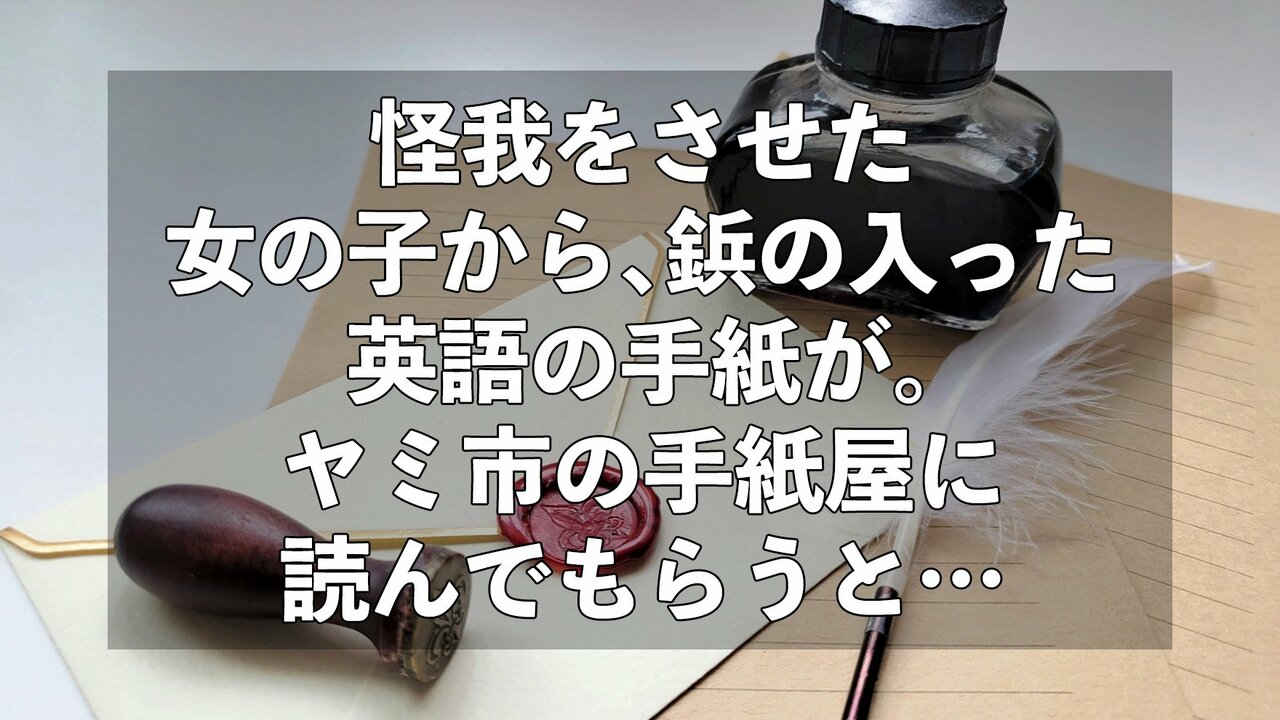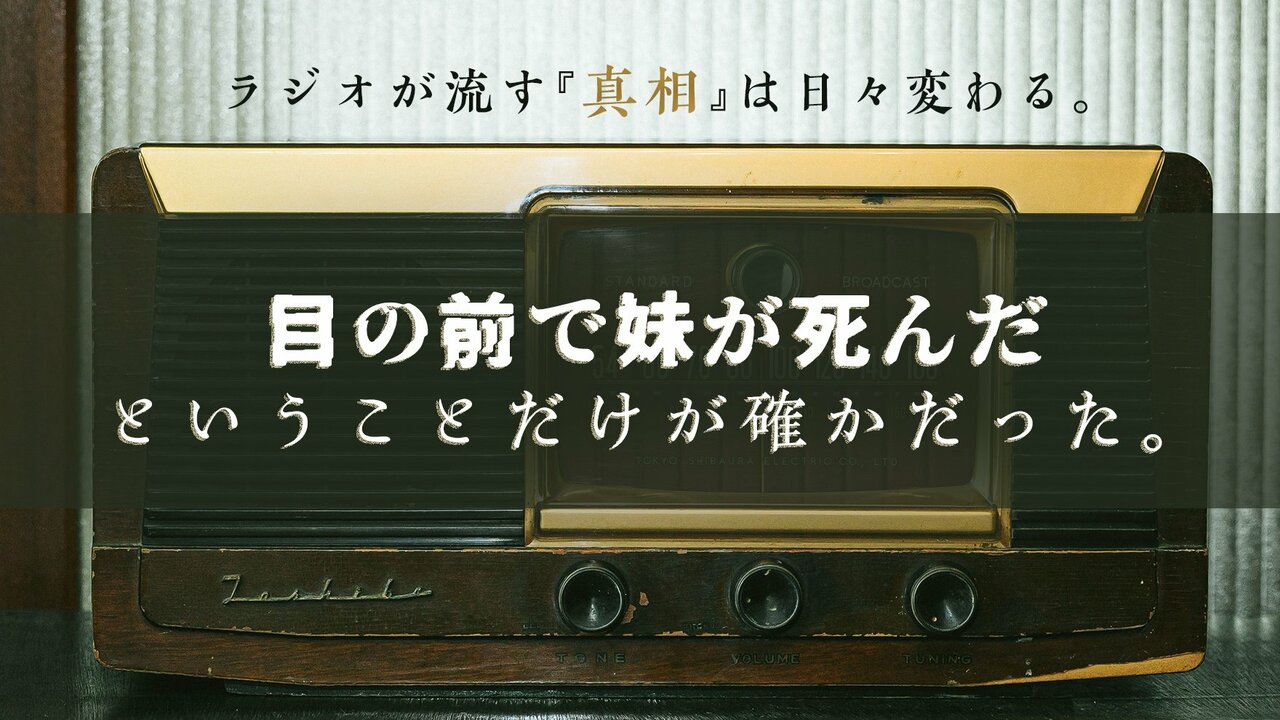鋲
街を隔てた遠くに海が光って見えていた。街といったって見渡す限り赤茶けた焼野原だ。そこは半年前まできれいな街並みが広がっていた所だ。色とりどりの屋根瓦が、モザイクのように並ぶ家々の間を緑の街路樹に縁取りされた道路が海に向かって伸び、駅舎の時計台や消防署の火の見櫓や公園の観覧車などが玩具のように遠くに見えていた。
今それらは何もない。あの一晩の間に降り注いだ焼夷弾と爆弾の雨がその景色を全部変えてしまったのだ。今その同じ場所には、焼け跡から拾い集めた焼けトタンを屋根にして、焦げた板でまわりを囲ったバラックが瓦礫の隙間の地面に貼り付くようにひしめいている。
爆音が近づいて、ヘリコプターが煙の尾のようなものを曳き始めた。

「DDTという新しい薬を撒いているんだ」
先生は言って、教壇を降りると窓際に近寄って外を眺めた。
「蚤もシラミも家ダニも、ああやって空からDDTを撒いて一掃しちゃおうってわけだ。さすが進駐軍だ。あれだけの物量と機動力を持った国に対して、日本は全く愚かな戦争をしたものだ」
日本は、と言うとき先生は文明とは無縁のどこか遠い国を批判するように腕を高く組んだ。ぼくは無感動に窓の外に目をやった。学校は高台にあるから、街の上を低空で飛ぶヘリコプターは、ぼく達の目の高さの延長線上にあった。
戦争が終わって初めてこの国の上に現れたときは珍しかった背中にローターの付いたアメリカ製のこの機械も、三カ月たった今はもうただの景色の一つでしかない。あまりにも激しい変化が次々とまわりに起こって、もう何が出てこようと、ぼく達はすぐに倦きた。
「じゃ、また授業に戻る」
その授業にも、ぼく達はもう倦きていた。でも筆に墨をいっぱいに含ませなおして待った。