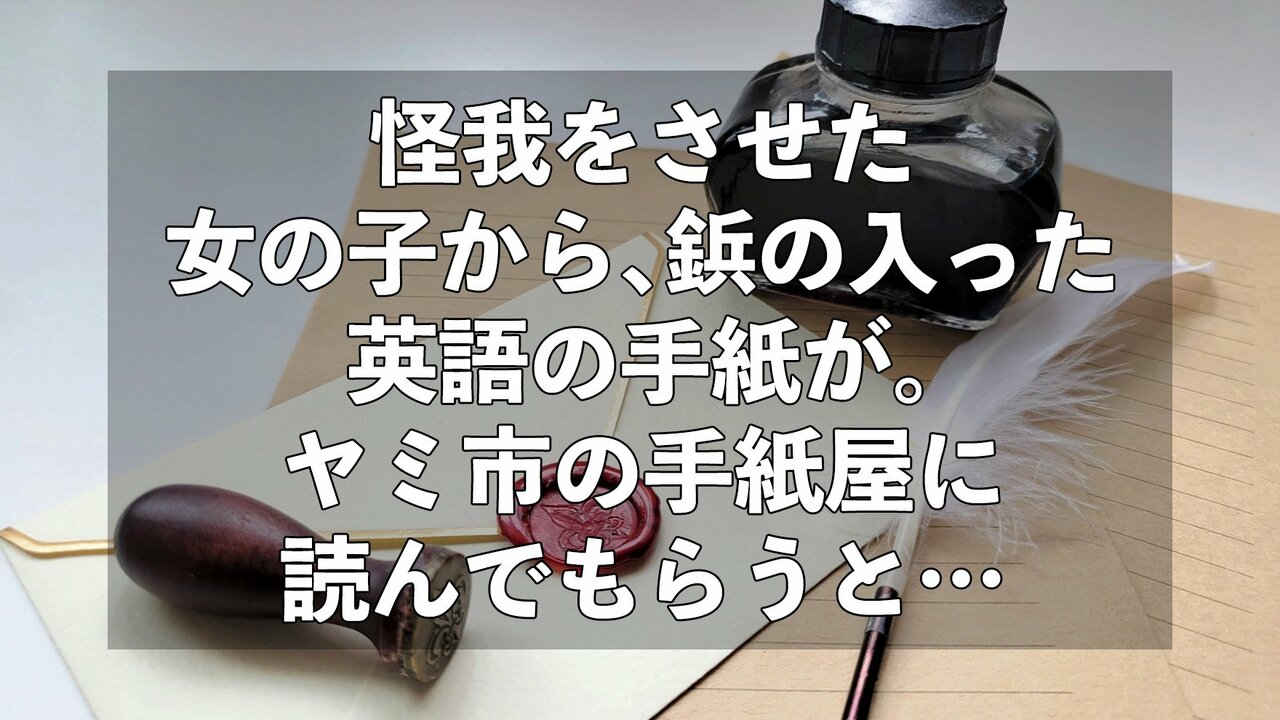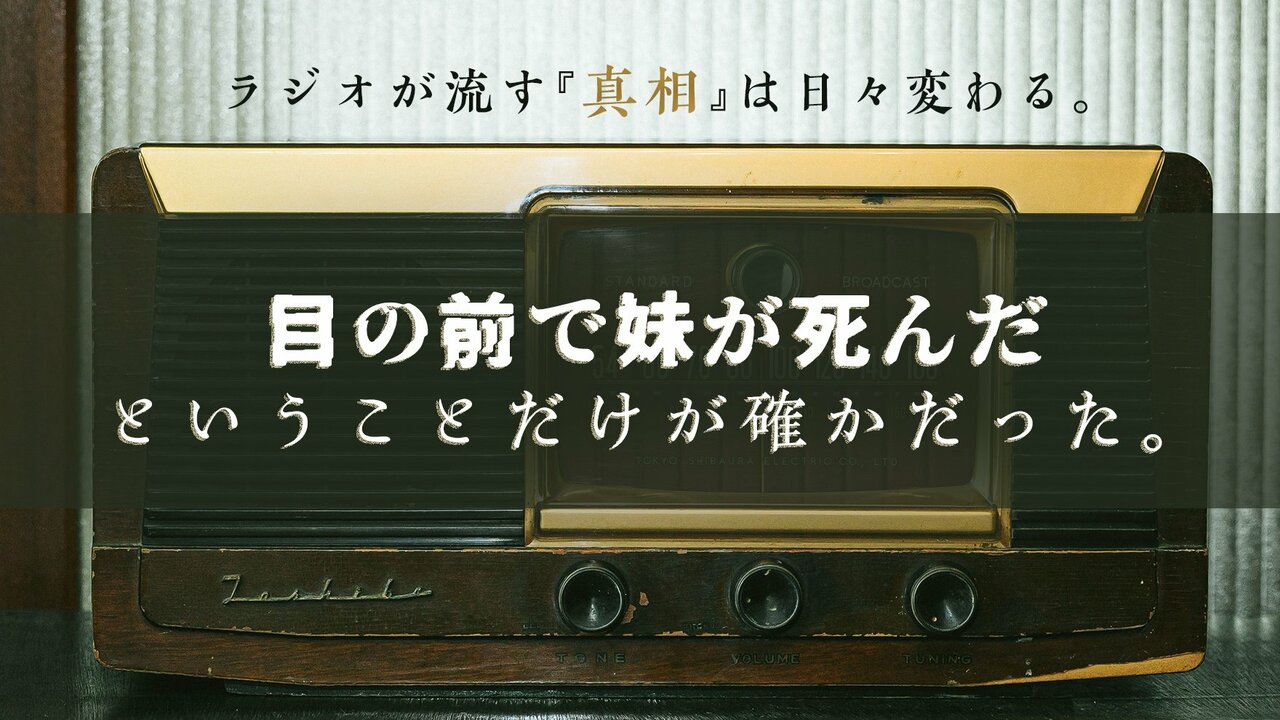鋲
誰に読んでもらったらいいのか。翌日の授業をうわの空で聞きながらぼくはそのことばかり考えていた。何が書いてあるのか見当もつかない以上、両親に見せるわけにはいかなかった。学校の先生にも何と説明していいかわからないし、内容によっては大変なことになると思った。学校の先生だってMPからぼくをかばうような危険なことは決してするわけがなく、それどころか通報でもされれば全てが終わりだった。
ぼくはポケットの中の鋲の付いた消しゴムを手で触りながら考えていた。すると前に友達から聞いて忘れていた話を突然思い出した。

そうだ。ヤミ市だ。ヤミ市に行ってみよう。
空襲で焼けた街は建物が建つまで復興しなかったわけではない。焼け跡の廃墟から街は物凄いエネルギーで復元していった。
全国どこでも、それはヤミ市という名前で呼ばれていたけれど、焼け跡の板一枚、トタン一枚がたちまち店舗になって商品が並んだ。人々がそこに集まり始めると何もないはずの日本の中のどこから持って来たかと思うくらいあらゆる物がここに集まっていた。ベーゴマも長靴も進駐軍放出のギャバジン素材のズボンも少し汚れているのを気にしなければ何でも手に入った。
ヤミ市には英語の読み書き屋がいるのだという話をぼくは友達に聞いたことがあった。
進駐軍の若い兵隊達が街に溢れていれば、それの相手になる日本の女達も街に溢れていた。それらの女達は、表面が黒くツルリと光るナイロンのバッグを持ち、シームのピチッと立ったナイロンストッキングを履いていた。靴もエナメルのピカピカだった。全部PX(進駐軍専用の売店)でアメリカ兵に買ってもらった服装で身を固めていたから、モンペ姿の一般の女達とは比べものにならないくらい鮮やかで得意気でさえあった。
これらの女達を相手にする職業として手紙屋がヤミ市にいるというのだ。正確にどこにいるのかを聞いていなかったことをぼくは後悔していた。しかも子供が頼んで読んでくれるかどうか。それもわからなかった。でも足はヤミ市に向いていた。
女達に聞いてみればわかるだろうとぼくは思った。ヤミ市はS川のほとりの坂田橋から柏木神社の境内にかけて道路の両側に伸びていた。そういう女達は一目でわかったから、ぼくは思い切って声をかけた。
「あの、手紙読んでくれる人を知りませんか」
最初の一人は黙って行き過ぎたが、二人目が返事をしてくれた。