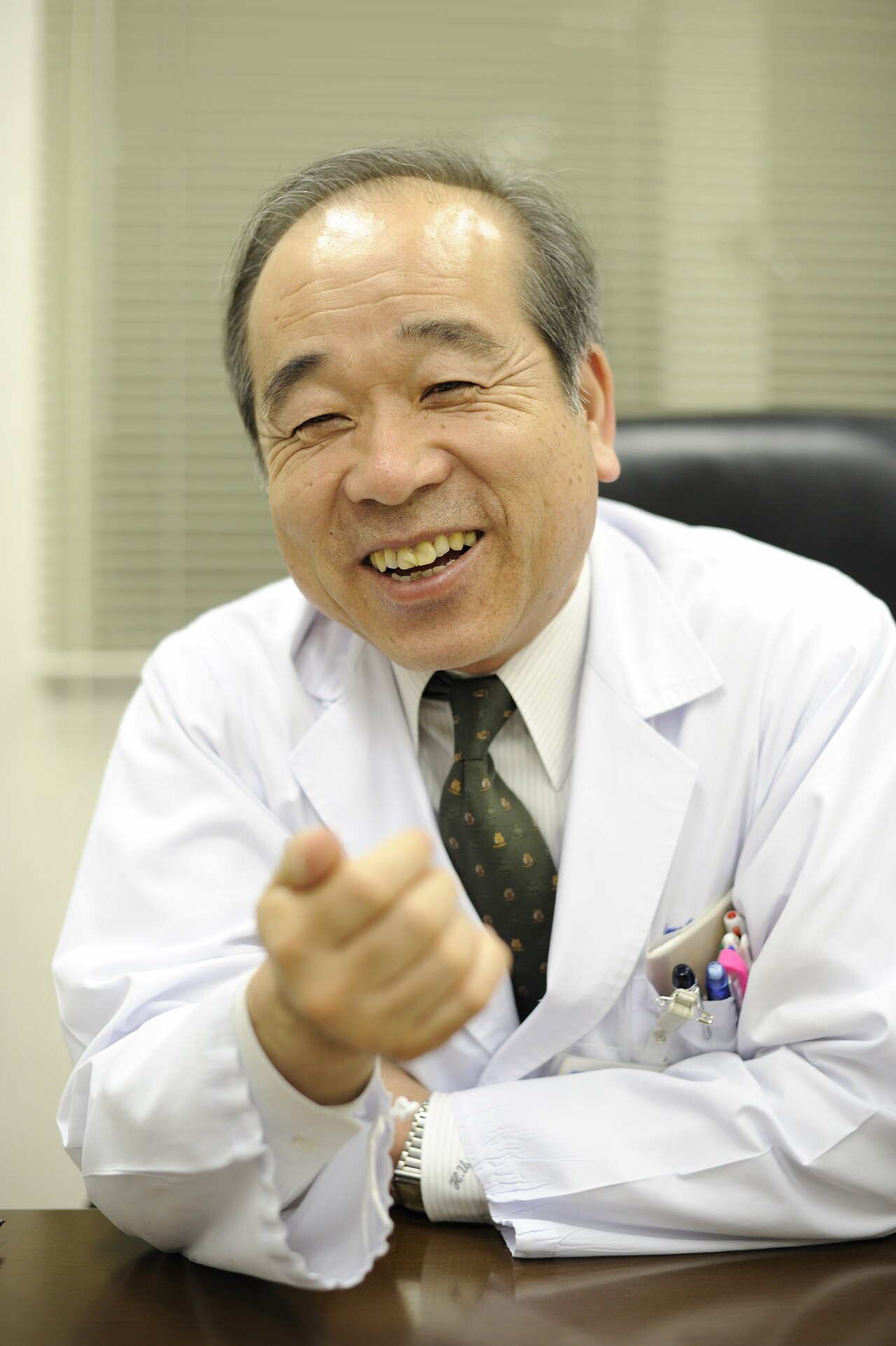再び患者の顔の上に屈んだ。梅澤の汗か涙か解らない滴が患者の顔に滴り落ちた。突然、患者の瞼が開き、覆い被さった梅澤の目と目が合った。
患者が言葉を発したが、苦しい息のために声に成らなかった。周りにいる麻酔科医にも看護師にも聞こえなかったであろう。しかし、梅澤には唇の動きでその言葉が読めた。
患者は、梅澤の目を見据えて「オ・ニ・」と呟いたのである。
「馬鹿な事言わないで。直に、呼吸を楽にしてあげるからね」
梅澤は、再びマッキントッシュを挿入した。
焦る心を抑えつつ、慎重に慎重にと自分に言い聞かせ、気管支にチューブを挿入した。アンビューバッグで空気を入れながら、聴診器で肺の音を聞いた。今度は、バッグを押すごとに肺が広がる音が聞こえた。
急いで、人工呼吸器にチューブを接続して、100%の酸素を機械で送り込んだ。機械の送気と同調して、胸が広がっている。鎮静剤を点滴で投与して患者が苦しまないようにした。紫色に変わっていた患者の顔に徐々に赤みがさしてきた。薬で鎮静が効いた患者は、機械のシューという音に合わせて胸が上下することを除けば、安らかに眠っているように見えた。
翌日、一時的に小康を保ったように見えたが、レントゲンの両肺は真っ白になっていった。間質性肺炎は改善するどころか、さらに進行していた。梅澤は、絶対に回復すると信じて、人工呼吸器の管理や点滴の調整を付きっきりで行なった。
しかし、挿管の二日後の夜、一度も目を覚ますこともなく患者は亡くなった。疲れきった身体で梅澤は死後の処置をした。深夜に寝台車で自宅へ運ばれていく患者を手を合わせて見送った。
梅澤にとって、初めての患者の死であった。倒れそうになりながら医局に戻った。疲労と喪失感で押し潰されるようにソファーに崩れ落ちた。身体を動かす事も出来ず、天井をぼんやり見つめていた。脳が勝手に働きだして、挿管した日の光景が浮かんできた。
苦しみに歪んだ患者の顔、病室の暑さとセミの声、額から汗を垂らした自分が見えた。患者の顔の上に覆い被さって、2回目の挿管を試みた。突然、患者の目が開き、目と目が合った。そして、患者は苦しい息の下で、「鬼」と呟いた。
窒息寸前の状態で、気管に異物を入れられる苦しさは想像を絶するものであろう。それを実行した自分が鬼に見えたに違いない。いや、本当に鬼のような形相をしていたのかもしれない。