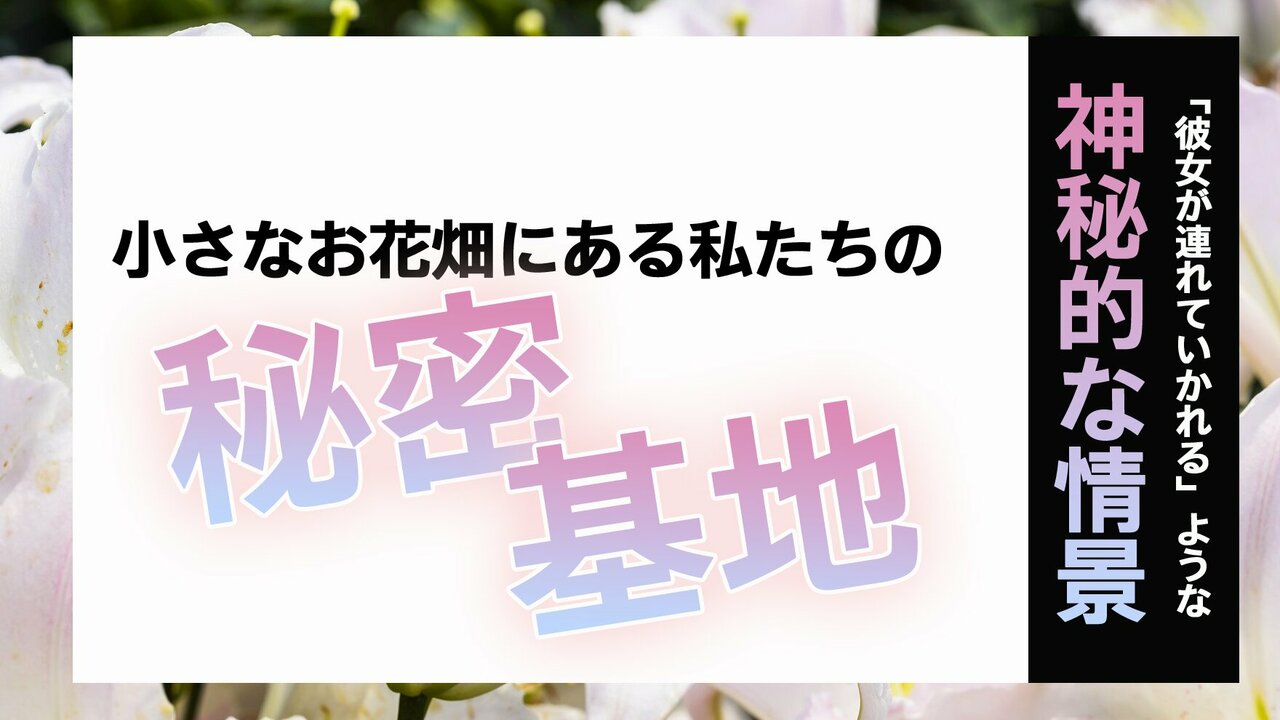駅から家まで自転車なら汗をかくような道のりを車はあっけなく進み、思い出に浸っているうちに家に着いていた。
正月ぶりの実家は…実家「も」相変わらずだった。良いことだ、と思う。なんとなく実家は変わってほしくない。社会に出てからそういう欲求が強くなっていた。
二階の自室も学生時代の様子から驚くほど変わっていない。誰も使っていないのだから当然と言えば当然だけど、それはつまり母が(父がやるわけないので)定期的に部屋を掃除してくれているということだから、素直にありがたく思う。
ベッドに倒れ込み、寝具に顔を埋めて深呼吸──。自分の匂いは……さすがに抜け落ちていたけれど、実家の洗剤の匂いがした。本能的に落ち着く匂いだ。
仰向けになり懐かしい天井をぼうっと眺める。どこからか反射して来た光が薄暗い天井に線を走らせていた。時折それが、ゆらゆらと瞬いている。まるで川面のきらめき──その揺らぎに焦点を合わせていると、頭のむこう側から睡魔が歩いてくる気配がした。
だめだ、だめだ、今後の過ごし方を考えなくてはいけないのだ。こんな時間から眠ってしまうわけにはいかない。…しかし意志に反して瞼は重みを増していく。
「ゆたかー。カレーすぐにあったまるからねー!」
母の声が聞こえ慌てて身を起こした。ドアを閉めなかったおかげで階下の声も届いたようだ。目の奥にある重い感じを散らすように顔を捏ねてから、立ち上がり部屋を出た。階段を下り台所へと入ると母はコンロの前で鍋の機嫌をとっていた。
「ああ、そうそうゆたか、ご飯食べてからなんだけど」
こちらを見ずに声を掛けてくる。
「うん、なに?」
お米くらいは自分でよそおうと食器棚を探りながら、私は気のない返事をした。