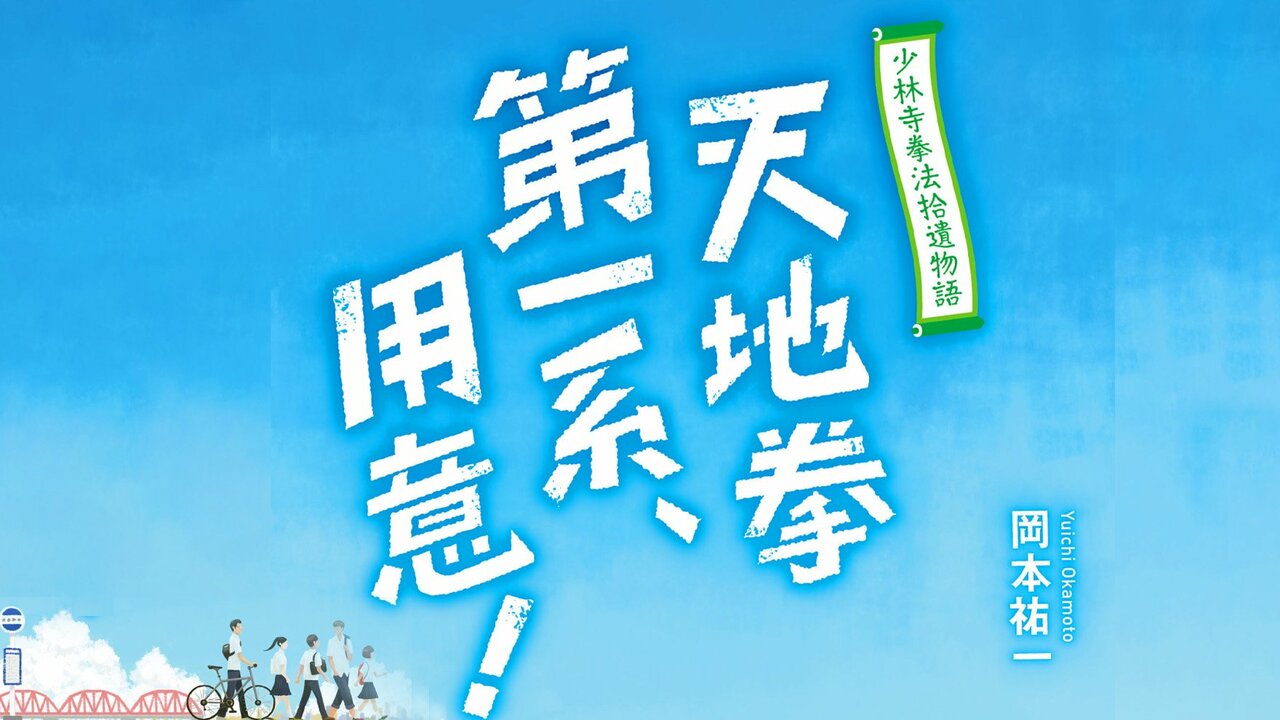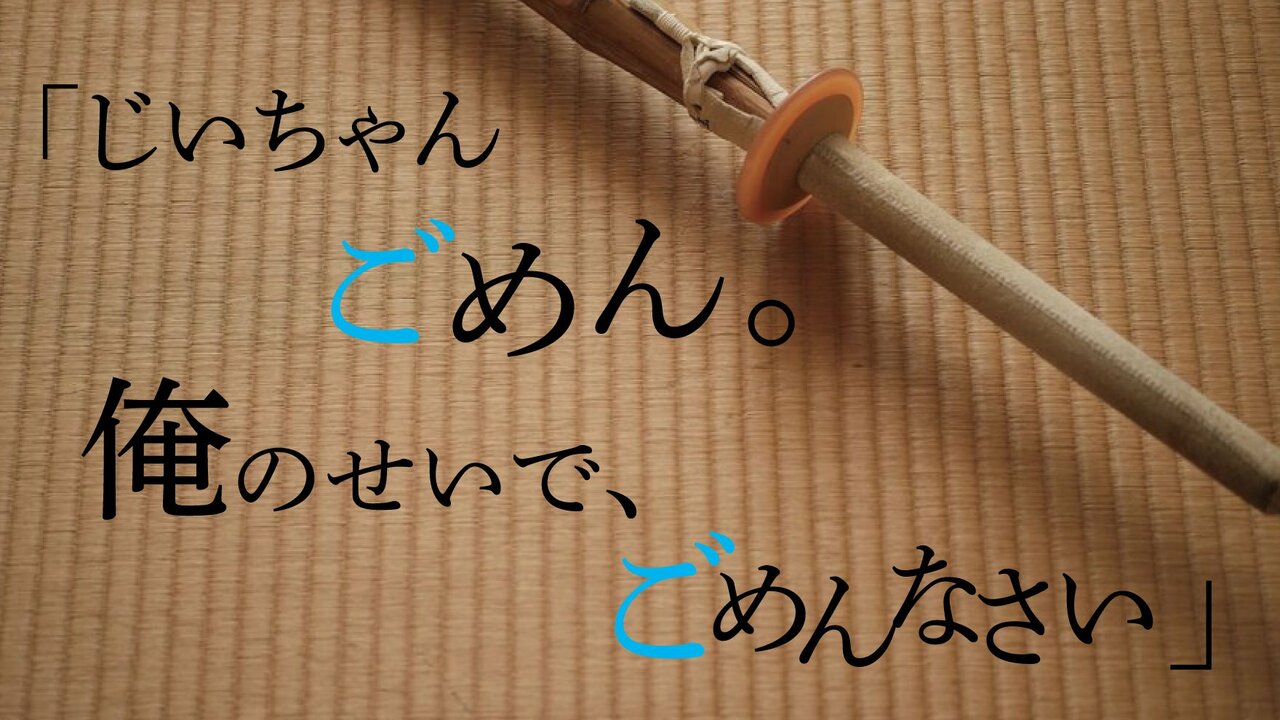破門 柘植虎次郎
午前中に試合会場を出るのは初めてだ。防具を提げた三本入りの竹刀袋が肩に食い込んでくる。防具ってこんなに重かったんだな。
すぐに家に帰る気にはなれず、どこかへ行く当てもなく、灰倉駅近くの児童公園でブランコに揺られていた。日曜の午後だというのに子供の姿が見えないのは、騒ぐな、ボールを使うなと規制が一々うるさいからだろう。その一方で、家でゲームばかりしているのは教育上よろしくない、子供は外で遊べというのだから、大人なんて身勝手なものだ。
でも、そのおかげで誰の目も気にせずにこうして落ち込んでいられる。身勝手な大人たちに振り回されているのに、そのおかげでなんて感謝しているのだから、俺に大人を批判する資格はない。
駅の方からかしましい声が聞こえてきた。重たい頭を上げると女子軟式テニス部がぞろぞろと歩いてくるのが見えた。白地に青のラインが入ったお揃いの部活ジャージは午前中に見上げた空によく似ていた。
今日の試合が終わったら有紀と二人で会う約束をしていた。最後まで勝ち残るつもりでいたから夕方に連絡するはずだったが、想定外の敗北で早く帰ってきてしまったので有紀が通りかかるのをここで待っていた。思っていたより早く会えたということは有紀も勝ち残れなかったのだろう。
俺と有紀が付き合っていることを知っている女子テニス部は色めき立ち、集団から押し出されるようにしてこちらに歩いてくる有紀を冷やかしながら学校へ帰って行った。
「どうだった」
「三回戦まで行ったんだけどね、負けちゃった」
「俺は二回戦で負けちまったよ」
納得できない反則で一本を取り消された挙句、誤審で負けた経緯を足元の地面に向かって説明した。有紀の顔を見ることはできなかった。
審判のせいで負けたなんて愚痴は武道家揃いの家では口が裂けても言えない。でも、誰かに聞いて欲しかった。この悔しさをわかってもらいたかった。
有紀は黙って聞いてくれた。そして、泣いてくれた。煮えたぎっていた腸は有紀の涙で少しだけ温度が下がった。