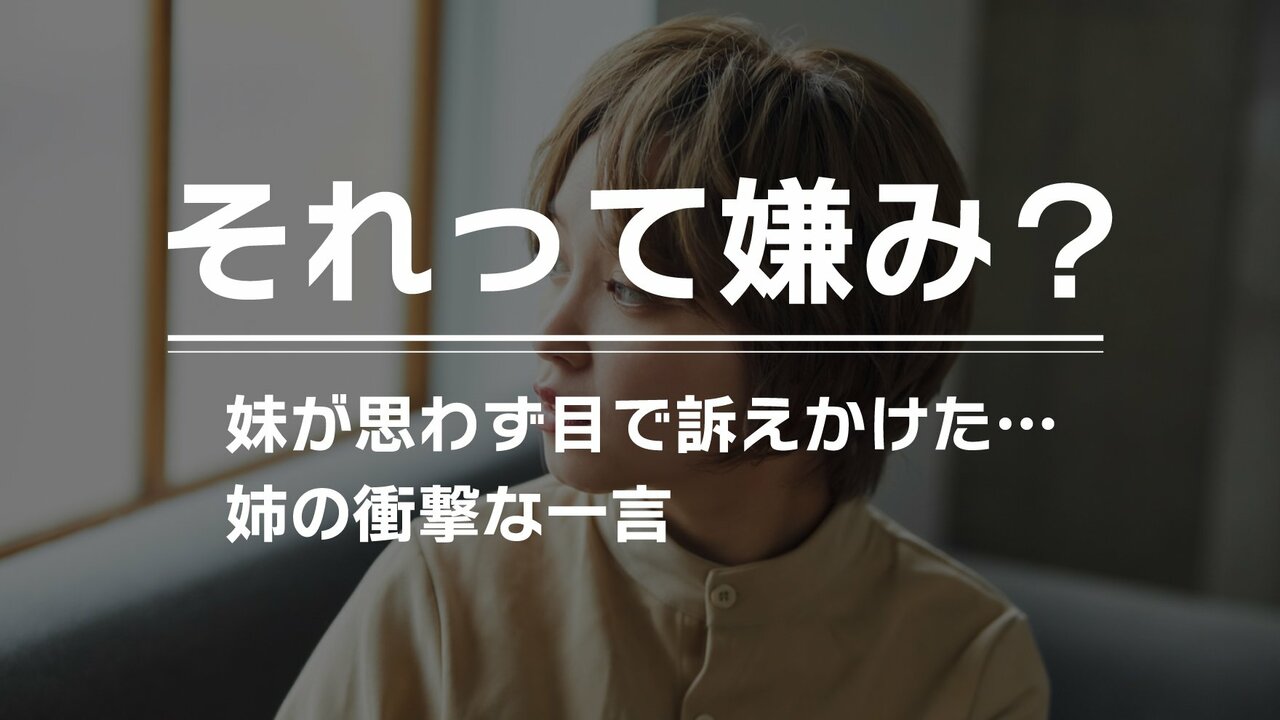四
「最近のお姉ちゃんを見てると、もう人生諦めたんかなって思うわ。何もしなくても時間は経ってくれるけど、そんなん虚しいないん」
この春、妹は公立大学の経営学部に合格し、日々粛々と勉学に励んでいる。
私はといえば母親に面と向かって反旗を翻しもできず、言われるがままにパーティの接待役を務めている。携帯を持っていないので夜遊び仲間から連絡が来るはずもなく、今さら夜の町に出ていく気にもなれない。CDやDVDで、長過ぎる時間を何とか埋める毎日だ。
「別にぃ。諦めたわけでも、捨てたわけでもないけど。これというて何もすることがないだけ」
ふぅん。私を見る妹の目が、蔑んでいるような憐れんでいるような、そんな気がして苛立ちが湧き上がる。
「映美は毎日が楽しそうやね。一生懸命に頑張ったあとには、ええことがいっぱい待ってるんや」
それって嫌み? 妹の目が聞いてくる。
「ほんま、これで一発逆転やよな。私は大学にいとも簡単に落ちて完璧なプータローやけど、あんたは我が家の期待の星やもんね」
「誰も期待なんかしてへんて。もししてるんやったら、裏方で役に立つってくらいやわ」
それでも、役に立つ頭脳と目標を持って日々を過ごしている映美が羨ましくもある。私はこの家での自分の存在が、どんどん小さくなっていくような気がする。さすがの親も、もう大学へ行けとは言わなくなった。無理だと察したのだろう。その判断は間違っていない。
「ほんとに、何のために塾の授業料を払ったのやら。こんなことなら大学に拘らないで、後継者としての修行をさせるんだった」
滅多に一緒に食事をしないのに、たまに同じ時間にテーブルに着くと説教の羅列だ。映美は母親も私をも見ようとせず、スマホを見ながらサラダに入った胡瓜をフォークで突いている。
私が携帯を持ちたいと言ったときは頑強に反対したのに、映美に対しては何がどう違うのか完全黙認だ。多分、信頼性の問題なんだろう。
「あなたは、ママたちが結婚して六年目にやっと生まれたの。お祖母ちゃんから子どもはまだかって散々言われてたから、妊娠が分かったときはほんとに嬉しかった。あんまり家を顧みなかったパパも、いそいそと帰ってくるようになったの。そのときに思うたの。この子はきっと、この家の希望になるって。跡取り跡取りって責め立てたお祖母ちゃんを、これで見返せるって思った」
私は、母親の敵討ちのために生まれてきたのか。血の繋がらない祖母と母親がどこを見てもそっくりな双子に思えた。だからといって、子どもの人生を決定してしまう権利が親にあるとは思えない。