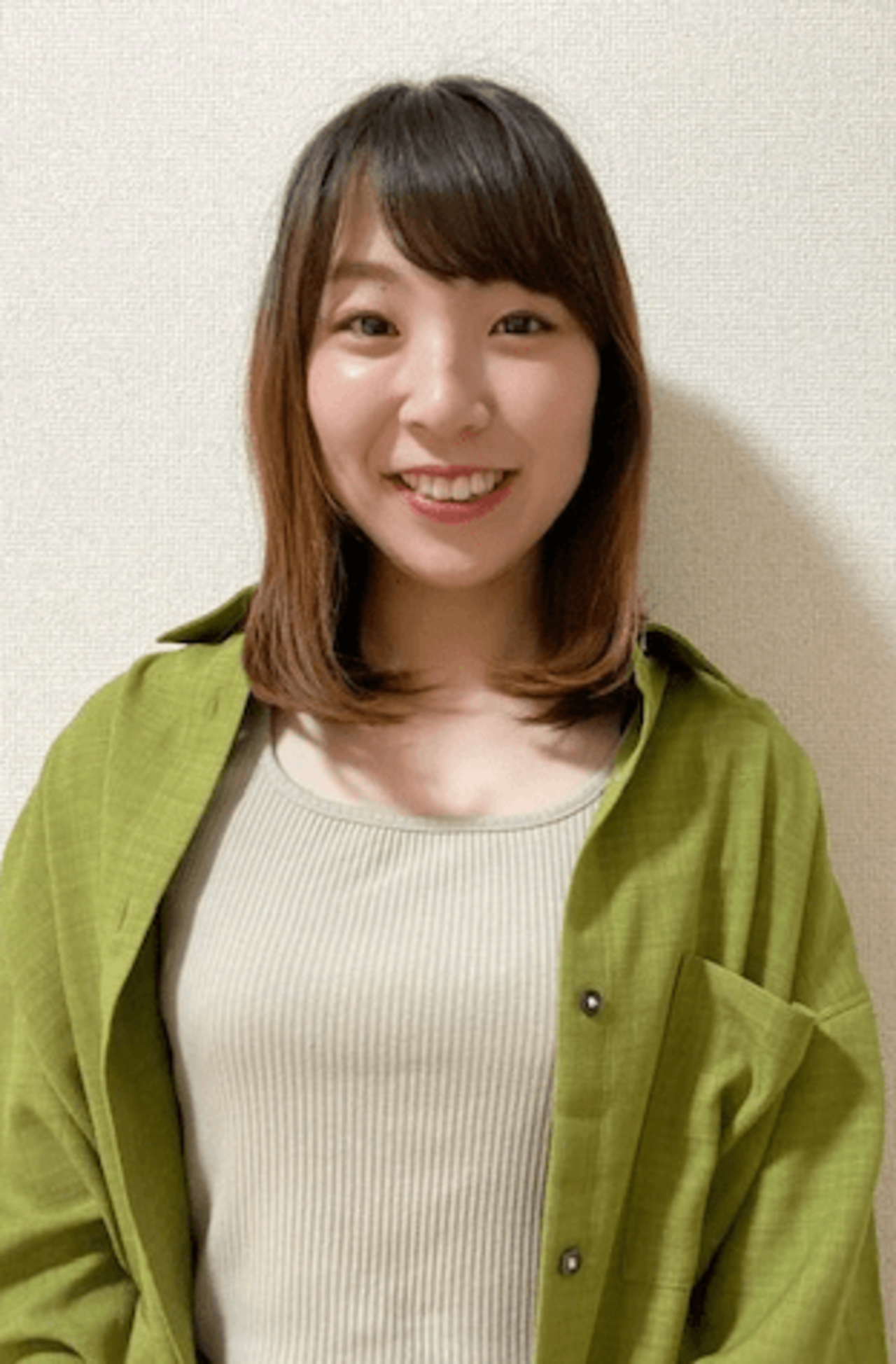雲と少年
彼のことをふと思い出した。大学生活は私が想像していたよりものんびりとしたものだった。大学では思いのほかすぐに友達もでき、高校でテニス部だったこともあって、その子らと一緒にテニスサークルに入った。高校までの部活とは違い、練習は週に二回で、サークルがない日はコンビニでアルバイトをしていた。毎日それなりに充実していたし、親元を離れて知らない土地で、新しいコミュニティーの中で生活できていることに誇らしい気持ちもしていた。
だが、時々ふと一人で散歩をしたくなるのだった。当時一人暮らしをしていたアパートは大きな川のすぐそばにあり、川のすぐ横には広く立派な土手があった。夕方、一人でその土手をぼーっとしながら散歩するのが私は好きだった。土手のことを立派だというのは変かもしれないが、春には菜の花や浜大根の花が土手一面に咲き、黄色と白で埋めつくされ、冬は風をさえぎるものがないのでとても寒かった。しかし、立派な土手だった。そんな土手で出会ったのが彼だった。
その日は晴れた空から穏やかな陽の光が照らす、春らしい天気だった。とても心地よい空気で、昼の大学の講義が終わった後、一人で土手を散歩していた。しばらく歩いたところで土手と河川敷をつなぐ階段に座って休憩しながら雲を眺める。私はこの土手で雲を眺めるのが好きで、その日は空一面にうろこ雲が広がっていた。
私が座っていた階段の七段ぐらい下のところに少年も座っており、彼も空を見上げていた。空には丸みをおびた可愛い雲たちが上下左右に均等な間隔を保ちながら整列しているように見える。でもよく見たら間隔は全然均等じゃなくて、ただそこに自由気ままに浮かんでいるだけなのに、人間の目が勝手にうろこに変換しているだけじゃないか、と勝手に名前をつけられた雲たちを見ながら、「人間ってほんと勝手……」と私が呟いたと同時に、振り向いた彼と目が合った。
彼はめがねをかけていた。茶色のふちの丸いレンズで、前髪がそのレンズにかかりそうになっていた。一四〇センチぐらいの背丈で、小学四年生か五年生ぐらいだろう。着ていたトレーナーの右胸に名札はついておらず、小さなくまの刺繍があった。見た目はいたって普通の小学生という感じなのだが、めがねの奥からのぞく瞳はとてもまっすぐでどこか独特な空気感をまとっており、私は吸い込まれそうになった。
そんな少年になぜか私は惹かれたのだった。彼はしゃべれなかった。私と話すときはいつも空書きかジェスチャーをつかっていた。土手の階段の半分ぐらいのところに二人で座り、空に向かって彼が人差し指で一文字ずつ言葉をかいていく。