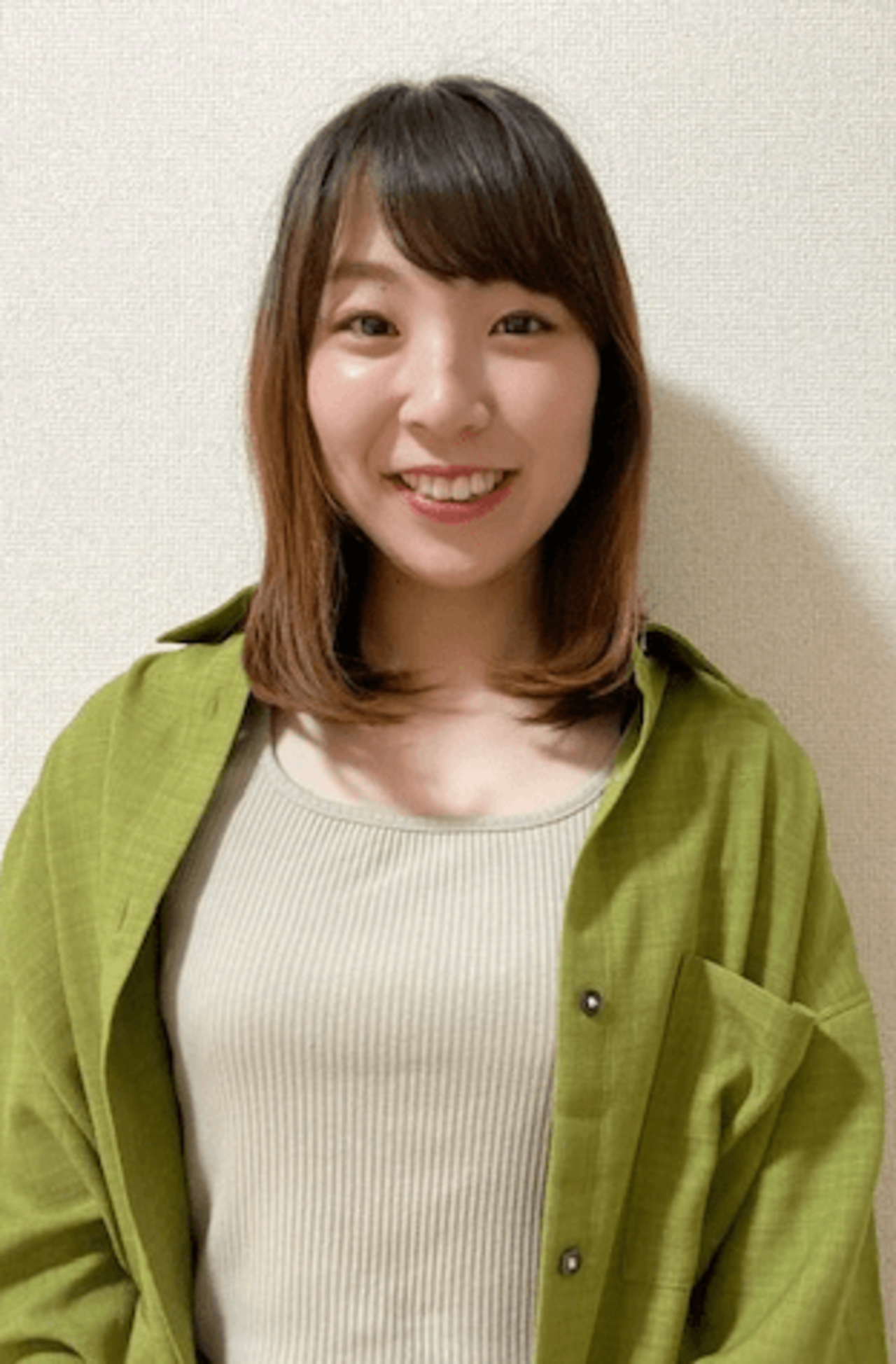ぼくのカレーライス
あたりはすっかり暗くなり、外の景色も闇に溶け込もうとしているのに家の横の電柱の明かりだけが空気を読まずに光り続けている。ぼくはカーテンをしめ、ベットに横になり目をとじた。
感染症は想像していたよりもあっという間に日本中に広がり、ぼくの変わらない日常にも変化が訪れた。まず、父が感染症が広がるのを防ぐためと、会社ではなく家で仕事をするようになった。朝から晩までいなかった父が家でパソコンを開いて仕事をしているのは不思議な感じだ。
朝、階段を降りるとリビングからコーヒーのにおいが漂っている。
「おはよう」
一人ソファに座る父が言うと、
「おはよう」
ぼくも返す。
この一年ずっと家にいたが、顔を見合わせて父と言葉を交わしたのはいつぶりだろう。ひきこもりの息子のことをどう思っているのだろうか。正面から目を合わせることができず横目に父が飲んでいたマグカップが見えた。どこか見覚えのあるものだった。
「えーーっと……」
どうにかして思い出したくて冷蔵庫の中をあさりながら頭をひねっていると、
「これ、サイズがちょうどいいんだ」
と父が言った。
あぁそうだ、思い出した。あの時もそう言っていた。
それはぼくが中学の時に父の誕生日にあげたものだった。誕生日の翌朝、朝のコーヒーを飲むのに一番いいサイズだ、と部活の朝練に行く前のリビングで母さんに話しているのが聞こえたのだった。あの時は、サイズじゃなくてぼくが選んだカップのデザインを褒めてよと小さく反論したことも思い出した。
「まだ使ってたんだ」
「サイズがいいからな」
ぼくはなにも返さなかったが、なんだか胸の中をあたたかいようなくすぐったいような、じんわり不思議な何かがとおっていった。