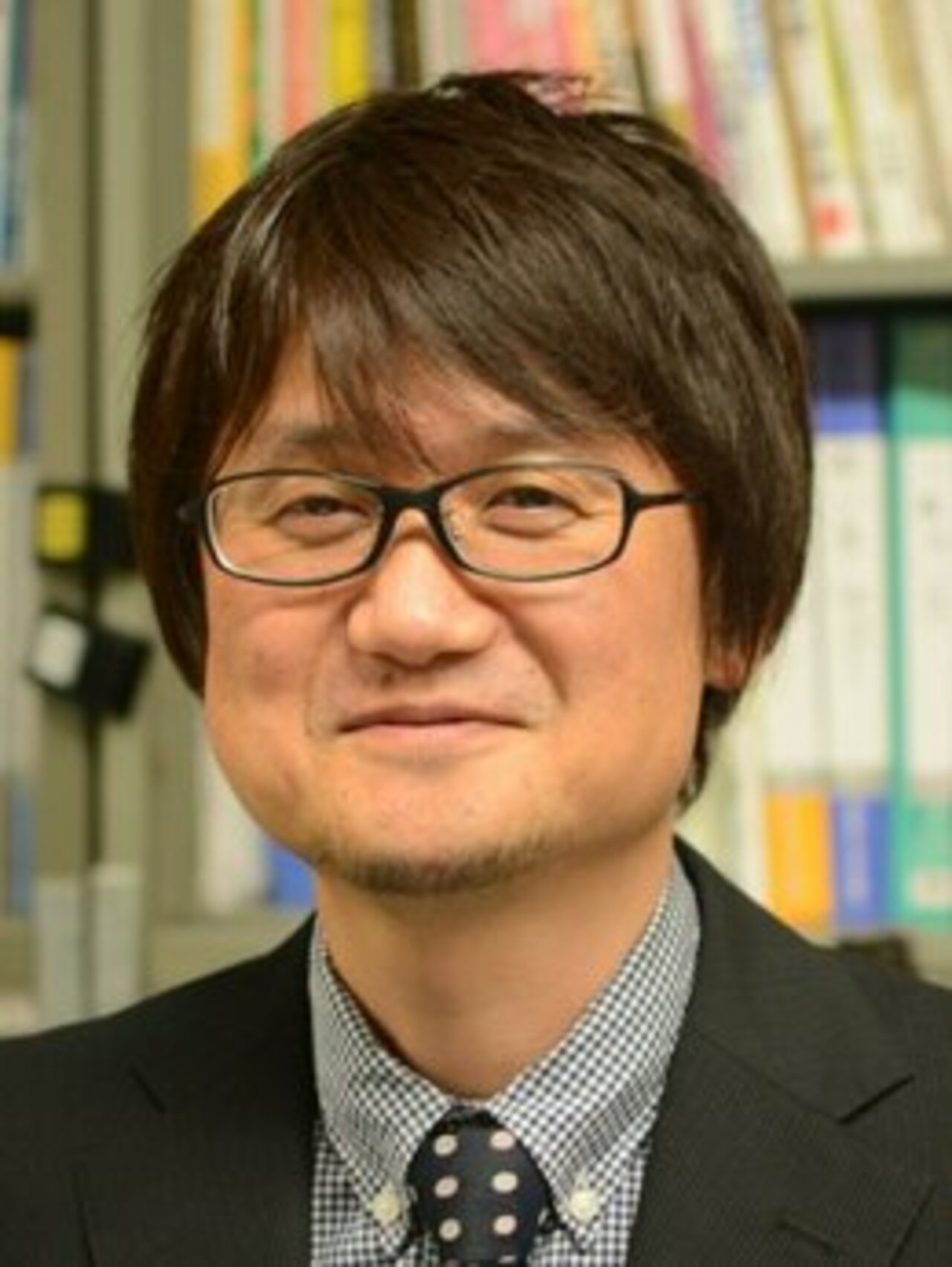2
鈴木由美は巣鴨に住んでいた。地下鉄を使えば職場まで20分足らずで行ける。できれば文京区、本当は港区白金台に住みたいが、それは今後の目標。生きる目標として残してある。ここに安住するつもりは毛頭ない。マンション価格が大きく違う。とりあえずの女性一人暮らしに巣鴨は適していた。
このあたりでは珍しい37階建て高層賃貸マンションの35階だ。自分の年齢と同じ階数だ。2年間の賃貸契約が終わると、決まって2階上層フロアを契約した。次の更新まであと1年半。次が最後の更新だ。その後は目標だった港区に住んでやる。
「待ってろよ、白金台」。35階の部屋から夜景を眺めた。
「"君のために輝いているよ"とか言いなさいよ」。
ひとりつぶやいてキッチンのキャビネットから、2リットルのガラス製の容器を取り出し、ワークトップに置いた。お手製の梅酒だ。キレイな梅が下半分にぎっしりと詰まっている。梅酒を氷の入ったグラスに注ぎ、2粒のビタミン剤を投げ入れた。マドラーで混ぜながら「なんでこうなっちゃったんだろ」とため息をついた。
地元の高校ではトップクラスの成績だった。親の「きちんと資格が取れる大学にしなさい」との言葉で、チャレンジ校の地元の国立大学医学部を諦め、お嬢様学校と言われた都内の女子大薬学部に進んだ。「男っぽさを直すために」という親の考えだった。医者は1人ずつしか治療できないが、薬は一度に多くの人達に恩恵を与えることができる。医者よりも崇高なことができる。という想いもあった。
同じ高校の田中や須藤が医学部に受かり、今では立派なお医者様。奴らと私でどちらが優秀かは、はっきりしている。それなのになんで今じゃ、奴らに頭下げなくちゃいけないの。頭の良し悪しで人生の序列が決まると思っていた。東大をトップに京大、阪大、九大と。
でも実際は違った。医学部がトップだった。どんな地方の私大出身者でも医者は医者。そこにぶら下がって仕事をもらっているのが私達製薬会社。医者の許可を得て臨床試験ができて、初めて薬ができあがる。なんであの時に気が付かなかったのか。今思えば何も考えていなかった。人生について。今ならわかる。過去にさかのぼって高校生の自分に言ってあげたいくらい。
「親の言葉を信じるな」って。
2粒のビタミン剤ごと梅酒をあおった。「チッ」、「なんなんだ」と言って、由美はグラスに残った氷をシンクにぶちまけた。由美はガラス容器を見て、もう一杯飲もうか考えていた。ガラス容器の底に沈んだ梅がテニスボールに見えた。由美は大学時代を思い出していた。
由美は女子大時代にテニスサークルに所属していた。他大学との交流が盛んで、派手好きな人が多いそのサークルは由美には合っていた。特に、由美のサークルは、医学系テニス協議会という団体に所属していた。都内でも有名な大学の医学部と薬学部が登録していた。月に1度は交流試合が行われた。女子ばかりの大学構内とは違う、華やかな雰囲気に由美は、のめり込んでいった。
学年が上がるにつれ大学の実験や実習が増え、多くの学生が活動に参加しなくなった。でも由美は違った。サークル活動にも手を抜かず3年生になると幹事的役割を担うようになった。そこで慶生大学医学部の幹事役の4年生、タクヤと出会った。学年が1つ上ながら偉ぶらず謙虚で自己主張のできないタクヤを弟のように感じながら好きになっていった。
夏の合同合宿の最終日。例年のように宴会場で打ち上げをしていた。各大学の幹事が前に呼ばれ、由美とタクヤも並び立っていた。参加者からお礼の拍手をもらい、中締めが終わった。廊下に出るとタクヤが一人でそこにいた。勇気を振り絞り、それとなくタクヤに近づき声をかけた。
「お疲れ様でした」
タクヤは由美を見てすぐ目をそらした。そして「……お疲れ様でした」と誰に向けたのか分からないような小さな声で呟いた。
「来年も幹事役ですか?」
「……いや、もう来ないんだ。今月でやめるんだ。今月というか、この合宿で辞めるんだ。この会での活動は」
「この会でのって、ことは?」
「……そう。この会での活動は辞めて、他の会に移るんだ」
タクヤは由美を見てこう言った。
「ごめんね。どうしても親が辞めろって言うんだ。テニスをじゃなくて、この会を。すごく言いにくいけど。純粋に医学部だけの団体があって、うちの父親もそっちで活動してたんだ。だから」
タクヤは眉と眉の間のこめかみ部分を右手でこすっていた。
結局そうなんだ。医学部生にしてみたら薬学部生は下層階級なんだ。
「そうよね」としか言葉がでなかった。罵声を浴びせてやりたかった。でも天に唾する、そんな言葉が頭に浮かんだ。医療現場での序列で人間の価値を決めつけていたのは自分自身ではないのか。理学療法士や管理栄養士を見下していなかっただろうか。努力して上を目指すとは、下の人間を蹴落とすことだと思っていたのではないか。
「がんばってね」とだけ言って宴会場に戻った。
宴会場ではいくつものグループができ、皆楽しそうに笑い合っていた。輪の中に入る気にはなれず、ノートの余白のような端の席に一人きりで座った。テーブルには、皆のためにと用意した梅酒の入った2リットルのガラス製の容器があった。しわだらけの梅が底に沈んでいた。テニスボールが小さく縮んでしまったかのように。
「おはよう、ケントくん。進んでる?」
ケントの机に近づき、毎朝繰り返す言葉を口にした。
「ええ、少しずつですけど、分かってきましたよ」
椅子に座ったケントがこちらを見上げた。その顔はいつもと違い頼もしげに見えた。叩けばその分、頑張れる。ヒトなんて所詮そんなものだ。カツを入れさえすればいいんだと、由美は自分の指導方法が間違っていないことに満足した。
「でしょ。基準があるんだから。それに従って商品を考えればいいだけだから。だって所詮、食品でしょ。薬と違うんだから。薬にももちろん基準があるわよ。研究の仕方とか細かくね。まずは小動物での実験、次に犬、猿、健常者の順みたいにね。でも一番大事なのは有効成分が新しいってことでしょ。その開発に10年、20年と研究が必要なんだから」
そうですけど、とケントが言ったようだが関係ない。
「薬と違うでしょ、食品は。なんとなくの効果が論文で示されていれば、健康食品なんて簡単でしょ。ハラールも一緒よね。健康食品の原材料を確認して、そこからハラールでないものを除けばいいだけでしょ。例えば豚肉とかアルコールとか。それくらい私だって分かってますからね。ノー・プロブレムよ」」
急にケントが椅子から立ち上がった。そして怪訝そうに言った。
「……どうもマレーシアが作った基準があって……」
「ほら簡単じゃない。その基準に従って商品を設計してみて」
ケントの肩を押して椅子に座らせた。ケントは目をそらし机の隅を見ていた。何かを言ったようだが、そんな小さな声では聞こえない。由美はケントを睨みつけた。
「……してみてって言われても……」と聞こえないくらいの小さな声でケントが言った。
その小さな声は「要求をすべて受け入れます」に等しいものだ。
「だって、ケントくん。食品の表示基準とか、特定保健用食品いわゆるトクホとかの基準を勉強してきてるんでしょ?」
ケントが「……基準があいまいのようで……」と言った。
「基準があいまいって、そんなの変でしょ」
「……そうですけど……」と言って、ケントは視線をそらし窓のほうを向いた。由美も同じように窓の外を見た。しばらくしてからケントが外を指差して「課長。あれ見てください」と言った。何か重要な手がかりを見つけた刑事のような顔で。
大通りを隔てたむこうには食品工場があった。川沿いの工業団地ではよくある風景だ。
「看板にISO9001認証取得って書いてあります……あれを見てどう思いますか?」
「どう思うって、この工場はすごいぞって、アピールしてるんじゃない。取引業者に対してなのか、一般の人に対してなのか、わからないけど。なんか基準をクリアして、そこで生産されたものは立派なんじゃないのかしら。それが何なの?」
「……ISOって食品工場での世界的な衛生基準です……どんだけ凄いかって、みんな知らないと思うんです」と言ってケントがこちらを見た。「言いたいことをご想像ください」と言わんばかりの顔だ。
「……ISOって一般の人にしてみたら中身なんかわからない。けど、さぞ凄いんだろうな、と思わされている。つまり厳密な基準があるけどそんなの消費者にしてみたら無関心……」とケントが言った。さっきの自信はどこに消えたのか、さえない表情で、頭を掻きながら。そして、下を向きしばらく黙っていた。
「……僕が言いたかったのは、ISOもハラールも同じで、一般の人にはよく分からないものだということで……」と、小さな声が消えてなくなった。
「ほら、ケントくん。やっぱりどこかにしっかりとした基準があるのよ。誰か知らないけど、専門家は基準を知ってて厳密にチェックしてるのよ。間違いないわ。だからこそ、ハラールを認証する団体があるんでしょ。大丈夫よ。最後は彼らに任せましょ」
そうは言ったものの若干の不安がある。ケントの言うことは当たっているのかもしれない。基準という言葉は魔法の言葉だ。基準をクリアと言えばなんだか凄いと感じる。その基準がおそまつなものであっても。責任を負うことになるのは我が部署だ。少し慎重になった方が良いのだろうかと思った。
でも、そうだろうか。心配することなどないとも思った。基準の良し悪しなど気にすることはない。利用できることは最大限利用する。トクホもハラールも。時間は有限だ。効率的に使わないといけない。私の鮮度が落ちる前に成果を挙げなければと思った。35歳のうちにできることは何でもする。結婚もする。今年の元旦にそう決めた。決めたことをやる。自己実現が私の座右の銘だ。だからこそ、この地位までたどり着けたのだ。
由美はこれまでの成功体験を振り返っていた。
就職活動を始めた大学5年生の時だ。専門を活かすため調剤薬局を志望する友人が多かった。一方で、給与の良さに惹かれて外資系製薬会社のMRと呼ばれる営業担当者を目指す友達もいたが、医者を相手に営業活動する気持ちにはなれなかった。先輩に聞きネットで調べ、「製薬会社の開発部門」に狙いを定めた。
"海外事業部とも連携できます"と謳うパンフレットを見たのがきっかけだ。英語も活かせるならと狙いを定めたが、入社1年目から開発本部に配属される会社など見つからなかった。そんななか、エリザス製薬は違った。その可能性を口頭で約束してくれた。ただし病院で処方される薬ではなく、薬局やコンビニでも購入できる一般薬の開発担当者だった。
それで充分だった。それが最初の小さなステップだった。
入社して5年間はがむしゃらに働いた。同期入社の仲間からの誘いは常に断った。
「自分のことしか考えていない」、「協調性がない」などと陰口を言われたが気にしなかった。そのうち同期から誘われることはなくなった。それでもよかった。男性に負けたくないという想いもあった。そのかいあって、30歳で異例の一般薬開発部門のリーダーに抜擢された。自分の心の想いのまま行動し、成功したのだ。
その後、高齢化社会で高騰した医療費を削減するため「セルフメディケーション」という言葉が使われ始めた。医者に頼らず食事に気をつけ健康食品も有効に使おうとの考えだ。エリザス製薬も健康食品部門を立ち上げた。健康食品に親和性の高い一般薬部門の中から由美が選抜された。
「女性が活躍できるエリザス製薬! 35歳女性課長の誕生」と華々しい報道がなされた。
由美は改めてISO9001認証取得と書かれた食品工場を眺めた。
食品工場の入り口のすぐ横には大きな駐車場があった。出荷するのに使うのだろう。今まで意識して見たことはなかった。1階からだと柵で視界がさえぎられる。駐車場の横の端にはフェンスらしきものが見えた。形状や大きさから考えればテニスコートかもしれない。従業員が使う福利厚生用なのだろう。久しぶりにテニスでもやろうと思った。
椅子に座ったケントは、いつものようにペットボトルを右手で握り、左肩を叩いていた。
「ところでケントくん。スポーツ、何やってたの?」
驚いた顔でケントが言った。「えっ……突然ですね……」
「突然の閃きが新商品を創り出す。誰かが言ってたわよね。有名な誰だかが。そんな昔の人の名前、知らないけど。で、どうなの?」
「……部活とかやってなくて……テニスを少し……」
「知らなかったわ」と言って、由美はケントを机の横に立たせた。大学時代に会ったタクヤとどことなく似ている。あまり筋肉がなく細身だという姿かたちだけではない。頼りないところも。自分の意見をはっきりと言えないところも。
夏の合宿での、タクヤとのミックスダブルスを思い出した。緊張のファーストサーブ。「フィフティーン・ラブ!」と審判の声が聞こえた。フォワードのタクヤが振り返った。その顔はここにいるケントそっくりだ。
ケントは私のいいパートナーになれるのかもしれない。もし、ケントがテニスをして体を鍛えて日に焼けて、仕事で成功もして自信がつけば、いい男になるかもしれない。自分より能力が下、地位が下くらいが私にはいいのかもと思った。そんな男を育て上げるのも女の喜びかもしれないと由美は思った。そうだ。テニスにはいい思い出も沢山ある。ラケットを振る真似をしてみた。
「閃きよ! この閃きを大事にしなきゃね」
今しかない。もう二度と無いチャンスかもしれない。ケントにそっと近づいた。耳元で「ハラールについて情報交換会します。今夜」とささやいた。床に落としたペットボトルを拾いながら「ですよね」とケントが言った。両耳だけが異様に赤く、審判が使う赤いホイッスルを連想させた。
「サーティーン・ラブ!」と審判の声が聞こえた。
右手の拳に力が入った。これほど力を入れて右の拳を握ったのはいつぶりだろう。
テニスラケットの感触が甦ってきた。
2人は巣鴨駅近くの居酒屋にいた。全席個室をうりにする店の、トイレに一番近い席にいた。
「ケントくん。普段は飲み会には参加しないそうね。なんで?」
由美は梅酒ソーダ割りの梅をマドラーで転がしながら聞いた。
ケントはほろ酔いで気持ちが良いのか柔らかな笑顔で答えた。
「由美さんはどうですか? 会社の人達と飲んで楽しいですか?」
「実を言うと私も大嫌いなのよ。同僚とか会社の人達との飲みは」
「ですよね。なんであんなに頻繁に飲み会するんですかね。職場の人の愚痴ばっかりですよ。"君はどう思うんだ?"とか聞かれても本心は言えないですよ。相手の意図することとずれた発言だと、後々問題になりますからね」
ケントは普段と違い饒舌だった。声のトーンも少し高めだ。会社での顔と違い、目尻が下がり口角が上がり綺麗な白い歯が見えていた。白いTシャツに薄いブルーの麻のジャケットが爽やかさを増していた。
「実は、飲み会に参加しないもうひとつの大きな理由があって、お酒あんまり飲めないですよね」と、ケントは3杯目のジンジャーハイボールのグラスを持ち上げた。
「でも、そう言うケントくんがこうやって私と飲んでくれてることに感謝よね」
「ハラールプロジェクトは副業的な感じですよね。当たればオッケイ。失敗しても、まぁいっかみたいな」
「いわゆるアングラ。アンダーグラウンドな活動に近いわよね。でも、もしこの分野でヒット商品を出したら、私達は有名人よ。社内で表彰されちゃうかもね」
由美は枝豆を横にし、両端を右手と左手でつまみ、賞状を渡すようにケントに差し出した。ケントはていねいに両手で受け取った。
「私達ラッキーかもね。だって、ハラール基準をクリアさせる会社を見つけたんでしょ?」
「ええ。一箇所、引っかかりのありそうなのを見つけたんです。大学時代の友人が関わってそうなんで。なにやら怪しげですけど。」
「いいじゃない。知り合いがいるなんて。運命を信じなさい」
由美は枝豆を鞘から半分出したまま、ケントの口元に持っていった。さすがに口を持っていけないと、ケントは右手を顔の前に出した。酒に酔ったからなのか、恥ずかしいからなのか、分からないほど顔が赤みをおびていた。
「正直、不思議ですよ。ハラールという基準がよく分からないものに対して、基準をクリアさせる認証団体がたくさんあるんですから」とケントが言った。
「いいじゃないの。たくさんあることはニーズがあるってこと。つまり、商品ニーズもあるってことでしょ。むずかしいことは専門家に任せるのが一番よ」
「ですよね。今度そこに行きますので」
「ケントくんのそういうポジティブさが素敵ね。若さなのかもね」
「そんなことないですよ。由美課長も若いじゃないですか」
由美は頭を下げ左右に振ってみた。
可愛らしさをアピールするにはもってこいの動作だと、なにかの雑誌で読んだことがある。
「全然よ。私なんかダメダメよ。叶えたい夢はたくさんあったけど。どれも果たせなくて。綺麗でいたいっていう夢もあるけど現実は厳しいものね」
由美は梅酒ソーダの梅を箸で取り出し、小皿にのせた。
「見てみて。シワシワでしょ。もとはハリのあるツヤツヤの表面だったのが、周りの環境にエキスを吸い取られてシワシワよ。環境は大事よね。いくらウメさんが頑張ったところで濃い溶液にドボンって入っちゃったらもう最後。こうなっちゃうのよ」
口に出す言葉は何でもよかった。ケントの表情を見ながら次の行動に出るタイミングを見計らった。背筋を伸ばし、ケントを見下ろして言った。
「結構飲んだし食べたわね。でもなんだか話し足りないし、もう少しだけ付き合いなさいよ」
顔全体が赤く染まったケントの耳はもうこれ以上に赤くなることはなさそうだった。
「ですよね」と小さな声で言ってケントはうなずいた。
「フォーティーン・ラブ!」と審判の声が聞こえた。
マドラーをグラスに差し入れ、目を閉じた。こうやって試合に勝ち進んだのよねと思った。
会計を済ませたケントの左腕に右手をさし入れ引きずり出すように店を出た。
35階の部屋でソファに深く座ったケントに聞いた。
「イスラーム教徒はお酒飲めないわけでしょ?」
「違いますよ。飲めないんじゃなくて、飲まないんですよ」
「私には違いがわからないわ。じゃどうやってストレス発散してるのかしらね。私達はこうしてお酒飲んで、いい気分でフワッとなって、日常のストレスを発散してるわけじゃない。それをできない、いや、していないってことはお酒以上に楽しいことを知ってるんじゃないかしら。それって何なんのかしら?」
「難しいですね。そこまで深く考えませんでしたね。お酒以上に楽しいことですか?」
「こういうことかしら」
由美はケントにキスをした。若い男子の柔らかい唇を吸い上げた。舌を挿入し、ケントの舌と絡めた。イスラーム教徒はお酒も飲まずにこんなことができるんだ。宗教の力は凄いなと思った。なんだかいやらしいなと思った。ケントの股間に手を伸ばした。
私ならお酒なしじゃこんなことできない。酒の神様ありがとうと思った。ケントのもの触っていると大学時代が思い出された。テニスラケットを握っているように思えた。これで試合したら勝てるはずと思った。審判の声が聞こえた。
「ファーストゲーム・由美!」。
観客席からスタンディング・オベーションが聞こえた。
「いいこと。2人の関係は会社には内緒よ。だって今後ね、私もケントくんも出世してどこかから引き抜き、ヘッドハンティングがあるかもしれないじゃない。オファーは当然製薬会社よね。でも私達2人が結ばれてる。つながってるとなると、それは受けられないの。製薬会社の不文律で、付き合う2人は同じ会社にしか勤務できないの。だってそうでしょ。例えばよ、結婚してる2人が、違う製薬会社で勤務しててごらんなさい。ライバル会社で社外秘なことを知っている2人が、毎日同じ家に帰ってきて話をして、『今日どうだった?』『何も言えないの』。なんてありえないでしょ。だから私達の関係がバレちゃうと、ビッグオファーを無駄にしちゃうの。ねぇわかった。バレないことも大事よ。そして、ここでは仕事の話はしない。女と男なのよ。いいかしら」
「ですよね」と頷くケントの頭をなでた。
「由美トゥーサーブ」と聞こえた。
またケントを強く抱きしめた。