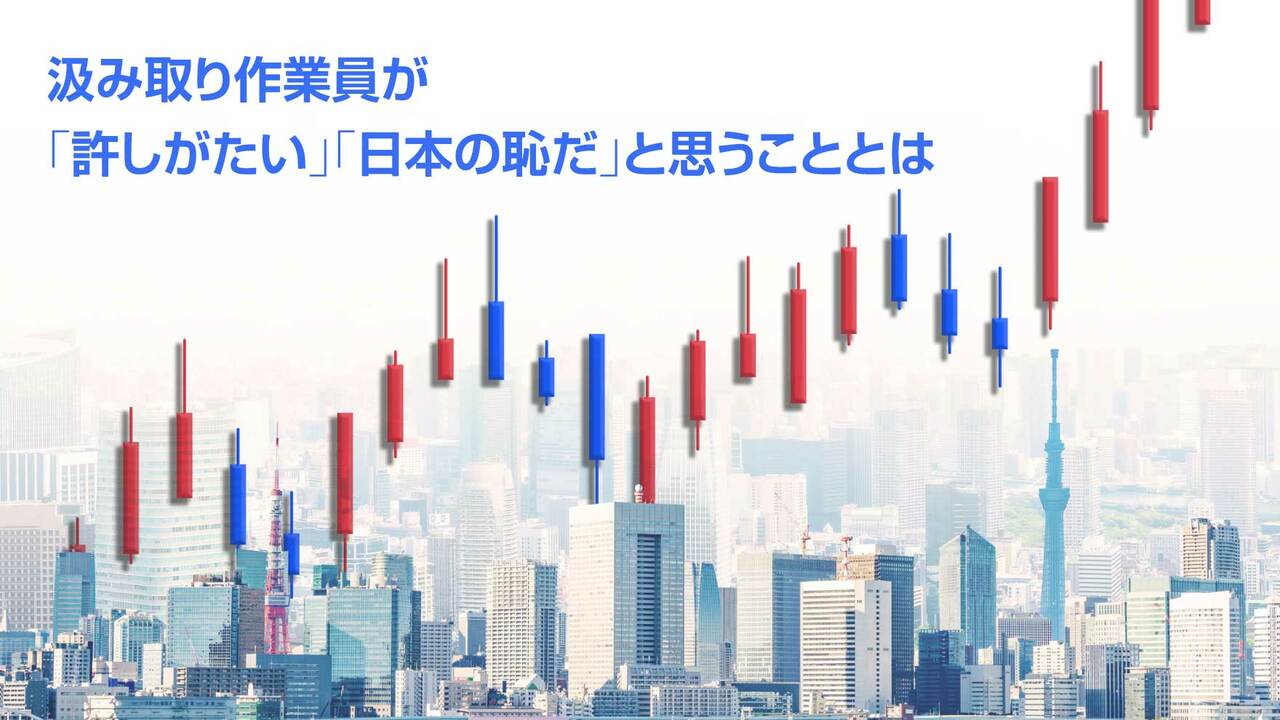女の子たちと朝帰り
末吉には、夜家に帰らない日がたびたびある。むしろ、どちらかというと、その日の内に帰宅することは珍しい。俗に言う午前様の常習犯だ。
フミは今日も、明け方の四時半頃になると、木綿の着物の上に真っ白でシワ一つない、丁寧にアイロンをかけた割烹着を着て出かける。そして井戸水で冷やしておいたラムネのビン一本と開栓するための玉押しを割烹着のポケットに入れて赤線に向かう。すると向こうから、まだ夜が明けきらない歓楽街の細いゴミゴミした通りを、末吉が女の子たちに腕を組まれて、フラウラ、ヨロヨロしながら、ニタついた顔をして帰ってくるのだった。
フミは、穏やかに微笑みながら、「送ってくれてありがとう。ここでもういいわ。お休みなさい」と女の子たちに言うと、「はい、あなた」と言って、持ってきたラムネの口に玉押しをあてて、慣れた手つきでビー玉を押し込むと、泡の収まるのを待って末吉に渡す。
末吉は、左手を女の子の肩に置いたままで、右手でビンを持って一口飲むと、飲み残したラムネを女の子に渡して、「あとは、あ・げ・る」と、お茶目に甘えた声で言って、クルリとフミの方に向き直って、「ただいま、帰還しました」とふざけて、しかもかなりふらつきながら、兵隊がする敬礼の真似をして言った。
フミは、静かに、ゆっくりと、
「お か え り な さ い」
と言うと、重い肥桶を天秤棒で担いで鍛えられた、末吉の太く長い腕を自分の肩に乗せて、今にも押し潰されそうになりながら、家に帰って行くのだった。
女の子の一人美香は、そんな末吉とフミを見送りながら、
「あの奥さんには敵わないわよね。どうしたらあんな風に平気でいられるのかしら。私だったら怒鳴り散らして、パヒッ、ピタ、バシッて、引っぱたいているところよ」
と言うと、もう一人の子、早苗も、
「会長さんも、悪いことをしているなんて、これっぽっちも思ってないみたいだし。少しは、申し訳ないと思わないのかしら。まあ、そのおかげでアフターで遊ばせてもらって、お小遣いまでもらえるんだから、いいんだけどさ」
と言うと、舌をペロッと出して、さっき別れ際に早苗の胸に末吉が挟み込んだ千円札を取り出して、自分の鼻の頭に擦り付けて、おどけて見せた。すると今度は美香が、股間からクチャクチャになった千円札を引っ張り出して、真っ赤な唇に当てて、帰って行く末吉の方に投げキッスした。
そして、「眠くなってきたから、私たちも帰ろうか」と言うと、二人は朝日で明るくなって、捨てられたゴミや酔っ払いが吐いたゲロの跡が、よりクッキリと汚く目立つようになった道を通って、赤線の路地裏に再び消えていった。