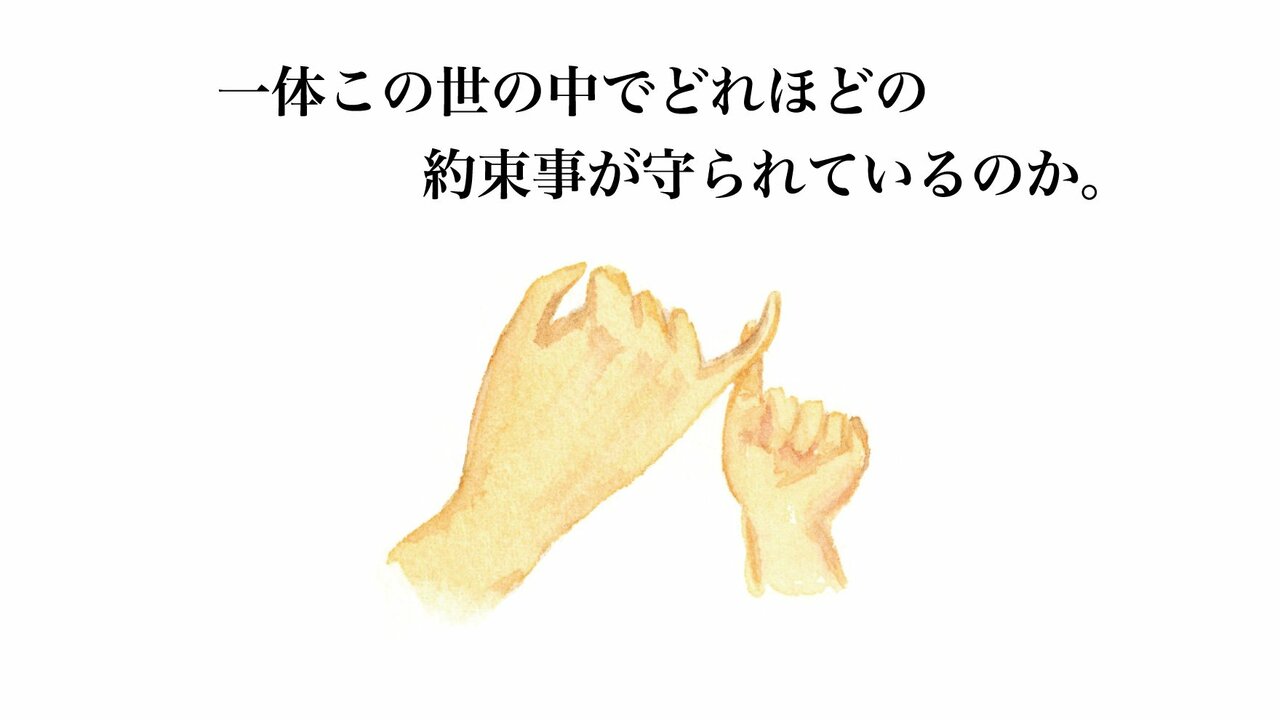美琴には俄かに信じられなかった。御伽噺のように覚えていたマドンナの絵にまつわる話は、少女時代の美琴にとってあまり愉快な物語ではなかった。今ここでまた思い出す日が来るとは、そして母に想いを寄せた画家に自分が絵を教わるようになるとは、運命の糸が絡まり合っているみたいだ。ただその舞台となった浜松を離れ一人暮らしを続けているうちに、美琴は母という人を客観的に見ることができるようになっていた。
十和子の笑顔や明るい声は家族皆にとって元気の源だった。結婚後は近所の町工場でパート事務員として働いていたが、家事との両立で忙しい中でもあまり怒った顔は覚えていない。
後年は義母の介護も担っていたが、書道やフラダンスなどの趣味にも勤しんでいた。しかし当然であるが完璧な人間だった訳ではない。彼女は美琴の容姿をけなすようなことは言わなかったが、ときには「お父さんに似て、理屈っぽい」などと突き放し、娘の気持ちを理解しようとしないときもあり、思春期の美琴は寂しさを味わった。
洋服を一緒に選ぶ時は楽しそうで、たまにはミシンでブラウスやスカートを手作りしてくれた。言葉の足りない部分もあった母だが、「美琴とは気が合わない」と言いながらも、最終的には娘の望む進学や就職を応援し父を説得してくれた。
「蔦先生が母を好きになった理由は、顔が一番ですか?」
「うーん、人の美しさっていうのはね、君が男性を見るときもそうだと思うけど、その人の考え方や感じ方が姿かたちに滲み出ると僕は思うんだ」
「心が美しい人が美しいってやつですか?」
「心の美しさって言っちゃうと抽象的だけど、彼女の場合はフェアなところや、潔いところかな。十和子さんは貧乏画家の僕を見下すような態度は決して見せず、純粋に僕の絵を見てくれた。他人からどう思われるかとはあまり考えずに、自分の価値観で決断して、恨み言は言わない人だった。そうだな、君の笑顔は彼女によく似ているよ。そして君にはお母さんとはまた違う、タフな美しさもある」
「タフって、一応ほめ言葉でしょうか」
美琴は首を傾げ、蔦の両目の虹彩が揺れるのを見つめた。ふと、母は父とは異なるタイプの蔦のことが結構好きだったのではないか、と思えてきた。嫌いな人のモデルになったり、一度でもデートに行ったりするような人ではない。別の男のことを打ち明け、蔦の反応を確かめたかったのかもしれない。そこであっけなく引き下がった彼は、もしかしたら[意気地なし]とみなされたのかもしれない。