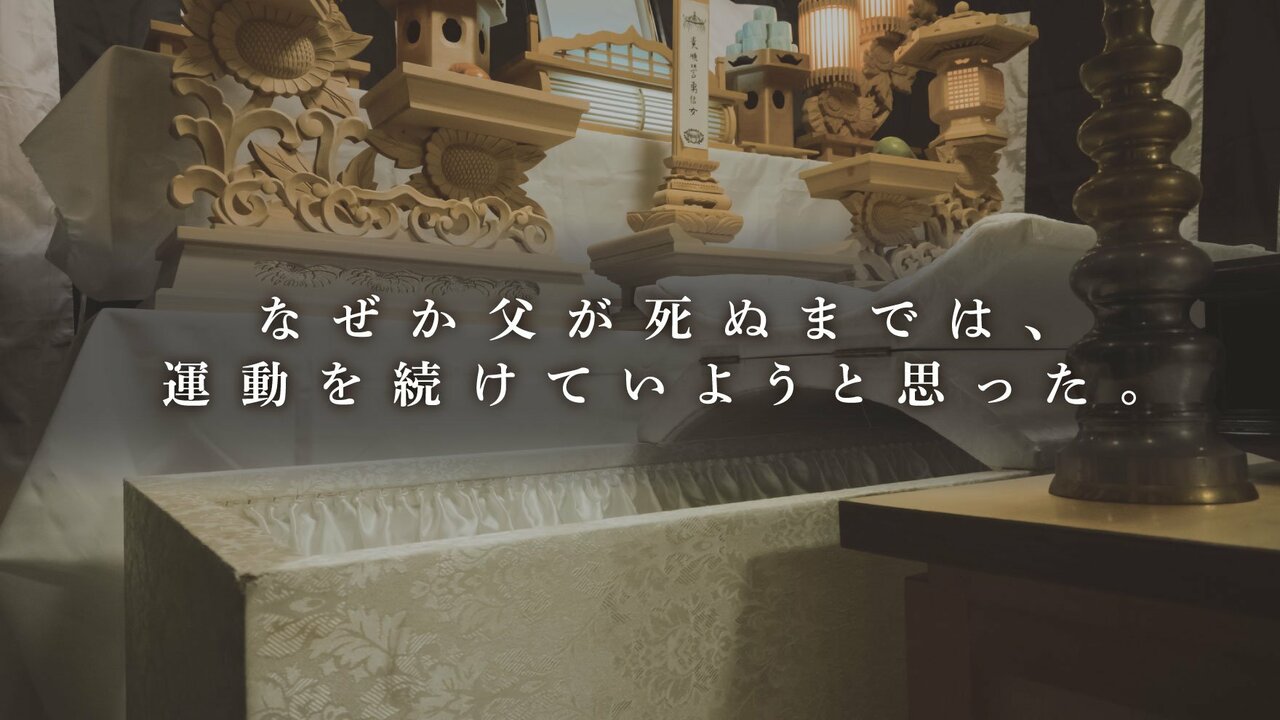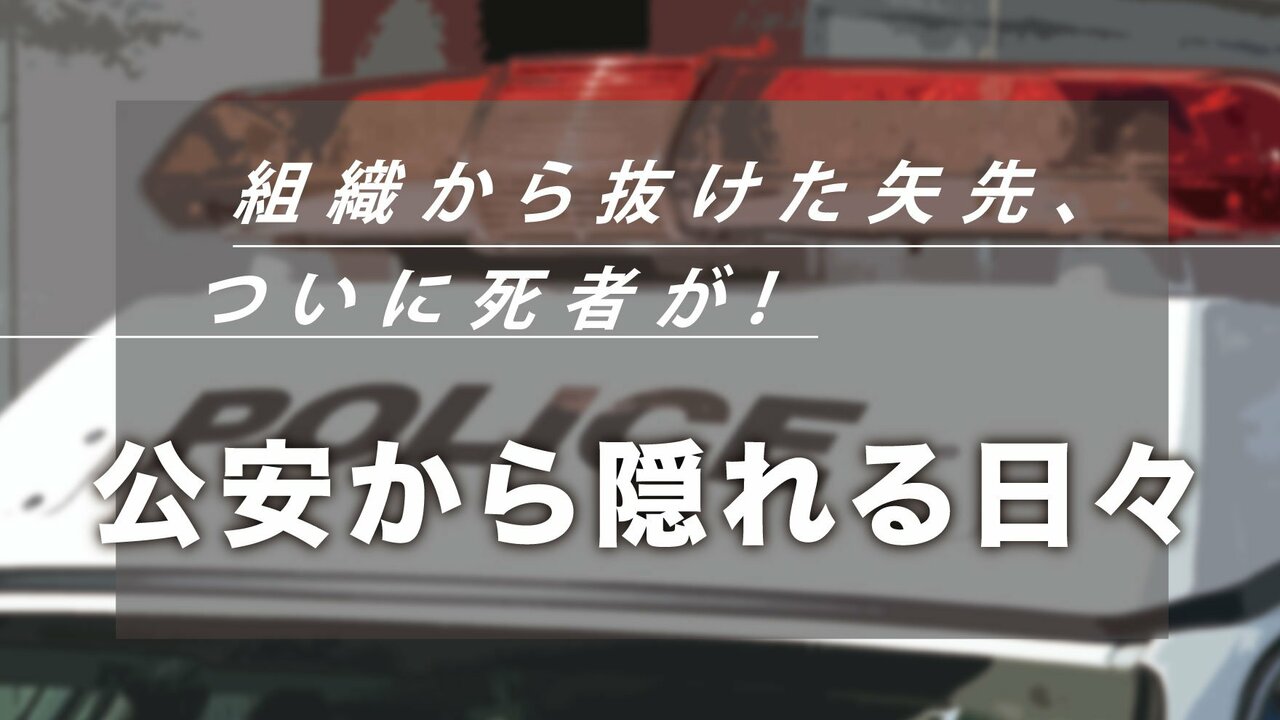止められない党派闘争
全学連は機動隊とそんな衝突を数週ごとに繰り返し、そのつど、私も傷ついたが、戦って自分の汗と血を流すことには爽やかさがあった。それまでの屈辱も恥辱も洗い流されていくようだった。初めの頃は部隊の中ほどにいたが、すぐに馴れて部隊の先頭をやるようになった。全学連の先頭はW大がやり、W大の先頭は一文がやったのだ。
負傷のほとんどは殴られることによる打撲傷だったが、傷つくことは勇気の証しには違いなかった。私は白い包帯の巻かれた腕を三角巾で吊り下げた格好で、W大のキャンパスを闊歩した。傷だらけの青春には心なしか誇らかなロマンがあったのだ。
四月の末、運動の最中に亡くなった仲間の追悼のために、仲間たちと駒場のT大に行った。その構内は広々としていて、どこか片田舎に帰ったような気がした。誰が吹くのか夕暮れの寮から流れるトランペットの調べが物憂かった。
そこで全学連はxx派の立て籠もった学生寮を包囲し、夜になると、一文だけ残って躑躅の植え込みに、鉄パイプを持たされて身を潜めた。「出てきたら叩け」と言われてまんじりともせずに一夜を明かした。結局、誰も出てこなくて安堵の溜息を吐いた。
私はそのあとのミーティングで意見を聞かれると、「権力と戦うのはいいが、党派と戦うのは下らない」と言った。しかし、私がいくら反対しても、私が部隊の中にいるかぎり、部隊のなす党派闘争に巻き込まれていくのだった。
幾度となく闘争を繰り返した一学期が過ぎて、夏休み、米軍の相模原補給廠からベトナムへ戦車を輸送するのを阻止する闘争が始まった。弾圧は熾烈を極め、私が加わった現闘の部隊は、機動隊に一晩中、引き回され、私は警棒で殴られ続けて病院に運ばれた。背中が腫れあがって熱をもっていた。全治二週間の怪我ということだった。
医者は「私は君のような人間(自分の命を粗末にする人間)は嫌いだ」と言った。そして「君は(こんなことをしていたら)死ぬぞ」と言った。私はその温情に感謝して俯いた。私は変わりようがないと思ったのだ。
私自身であり切ることを通して、永遠的なもの(真の共同体)に回し向けられていくことは、私の手放すことのできない主義であり、信仰であり、実存だった。青春の私はそれをもって、この世に受け入れられることは、決してないであろうという悲しさを、この世に対する絶望的な闘争として表わして生きていた。
私はマルクスの名の下に自分の実存(信仰)を貫いて生きていた。私はその中で容易に十七歳の行動ニヒリズムにも帰れたし、十八歳の原始キリスト教(共産主義の源流)にも帰ることができた。確かに、そのためには死んでもいいと思ったのだ。