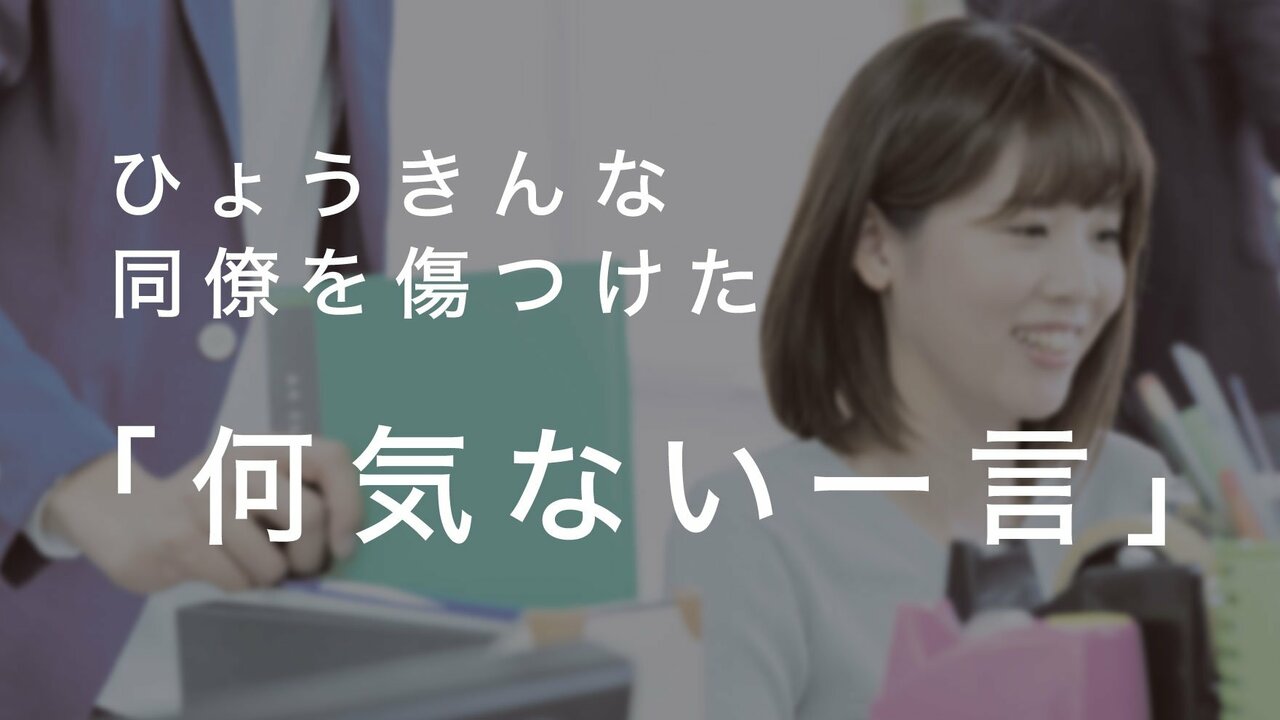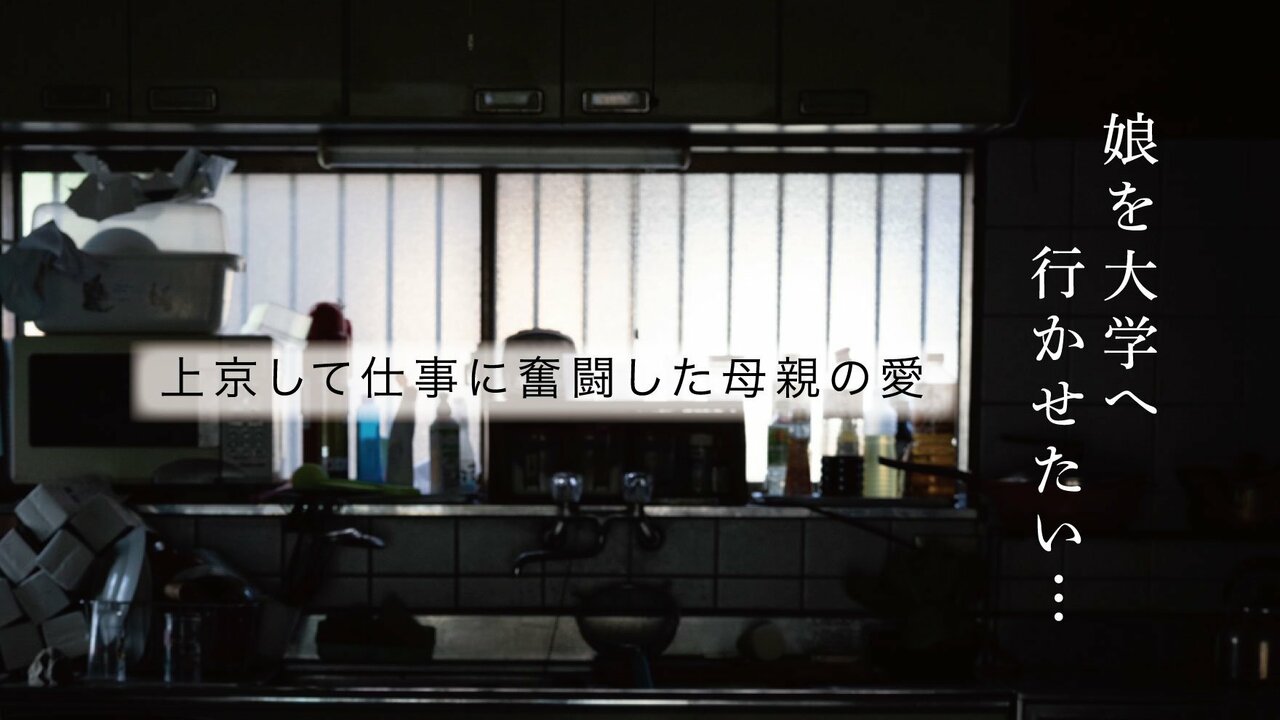親腹七日
母が長野で一人暮らしをしていた頃、私は毎年お盆に帰省した。母の食事の盛り付けは何でも『たっぷりに』が基本である。
「『親腹七日』っていうからなあ、たくさん食べていけ」
とよく言われた。
『親腹七日』とは実家に帰ったらたらふく食べて、婚家に戻っても七日間はひもじい思いをしなくて済むように、という意味である。それからお酒の好きな母は、飲めない私を相手にいつも同じ話をした。
母の実家は農家で、戦争中もそれほど食べ物には困らなかった。嫁いだ先は舅が県庁に勤めていた。父が出征したあと、小姑三人を含めて家族六人、食べ物に不自由したらしい。食事は粉ものとか芋とか、母の苦手なものが多かった。
「栄子におにぎりを一個、昼休みにこっそり持ってきてくれるように頼んだのよ」
と言う。運よく妹の栄子叔母が、嫁ぎ先の近くに働きに来ていたのである。
しかし今と違って携帯電話があるわけではない。彼女は昼休みにおにぎりを持って、母の家の近くをうろうろする。しかしそうと気づいたかどうか、姑は母が外に出られないよう、用事を言いつける。妹はそのうち職場に戻ってしまう。母はおにぎりにありつけない。
「あの意地悪な姑が……」
と、話す度に腹を立てている。
「えーっ、自分だけお米にありつこうとしたわけ?」
なんて突っ込もうものなら、いかに空腹だったか話は一時間長くなる。里帰りしたときは、さぞかし『親腹七日』とたっぷり食べたことだろう。母は死ぬまで、粉ものである信州名物おやきが嫌いだった。
食べ物が豊富な現代で、一人暮らしなのに『親腹……』と食べて東京に戻ると、私はいつも一キロ太っている。悩みの種であった。母が九十三歳で亡くなり、今年は墓参りを兼ねて姉の家に帰省した。やっぱり一キロ太った。
「お宅に来ても太ったわ。ずうずうしく『親腹七日』をしちゃったかしら」
「いいじゃないの」
と姉は笑って、自分の家の菜園で採れた茄子や胡瓜を、「ちょっと荷物になるけど」と、持たせてくれるのであった。