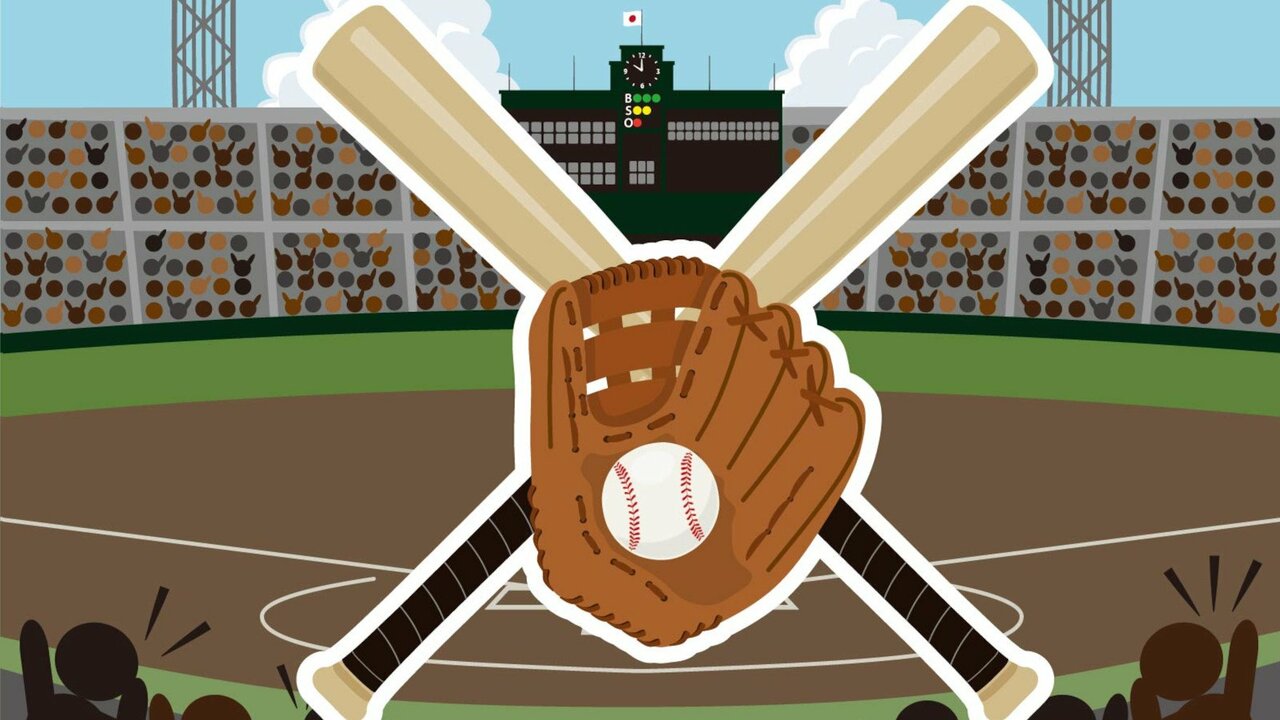ライジング・ウルフは一人荒野を行く。腹が減れば鹿や野鳥を仕留め、その肉を貪る。喉が渇けば川の水をしたたか飲み、くたびれれば満天の星空を見ながら眠る。その繰り返しの中、彼は常に思索に耽っていた。
思考よりも肉体を躍動させること、それだけが彼の生き方だったが、己自身、生まれて初めて、自分は何のために生きるのか、疑問に思ったのだ。生きる価値を見出すことができず、さまよっていたある陽光の日、彼は驚くべき光景を目の当たりにした。それは、皮だけが剥がれたバッファローの死体の群れであった。
インディアンは、バッファローを天からの贈り物と考え、成獣しか狙わない。そして、仕留めた獲物は、肉や内臓はもちろんのこと、骨や髄、皮や蹄まで、全てを利用する。それこそが、バッファローへの供養となる、そう考えるのが常であったが、この光景は理解の範疇を大きく超えていた。
「白人の仕業か……。彼らには、自然や動物に対する敬意や感謝がない……」
そう呟くと、ウルフは身を清め、腰みの一つの半裸となり、顔を赤と青に塗った。頭と手首にセージの輪を嵌め、鷲の骨の笛を唇に挟み、それを吹きながら、太陽に向かい、彼は一人狂ったように踊りを舞い始めた。見る者に畏れと悲しみを抱かせる、死者のための鎮魂の踊りであった。
ウルフは、日の出から日没まで踊り、それを4日続け、失神した。